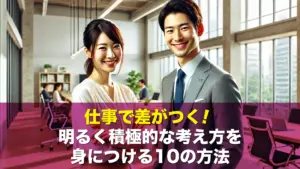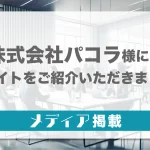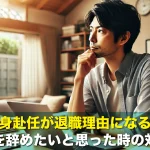職場でのちょっとした一言に、ついカッとなったり、思わず言い返したくなってしまった経験はありませんか?「売り言葉に買い言葉」そんな感情的なやりとりは、相手との関係を悪化させるだけでなく、自分自身の心も大きくすり減らしてしまいます。でも、毎日忙しい中で感情をコントロールするなんて、なかなか簡単なことではありませんよね。
だからこそ大切なのは、「イライラしないように我慢する」ことではなく、「どうしたらイライラとうまく付き合えるか」を考えることです。本記事では、職場で感じるイライラをやわらげ、冷静に対話できる自分を育てるための10の思考法をご紹介します。
感情の構造を知ること、思考に一呼吸を挟むこと、共感力を育てること。こうした心の習慣を少しずつ身につけることで、これまでとは違った落ち着いた関わり方が見えてくるはずです。売り言葉に買い言葉で疲れた日々から、自分のペースで心穏やかに働ける毎日へ。あなたらしく仕事に向き合うためのヒントを、ぜひ見つけてみてください。
この記事の目次(タップでジャンプ)
1. 感情の連鎖を断ち切るために必要な意識の持ち方

日々の仕事のなかで、ふとした一言にカチンときたり、誰かの態度にイライラしたりすることは、決して珍しいことではありません。むしろ、人と関わって仕事をしていく上では、ごく自然に起きる感情の動きとも言えるでしょう。ただ、その感情が思わず口から出た強い言葉につながってしまったり、相手の発言に売り言葉で返してしまったりすると、思いもよらない方向に関係がこじれてしまうこともあります。そうならないためには、感情が連鎖的に加速してしまう前に、立ち止まって意識を切り替えることがとても大切です。
その第一歩は、「これは本当に反応すべきことなのか?」という問いを、自分自身にやさしく投げかけることです。感情がふくらむときほど、わたしたちは反射的に動いてしまいがちです。でも、ほんの少し視点をずらしてみることで、自分の中に沸き起こっている感情を客観的に見ることができるようになります。
このセクションでは、まず「売り言葉に買い言葉」がどうして生まれるのかを見つめなおし、感情の悪循環から一歩引くための考え方を整理していきます。
売り言葉に買い言葉が起こるメカニズムを知る
誰かにきつい言葉を言われたとき、それに負けじと応戦したくなる気持ちは、自然な感情反応のひとつです。特に職場では、「理不尽なことを言われた」「自分の努力を理解してもらえない」などのもやもやが積み重なっていると、それらが一気に表面化することがあります。その結果、「売り言葉に買い言葉」という応酬が起きやすくなってしまうのです。
この現象の根っこには、防衛本能があります。人間は、攻撃を受けたと感じると、自分を守るために言葉で返そうとするものです。そして、その防衛の手段が時に攻撃になってしまうこともあるのです。つまり、自分の心を守るための言動が、無意識のうちに相手を追い詰める結果になるという、悲しい循環が生まれてしまうのです。
だからこそ、「今、自分は守りたいと思っているのか、それとも攻撃し返したいのか」ということを静かに見つめる時間が大切です。その問いかけができるだけでも、感情の渦に巻き込まれずにすむ第一歩になります。
職場のコミュニケーションに潜む感情のすれ違い
職場という場は、さまざまな価値観や背景を持った人たちが集まる場所です。同じ出来事を見ていても、どう受け取るかは人によって大きく異なります。そのため、「あの人はどうしてあんな言い方をするのか」と感じたり、「なぜ私ばかりが責められるのか」と思ってしまう場面が出てくるのです。
こうした誤解やすれ違いが蓄積すると、次第に感情のハードルが下がっていきます。つまり、小さなことでもイライラしやすくなったり、些細な言葉に過剰に反応してしまったりするようになるのです。言い換えれば、心のセンサーが敏感になりすぎてしまっている状態とも言えるでしょう。
この状態では、たとえ相手が悪気なく言った言葉でも、鋭く聞こえたり、冷たく感じられたりすることが多くなります。だからこそ、まずは「自分が今どんなフィルターで相手を見ているのか」を意識することが大切です。その視点を持つだけでも、余計なイライラを抱えずにすむ可能性が高まります。
反射的な反応ではなく、意図的な選択を意識する
感情に任せて話してしまったあと、「ああ、あんなこと言わなければよかった」と後悔した経験がある人も少なくないでしょう。反射的な言動には、自分自身の意図が置き去りにされていることが多いのです。それに対して、意図的な反応とは、「自分はどうしたいか」「どう伝えたいか」を一度立ち止まって考えたうえで行動することです。
もちろん、すぐにうまくできるものではありません。慣れていないと、怒りや悲しみが先に出てしまうこともあります。それでも、「意図して言葉を選ぼうとする姿勢」を持ち続けることが、感情を整える力を少しずつ育てていく土台になります。
意図的な選択をするためには、自分の感情と仲良くなることが欠かせません。「今、自分は怒っているんだな」「悔しいと思っているんだな」と、名前をつけてあげるだけで、不思議と気持ちが落ち着いてくることがあります。感情を否定するのではなく、受け止めて扱っていくことが、自分と他人を傷つけない行動につながっていくのです。
2. イライラの正体を見極める内省の技術
職場で感じるイライラは、ただの気分のムラや相手のせいだけではなく、自分の心の奥にあるさまざまな感情や思い込みが絡み合って生まれていることが少なくありません。その場では「なんでこんなに腹が立つんだろう」と感じていても、少し時間をおいて振り返ってみると、怒りの裏にある別の感情に気づくことがあります。
たとえば、認めてもらいたかったのに無視されたと感じた寂しさや、責任を押し付けられているように思えて苦しかった経験が、怒りという形で噴き出していることもあります。そうした感情の構造に気づいていくことは、イライラの連鎖を断ち切る大きなヒントになります。
ここでは、自分の中にある「本当の感情」に出会い、対話していくための内省の考え方や方法を紹介します。内側を丁寧に見つめることで、無意識に引き起こしていた売り言葉に買い言葉の応酬を、ぐっと減らすことができるようになります。
自分の中にある期待や前提を見直す
イライラの根っこには、「こうあるべき」という無意識の期待や前提が存在していることがあります。たとえば、「上司はちゃんと部下を気にかけてくれるべきだ」とか、「同僚なら手が空いていたら手伝うのが当たり前だ」といった思いがあると、その通りにいかない現実に出会ったとき、大きなストレスを感じてしまいます。
もちろん、そうした期待自体が悪いわけではありません。でも、それが強すぎたり、あまりに当然のことと決めつけていたりすると、現実とのズレに耐えられなくなってしまいます。そのズレこそが、イライラという感情を呼び起こすきっかけになります。
自分がどんな前提で人や状況を見ているのかを知ることは、感情の負担を軽くする第一歩です。そして、その前提を少し緩めたり、「そうでない人もいる」と受け入れる幅を持つことで、心の揺れが少しずつ穏やかになっていきます。
怒りの奥にある感情を丁寧に読み解く
怒りという感情は、実はとても強いエネルギーを持っています。でも、その力強さの裏側には、「わかってほしい」「傷ついた」「苦しい」といった、もっと繊細でやわらかい感情が隠れていることが多いのです。
たとえば、ある人に注意されたときにイラッとした自分がいたとします。でも、その感情を丁寧にたどっていくと、「頑張っているのに否定された気がした」とか、「自分の努力が認められなかった寂しさ」が見えてくることがあります。こうした感情は、普段なかなか表には出しにくいものです。でも、自分自身ではその存在に気づいていることが多いのです。
そうした本音に寄り添ってあげることで、「怒りでしか表現できなかった自分」が、少しずつ言葉を取り戻していきます。そして、そうなると、売り言葉で返したくなるような状況でも、「今はまだ反応しないでおこう」と自分を落ち着かせることができるようになります。
ストレスの根源を具体的に言語化する習慣
なんとなくイライラする、なんとなく不快…そんなふうに「なんとなく」で済ませてしまっている感情は、しだいに体や心に澱のようにたまっていきます。その結果、ある日突然、怒りとなって噴き出してしまうこともあります。
そうならないために大切なのは、自分がどこで、何に対して、どう感じたのかを、なるべく具体的に言語化することです。「朝の会議で話をさえぎられて、無視されたように感じた」「自分の担当範囲以上の仕事を当然のように押し付けられたとき、不公平に感じた」など、できるだけ状況と言葉をリンクさせて記録してみると、自分の感情が整理されやすくなります。
この習慣は、ノートでもスマホのメモでも構いません。1日1行でも「今日はこんなことでモヤモヤした」と書き出すだけでも、感情が整ってくるのを感じられるようになるでしょう。言葉にすることで、自分が抱えているストレスの輪郭がはっきりしてきて、そのぶん、自分自身との付き合い方がやさしくなっていきます。
3. 一呼吸おく思考のトレーニング

仕事中、誰かの言葉や態度に強く反応しそうになる瞬間、そんなときこそ「一呼吸おく」ことが大切です。けれど、「それができたら苦労しない」と感じる方も多いかもしれません。確かに、感情が高ぶっている最中に冷静さを取り戻すのは簡単なことではありません。しかし、その「難しさ」を受け止めたうえで、自分の思考にほんの少しだけ間を作る練習を続けていくと、次第に感情に巻き込まれない時間が増えていきます。
「一呼吸おく」とは、ただ黙るという意味ではありません。自分の気持ちを押し殺すわけでもありません。それは、自分自身の内側に意識を戻し、「いま何が起きているのか」「どんな気持ちになっているのか」を確認するための大切な時間です。この短くて静かな時間が、自分の言動を選ぶ自由を与えてくれるのです。
ここでは、「一呼吸おく」というシンプルながら効果的な考え方について、実際に職場で活かせる視点を丁寧にひもといていきます。
瞬間的な反応を抑える身体感覚の使い方
怒りやイライラといった感情は、言葉よりも先に体に現れることが多くあります。たとえば、心臓がドキドキする、呼吸が浅くなる、肩や首が緊張するなど、体は常に感情を反映しているのです。そのため、感情に気づく前に、まず体の反応に意識を向けることで、自分の変化をいち早くキャッチすることができます。
一番簡単な方法は、「呼吸」に意識を戻すことです。誰かにきついことを言われたとき、あるいは予想外の出来事が起きたとき、すぐに反応せず、そっと自分の呼吸のリズムを感じてみるだけでも、感情の勢いが少しずつ落ち着いてきます。
また、軽く背筋を伸ばす、足の裏を床にしっかりつける、手を握ってからゆっくり開くなど、簡単な身体感覚へのアプローチも効果的です。身体を整えることで、心の余裕も自然と戻ってくるのです。
「いま何を感じているのか」を言葉にする練習
感情が大きく動いているとき、頭の中では「なんであんな言い方するの?」「もう無理!」といった思考がぐるぐる巡っていることがあります。でも、その言葉の奥には、まだ明確に言葉にできていない感情が潜んでいることが多いのです。
その感情に近づくためには、「いま、私は何を感じているのだろう?」と静かに自分に問いかけることが役立ちます。「悔しい」「寂しい」「傷ついた」「疲れた」など、感情に具体的な名前をつけてあげると、ふわふわしていた気持ちがすっと落ち着いてくることがあります。
この練習は、声に出さなくても、頭の中や紙に書き出すだけでも構いません。言葉にすることは、自分の内面を整理するための道具です。思考と感情を切り離して整理することで、自分が本当に伝えたいことや行動すべき方向が見えてくるのです。
「沈黙」や「保留」がもたらす効果を理解する
職場では、ときに「すぐに返さなければ」「はっきり反応しなければ」と思ってしまう場面が多くあります。しかし、そうした「即答」や「即反応」が、自分にとって望ましくない結果を生んでしまうこともあります。
そのような場面では、あえて「今は答えられないので、少し考えさせてください」と保留する勇気を持つことが大切です。あるいは、言い返したくなる気持ちがわき上がってきたときに、言葉を飲み込み、深呼吸をしてその場をやり過ごすことも、「沈黙」という大切な対応のひとつです。
沈黙や保留は、決して弱さのあらわれではありません。それは、後悔しない言葉を選ぶための時間であり、自分と相手の関係を守るための行動でもあります。感情の渦の中では勇気が要りますが、その一歩が、自分の思考を丁寧に扱うことにつながっていきます。
4. 相手の言動に引っ張られない心の境界線を持つ
職場でのやりとりは、自分の意思とは関係なくさまざまな言葉や感情が飛び交う場所でもあります。誰かの一言が思わぬトリガーとなって怒りや落ち込みを引き起こしたり、理不尽な態度に心が揺さぶられたりすることは、誰にとっても避けがたいことです。けれども、そのたびに心が翻弄されていては、日々の仕事がとても消耗するものになってしまいます。
大切なのは、「自分の感情は自分のものである」という感覚を持つことです。相手の言葉や態度に影響されることはあっても、それによって自分の行動や気持ちが完全に決められてしまわないようにすること。それが、心に境界線を引くという考え方です。この境界線がしっかりしていると、外からの刺激に動じにくくなり、イライラに飲み込まれにくくなります。
ここでは、感情に飲み込まれないための心の境界線の保ち方を、やさしく整理していきます。
これは自分の課題か?相手の課題か?を区別する
相手が不機嫌そうにしていると、「自分のせいかもしれない」と感じてしまったり、無意識のうちに空気を読みすぎて気を使いすぎたりすることがあります。そうした思考は、責任感のある人ほど陥りやすいものです。けれども、その気遣いが自分の感情を消耗させているとしたら、少し立ち止まって考える必要があります。
そのときに意識したいのが、「これは自分の課題か、それとも相手の課題か?」という視点です。たとえば、誰かが怒っている理由が相手自身の都合や思い込みによるものであれば、それはその人の課題であり、あなたが引き受ける必要はありません。
この区別がつくようになると、「自分ができること」と「自分にはどうにもできないこと」が明確になります。その結果、責任を感じすぎてイライラしたり落ち込んだりすることが、少しずつ減っていきます。
他人の感情に巻き込まれない距離感の整え方
相手が不機嫌そうだったり、否定的な言葉を投げかけてきたとき、「自分までイライラしてしまった」という経験はないでしょうか。人はどうしても、周囲の感情に影響を受けやすいものです。特に繊細な気質を持つ人ほど、相手の感情を自分のもののように感じてしまいがちです。
そうしたときに有効なのが、「心の中でひとつ壁をつくる」イメージです。言い換えるならば、相手の感情と自分の感情を分けて捉えるということです。たとえば、相手の怒りを「この人はいま怒っているようだ」と観察するように捉えると、それに巻き込まれることなく、自分の冷静さを保ちやすくなります。
距離を置くことは冷たいことではなく、自分の感情を守るやさしさでもあります。相手の感情をそのまま背負い込まない練習を重ねることで、イライラを必要以上に引き受ける場面が減っていきます。
反応しない自由を自分に許すという視点
「何か言い返さなければならない」「はっきり主張しなければ負けたように感じる」そんなふうに、職場では時に自分を無理に奮い立たせてしまうこともあるかもしれません。けれど、感情をぶつけ合うことが本当に建設的なやりとりになるとは限りません。
そのため、ときには「反応しない自由」を自分に許してあげることが、とても大切になります。これは「我慢する」とは少し違います。あえて反応しないことを選ぶのは、自分の冷静さや思いやりを守るための、意志ある選択です。
たとえば、売り言葉に買い言葉で応じそうになったとき、「いまは言わない方がいい」と判断することで、後々の後悔や関係の悪化を防げることもあります。自分の感情に正直であることと、感情にすべてを任せてしまうことは違います。その違いを理解することが、心の境界線を築く大きなヒントになります。
5. 相手を理解しようとする共感力を育てる

イライラしてしまう場面では、「どうしてそんな言い方をするの?」と相手を責めたくなったり、「なんでわかってくれないの?」と強く思ってしまうことがあります。ですが、そこで一度立ち止まり、相手の背景や考え方に想像力を向けることができたとき、気持ちの向かい方がぐっとやわらかくなります。
共感とは、相手の言葉に同意することではありません。「そういう考え方もあるのか」「そう感じる理由があるのかもしれない」と一歩引いて相手の立場を想像する姿勢のことです。その視点を持つだけで、売り言葉に買い言葉のような応酬から離れ、自分の心を守りつつ相手との関係を整えていくことが可能になります。
ここでは、共感力を少しずつ育てていくための視点を紹介していきます。
相手の背景や状況に想像力を働かせる習慣
誰かの発言にイライラしたとき、その言葉の背後にどんな事情があるのかを想像してみるのは、とても意味のあることです。たとえば、上司が厳しい口調で話してきたとき、その言葉の奥には業務の責任やプレッシャーがあるかもしれません。同僚がそっけない態度を取ったとき、前日から体調が悪かったり、家庭での悩みを抱えている可能性もあるのです。
もちろん、すべてを理解することはできませんし、無理に相手を肯定する必要もありません。でも、「あの人なりの事情があるのかも」と思えるだけで、自分の感情のとらえ方がやわらかくなります。
想像力を働かせるというのは、相手の言動の意味を自分なりに再解釈することでもあります。その習慣が、イライラの衝動を少しずつ落ち着かせてくれるのです。
攻撃的な言葉の裏にある本当のニーズを探る
怒りっぽい言動やトゲのある口調は、一見すると相手が自分を否定しているように思えてしまいます。けれど、その奥には「助けてほしい」「認めてほしい」「わかってほしい」という気持ちが隠れていることがあります。
たとえば、「こんなの間違ってるだろ!」と強く言ってくる人がいたとします。その裏には、「自分の意見を聞いてもらえていない」と感じていたり、「自分の立場が脅かされている」という不安があるかもしれません。
そう考えると、怒りをぶつけてくる相手もまた、誰かに理解されたいと願っているのかもしれないという見方ができます。すべてを受け止める必要はありませんが、少しでも「この人にも何か事情があるのかも」と思えたとき、自分自身の感情も穏やかになり、反応も自然と変わっていきます。
「分かってもらいたい気持ち」に焦点を当てる
誰かにイライラしたとき、その奥には「本当は自分がわかってもらいたかった」という気持ちがあることがよくあります。たとえば、「もっと丁寧に扱ってほしかった」「一言ねぎらってほしかった」「ちゃんと評価してほしかった」といった、ちょっとした願いが満たされなかったことによる寂しさや不満が、怒りに形を変えて表に出てきているのです。
そのことに気づいたとき、相手の態度に目を向ける前に、「自分は本当はどうしてほしかったのか?」という問いかけができるようになります。そうすることで、イライラの原因が少しずつクリアになり、無意識に反応していた売り言葉に買い言葉のパターンを手放すことができるようになります。
また、「相手ももしかしたら、わかってもらえずに傷ついていたのかもしれない」と思える瞬間があると、怒りの感情は不思議とやわらいでいきます。共感は、誰かのためだけではなく、自分の心をやさしく守る力にもなるのです。
6. 冷静な言葉選びで職場の空気を整える
言葉は、人との関係性を築くための大切な橋渡しでありながら、同時に関係を壊すきっかけにもなり得ます。職場のように多くの人と日常的にやりとりをする環境では、何気ない一言がイライラの火種になったり、意図しないすれ違いを生むことも珍しくありません。だからこそ、「どんな言葉を使うか」という選択には、日々の空気を少しずつ穏やかに整えていく力があります。
冷静に言葉を選ぶことは、自分の感情を押し殺すことではなく、「どんなふうに伝えたら、お互いにとってやさしいやりとりになるか」を考えるということです。そして、その積み重ねが、自分自身のイライラを和らげ、売り言葉に買い言葉のような対立を避けることにつながっていきます。
このセクションでは、職場での言葉の使い方について、少し意識を変えるだけで実感できる工夫を紹介します。
強い言葉の裏にある無意識の影響を知る
怒っているときや焦っているときに、つい言葉が乱暴になってしまうことは誰にでもあります。ですが、「どうしてこんな言い方になってしまったんだろう?」と後から振り返ったとき、そこには自分でも気づいていなかった不安や焦り、無力感が隠れていることがあります。
強い言葉というのは、往々にして自分を守ろうとする働きでもあります。とくに職場では、「ちゃんとしている自分でいたい」「なめられたくない」といった気持ちが無意識のうちに働いていて、それが攻撃的な口調となって現れるのです。
その仕組みに気づくだけでも、「今の自分は守りに入っていたのかもしれない」と客観的に自分を見ることができます。そして、その視点があることで、次に同じような場面が訪れたときに、少し立ち止まる余裕が生まれるのです。
主語を「私」にして伝えるアサーティブな表現
相手に何かを伝えるとき、「なんでそうするの?」や「あなたはいつも…」という言い方をすると、どうしても非難や責めの印象が強くなり、相手の防御反応を引き出してしまいます。すると、会話は対立の方向へ進んでしまいがちです。
そこで大切なのが、「私はこう感じた」「私はこうしてほしい」といった、自分を主語にした表現です。これはアサーティブ・コミュニケーションと呼ばれ、自分の気持ちや考えを率直に伝えながらも、相手を尊重する姿勢を大切にする話し方です。
たとえば、「報告が遅いと困るんです」ではなく、「私は、報告がもう少し早いと助かります」と伝えるだけで、受け取る側の印象がやわらかくなります。こうした言い方の工夫は、自分のイライラを抑えるだけでなく、相手の反応も穏やかに変えていく助けになります。
「指摘」ではなく「共有」でトーンを和らげる
職場では、意見の違いやミスの指摘が避けられない場面も多くあります。でも、その伝え方ひとつで、相手の受け取り方は大きく変わります。たとえば、「これは違います」ときっぱり言うのではなく、「こういうやり方もあると思ったのですが、どうでしょうか?」というふうに言い方を変えるだけで、話のトーンがぐっと和らぎます。
「指摘」はどうしても上下関係を意識させやすく、相手の自尊心を傷つけてしまう可能性もあります。それに対して、「共有」は対等な目線でのやりとりを前提としているため、相手も身構えずに話を聞きやすくなるのです。
大切なのは、「相手に伝える目的は何か」を明確にすることです。間違いを正すためなのか、より良い方向に進めたいのか。その目的が「責めること」ではないなら、伝え方も自然と穏やかなものになっていきます。
7. 感情の処理と発散の仕方を整える

職場でのイライラは、その場で表に出さなかったとしても、心の中でくすぶり続けてしまうことがあります。「ここでは言えないから」と感情を押し込めているうちに、次第に疲れがたまり、他の人との関係にまで影響してしまうこともあります。感情はしまいこめば消えるものではなく、むしろ内側に積もっていく性質を持っています。だからこそ、感情を上手に「出す」「整える」方法を持つことがとても大切です。
このセクションでは、怒りやモヤモヤを健やかに扱うための視点として、感情の処理と発散の仕方について考えていきます。感情をため込まないことは、売り言葉に買い言葉というような衝突を避けるための、静かだけれど確かな支えになります。
モヤモヤを言葉で吐き出す場を作る
どんなに冷静にふるまっていても、心の中で「納得できない」「悔しい」「傷ついた」と思っていることは、どこかに表現しないと収まらないものです。そうした気持ちを安全に外に出すためには、信頼できる相手との会話や、ひとりで自由に書ける場所が役に立ちます。
たとえば、家族や友人に「ちょっと話を聞いてほしい」とお願いして、ただ気持ちを吐き出すだけでも、心は少し軽くなります。相手にアドバイスを求める必要はありません。話すことそのものが、気持ちの整理につながるからです。
また、声に出せないときには、ノートやスマホのメモに「今日はこんなことがあって、こう感じた」と書くだけでも効果があります。誰にも見せない言葉なら、本音で書くことができ、それだけで感情が静まってくることも多いのです。
書く・動く・声に出すで感情を体外に出す
感情は心の中にだけあるものではありません。体の感覚や動き、呼吸と深く結びついているため、言葉で出すだけでなく、「体を使って放出する」ことも非常に有効です。たとえば、イライラしたときに数分間ウォーキングをしてみたり、好きな音楽にあわせて軽く体を動かしたりすると、感情がスーッと流れていくのを感じることがあります。
また、誰もいない場所で声を出すというのも有効です。誰かに向けてではなく、「あーもう、なんでこんなに疲れるんだろう」とか「ちょっと言わせてもらいたい」と自分の気持ちを口に出すことで、驚くほど心がスッキリすることがあります。
「書く」「動く」「声に出す」どれも特別な準備はいりませんが、自分にとって心地よい方法を見つけておくことで、感情のメンテナンスがしやすくなります。
他人ではなく自分で自分をケアする方法
感情が大きく揺れたとき、つい「誰かにわかってほしい」「助けてほしい」と思うことは自然なことです。でも、いつも他人の反応に自分の心を委ねてしまうと、満たされない気持ちが積み重なっていきます。
そんなときこそ、「いま、自分はよく頑張っているな」「つらかったよね」と、自分で自分を認めてあげることが、心の回復につながります。誰かの言葉を待たなくても、自分の内側にあるやさしい声を聞くことはできるのです。
たとえば、1日を終えて「今日もよくやった」と小さく声に出してみたり、お風呂の中で「今日は嫌なことがあったけど、乗り切れたね」と心の中でつぶやく。それだけでも、自分を大切にする感覚が育っていきます。
売り言葉に買い言葉で感情を荒らすのではなく、自分の心にやさしい言葉をかける習慣が、イライラの連鎖を断ち切る手助けになってくれます。
8. 日常的に感情を整えるルーティンを持つ
職場で感じるイライラは、突発的に起きるようでいて、実は日々の心と体の状態が大きく関係しています。睡眠が足りていなかったり、食事のタイミングが乱れていたり、プライベートでの疲労が積み重なっていたりすると、普段なら気にならないような言動にも敏感になってしまうことがあります。
だからこそ、「イライラしないように気をつける」という努力だけでなく、日常の中で感情を整える習慣。ルーティンを持っておくことが大切になります。心が整っていると、売り言葉に買い言葉といった反応的なやりとりに巻き込まれにくくなり、自分らしい穏やかさを取り戻すことができるようになります。
このセクションでは、気持ちを安定させるために日常でできる小さな工夫についてお伝えします。
朝や休憩時間にできる小さな習慣
1日の始まりにどんな気持ちで過ごすかは、その日全体の感情の流れに影響を与えます。たとえば、出勤前の数分間に「今日も大丈夫」と自分に声をかけたり、お気に入りの飲み物をゆっくりと飲むだけでも、気持ちが整いやすくなります。
また、午前と午後の仕事の区切りで小さな休憩を取ることも、感情のリセットに効果的です。深呼吸を数回する、窓の外を見る、少し歩いてみるなど、短時間でも意識的に「いったん止まる」時間をつくることで、気持ちに余白が生まれます。
こうした習慣は大げさなものでなくて構いません。続けやすく、気持ちが穏やかになる方法を自分なりに見つけていくことが、心の健やかさにつながっていきます。
栄養・睡眠・リズムを意識した生活整備
感情の波が大きいと感じるとき、実は身体のコンディションが影響していることもあります。寝不足の日はイライラしやすかったり、空腹のときは言葉がきつくなってしまったりという経験がある人も多いのではないでしょうか。
日々の栄養バランスや食事のタイミング、睡眠時間の確保は、感情を穏やかに保つ土台になります。たとえば、糖質やカフェインの取りすぎを避ける、就寝前にスマートフォンの画面を見ないようにする、といった小さな工夫を積み重ねることで、心のゆとりが少しずつ育っていきます。
生活のリズムが整っていると、無意識のうちに気持ちが安定していることに気づくようになります。毎日の積み重ねが、自分の感情に振り回されない自分を育ててくれるのです。
イライラしやすいタイミングを事前に知る
「この曜日は会議が多くて疲れる」「この部署の人と話すと緊張する」といった、自分の中の“イライラしやすいポイント”をあらかじめ把握しておくことは、感情を整えるための大きなヒントになります。
たとえば、毎週水曜日の午後は忙しくなりがちで心に余裕がなくなる、などの傾向を知っていれば、その時間帯は無理な予定を入れないようにしたり、あえて意識的に休憩を多めに取るようにしたりと、事前に対策をとることができます。
また、「あの人と会話するときは反応が気になる」といった場合でも、事前に「今日はあまり深く受け止めないようにしよう」と自分に言い聞かせておくだけで、心の構えができてイライラをセーブしやすくなります。
感情は完全にコントロールできるものではありませんが、自分の傾向を知っておくことは、感情と上手につきあうための大切な第一歩になります。
9. 建設的な対話に導く思考の土台をつくる

仕事の中で誰かと意見が食い違ったり、自分の考えがうまく伝わらなかったとき、つい感情が先に立ってしまいそうになることは誰にでもあります。そんなときに、少しでも穏やかに、そしてお互いのためになるやりとりができるようにするには、自分の思考の土台をしっかりと育てておくことが必要です。
建設的な対話とは、ただ話し合うだけではなく、「どう伝えれば相手に届くか」「どう聞けば相手を理解できるか」を意識して進めていく会話のことです。売り言葉に買い言葉のような衝突を避け、前向きなコミュニケーションを育てるための視点について、ここでは一緒に考えてみましょう。
相手と議論するのではなく、対話する意識
議論という言葉には、「どちらが正しいかを決める」というニュアンスが含まれています。職場でも、何か問題が起きたときに「自分の正しさ」を証明したくなってしまう場面はあるでしょう。しかし、その気持ちのまま話し合いを進めていくと、相手もまた「自分は間違っていない」と主張し始めてしまい、対立が深まるばかりになります。
一方で、「対話」は、勝ち負けではなく「違いを理解すること」を目的としています。たとえ意見が違っても、「そう考える理由があるのかもしれない」と一歩引いて捉える姿勢があれば、感情的なぶつかり合いは避けられます。
対話の中で大切なのは、自分が話すときだけでなく、相手が話しているときにも心を向けることです。そして、「なぜこの人はこう感じているのだろう?」と、相手の立場に思いを寄せること。それだけで、空気はずいぶん変わります。
自分がどうしたいかを軸に考えることの意味
誰かの言動にイライラしてしまったとき、その怒りの矛先を「どうしてあんなことを言うの?」というふうに、相手に向けてしまいがちです。でも、そこで「自分はどうしたいのか?」という視点に切り替えることで、感情の流れを自分の中で止めることができます。
たとえば、「私はこの状況をどう改善したいのか」「どんな関係を築きたいと思っているのか」と自問することができれば、売り言葉に買い言葉のような反射的なやりとりを避けて、建設的な行動に目を向けることができます。
「どうしてくれるの?」という問いかけは相手に依存しますが、「私はどうしたいか」という問いは、自分の意思に立ち戻る力になります。自分の中に軸を持つことが、冷静さと落ち着きを取り戻す大切なポイントになります。
意見の違いと人格否定を切り離して考える
職場では、立場や視点の違いから、意見が食い違うことは日常的にあります。しかし、意見が違うというだけで、「この人とは合わない」「もう話したくない」といった極端な感情にまで発展してしまうのは、とてももったいないことです。
意見の違いは、その人の考え方や状況によるものです。それは決して、その人自身を否定するものではありません。けれども、つい感情的になってしまうと、「私の考えを否定された=私という存在を否定された」と受け取ってしまいがちです。
そこで意識したいのが、「意見の違いは、人格の違いではない」という視点です。たとえ考え方が合わなくても、その人なりに理由や背景があるということを理解しておけば、自分自身も攻撃されたように感じにくくなります。
この考え方を持つだけで、対話の場で自分の気持ちを守ることができるようになりますし、相手の言葉にも過剰に反応せずにすむようになります。
10. 職場で自分らしさを失わないための思考習慣
仕事に真剣に向き合えば向き合うほど、職場での評価や周囲との関係、役割の期待に振り回されてしまうことがあります。「こうあるべき」「ちゃんとしなければ」という思いが強くなりすぎると、少しの言葉や態度に深く傷つき、自分の感情が大きく揺さぶられるようになってしまいます。
そんなときに大切なのが、「自分らしさを保つ」ことです。自分の考えや気持ちに立ち返る時間を持つことで、たとえ職場でイライラすることがあっても、心の中心を見失わずにすむようになります。ここでは、周囲に流されすぎずに穏やかに働き続けるための、内面的な土台を整える思考習慣について考えていきます。
自己評価を他者の反応に委ねない強さ
誰かに褒められたり認められたりすると、自分の存在が肯定されたように感じてうれしくなるものです。でもその一方で、誰かに冷たくされたり否定的な言葉をかけられると、まるで自分のすべてが否定されたかのように感じてしまうこともあります。
それは、自己評価の土台が「他者の反応」に置かれている状態です。この状態が続くと、自分の価値が周囲の言葉や態度によって揺れ動き、自信を保つことが難しくなります。
そこで意識したいのが、「自分がどう感じているか」「自分がどうありたいか」に目を向けるという視点です。「あの人はああ言ったけれど、自分はこう感じている」というように、自分の感覚を一番大切にすることで、少しずつ心の軸が整っていきます。
周囲の言葉はあくまでひとつの意見であり、それがすべてではありません。そう思えるようになると、イライラする出来事があっても、自分を取り戻すスピードが速くなっていきます。
「完璧さ」ではなく「安定」を基準にする視点
完璧であろうとすると、少しのミスや予想外の出来事にも過敏に反応してしまいがちです。そして、誰かの指摘や批判に対しても「やっぱり自分はだめだ」と必要以上に落ち込んでしまうことがあります。
でも、そもそも仕事には予期せぬことがつきものです。すべてを完璧にこなそうとするよりも、「今日はこれができたからOK」「昨日より少しだけ前に進めた」といった、自分なりの安定したリズムを持つことの方が、ずっと健やかで続けやすい働き方につながります。
「うまくやらなければ」ではなく、「穏やかに続けていくにはどうすればいいか」と考えることで、気持ちの余裕が生まれます。その余裕が、売り言葉に買い言葉で反応してしまうような瞬間に、ふと心を落ち着けてくれる支えになるのです。
自分のペースを大切にすることで得られる安心感
職場にはいろいろな人がいて、それぞれに仕事の進め方や考え方があります。周囲が忙しく動いていたり、声の大きな人がいたりすると、自分も合わせなければと焦ってしまうこともありますが、自分のペースを無理に変えることが必ずしも正解とは限りません。
むしろ、自分が心地よく、持続的に働けるリズムを知っておくことは、長い目で見たときに大きな財産になります。「私はこういうときに集中できる」「このタイミングで休憩を取ると調子が戻る」といった、自分の傾向を大切にすることで、感情の揺れ幅も小さくなっていきます。
誰かのスピードに合わせて疲弊するのではなく、自分のペースを尊重する。そうすることで、職場でのイライラも少しずつ減り、自然体で過ごせる時間が増えていくはずです。
まとめ
仕事の場でイライラしてしまうことは、決して特別なことではありません。むしろ、真面目に取り組んでいるからこそ、他人の言動に敏感になったり、自分の思い通りにいかない現実に落胆したりすることがあるのだと思います。ただ、そうしたイライラがたびたび募ると、売り言葉に買い言葉という悪循環を生み、人間関係の溝が深まったり、自分の心がすり減ってしまうこともあります。
今回ご紹介した10の思考法は、感情を押し殺すためのものではありません。むしろ、感情と向き合い、丁寧に扱いながら、より心地よく働くための道しるべです。怒りの裏にある本当の気持ちを知ること、身体の反応に気づいて立ち止まること、共感や自己理解の力を育てること…。どれも、日々のちょっとした意識の積み重ねが、やがて自分の心を守る強さへと変わっていきます。
すぐにすべてを完璧に取り入れる必要はありません。自分が「やってみよう」と思えるものから、ひとつずつ取り入れてみてください。たとえば、朝の深呼吸を習慣にするところからでもいいのです。それが、誰かの言葉に心を乱されずに済む第一歩になります。
仕事の中で大切なのは、成果だけでなく、そこに向かうプロセスや人との関わり方を、自分なりに気持ちよく整えていくことです。そして、そのためには、自分の感情を理解し、大切にすることが何よりの基盤になります。言葉に振り回されず、自分らしい穏やかさを持って働けるようになることで、職場での過ごし方や人との関係も、少しずつ変わっていくはずです。
どうか、自分にやさしい思考法を味方にして、今日も静かな自分らしさを育んでください。