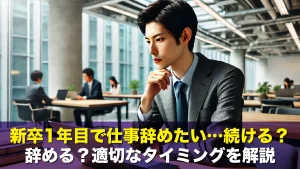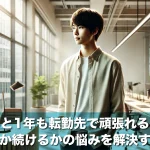仕事ができる人とそうでない人の違いは、特別なスキルや能力だけではなく、日々の何気ない行動にも表れます。仕事ができる人は、意識せずとも当たり前のように実践していることが多く、それが成果や信頼につながっています。しかし、実際に「当たり前の行動」と言われても、自分がどれだけできているのか、どの部分を改善すべきなのかを具体的に把握するのは難しいかもしれません。
この記事では、仕事ができる人が自然に行っている10の行動を紹介します。これらは特別な努力をしなくても、日々意識をすることで少しずつ身につけていくことが可能です。今すぐに実践できることも多く、少しの工夫で仕事の質を向上させることができるでしょう。
また、仕事ができる人の行動には、共通した考え方や習慣があります。ただ漠然と「仕事を頑張ろう」と思うのではなく、具体的に何をすれば良いのかを知り、少しずつ実践していくことが大切です。本記事を通じて、自分の仕事のやり方を振り返り、より良い働き方を目指すきっかけになればと思います。
それでは、仕事ができる人が自然にやっている当たり前の行動を見ていきましょう。
この記事の目次(タップでジャンプ)
1つめ「時間を無駄にしない工夫をしている」

仕事ができる人は、限られた時間を有効に活用し、効率的に仕事を進めることを自然に行っています。時間は誰にとっても平等であり、一日は24時間しかありません。しかし、その時間をどのように使うかによって、成果や評価に大きな差が生まれます。
時間を意識せず、なんとなく仕事をしてしまうと、気づいたときには非効率な作業に追われ、本来やるべきことに十分な時間を割けなくなってしまいます。そこで、仕事ができる人は、日々の業務の中で時間を無駄にしない工夫を取り入れ、効率的に仕事を進めることを心がけています。
小さな時間も有効活用する
仕事ができる人は、短い時間でも有効に活用しようとする意識を持っています。たとえば、次の会議が始まるまでの5分間や、移動中の隙間時間など、何もしないで時間が過ぎるのを待つのではなく、その時間でできることを考えています。メールの返信を済ませたり、次の業務の準備をしたり、メモを整理するなど、少しの工夫で時間を有効活用できます。
また、仕事中に少し手が空いたときも、ぼんやりと時間を過ごすのではなく、やるべきことを探し、すぐに取り掛かることで、業務の進行がスムーズになります。特に、次に何をするかが明確になっていると、迷う時間が減り、スムーズに仕事を進めることができます。時間ができたらやろうと思っていたことをリスト化しておくのも、無駄な時間をなくすための一つの方法です。
先を見越した行動を心がける
仕事ができる人は、目の前の仕事だけでなく、その先の流れを意識しながら行動します。たとえば、上司や同僚から依頼された業務を進める際にも、「この仕事が終わったら次に何をすべきか?」を考えながら取り組むことで、無駄な時間を減らすことができます。
また、会議や商談の準備をするときも、ただ当日の内容を確認するのではなく、「この会議の後にどのような対応が必要になるのか?」を想定して準備を進めることで、スムーズに次の業務へ移ることができます。これにより、急な対応が必要になったときでも、余裕を持って仕事を進めることが可能になります。
先を見越すことで、突発的な業務にも冷静に対応できるようになり、無駄な時間を減らすことにつながります。特に、スケジュールが詰まっている場合は、次に何をするかを明確にしておくことで、効率的に仕事を進めることができます。
作業効率を上げるための環境を整える
仕事ができる人は、効率よく仕事を進めるための環境づくりにも気を配っています。たとえば、デスク周りが整理されていないと、必要な資料や道具を探すのに時間がかかり、作業の流れが止まってしまいます。そのため、使う頻度の高いものはすぐに取り出せるように整理し、不要なものは減らすことで、仕事の効率を上げることができます。
また、パソコンのデスクトップやフォルダの管理を適切に行うことも重要です。ファイルが乱雑に保存されていると、必要な資料を探すだけで時間を取られてしまいます。そのため、ファイル名やフォルダ構成を統一し、どこに何があるのかを明確にしておくことで、必要なものをすぐに見つけることができ、作業のスピードが向上します。
さらに、集中して仕事に取り組める環境を整えることも大切です。周囲の雑音が気になる場合は、ノイズキャンセリングイヤホンを使用する、集中できるスペースを確保するなど、自分にとって最適な環境を作ることで、仕事の効率を上げることができます。
仕事ができる人は、限られた時間を最大限に活用する工夫を常に意識しています。小さな時間を無駄にせず、次に何をすべきかを常に考えながら行動し、作業環境を整えることで、効率的に仕事を進めることができます。
時間を上手に使うことは、単に仕事のスピードを上げるだけではなく、余裕を持って業務に取り組むためにも重要です。無駄な時間を減らし、効率的に仕事を進めることで、結果として質の高い成果を出すことができるようになります。
日々の仕事の中で「無駄な時間を過ごしていないか?」と自分に問いかけながら、時間の使い方を工夫していくことで、より充実した仕事のスタイルを築くことができるでしょう。
2つめ「優先順位をつけて仕事を進める」
仕事ができる人は、すべての業務に対して同じように時間をかけるのではなく、優先順位を明確にしながら仕事を進めています。時間やリソースは限られているため、何を優先すべきかを判断し、効率的に進めることが求められます。優先順位を決めることで、重要な仕事に集中し、成果を出しやすくなります。また、無駄な業務に時間を取られず、効果的に仕事を進めることができるため、余裕を持った働き方につながります。
しかし、仕事の優先順位をつけるのが難しいと感じる人もいるかもしれません。ここでは、仕事ができる人が自然に行っている優先順位のつけ方を解説していきます。
重要度と緊急度を見極める
仕事の優先順位をつける際に、多くの人が迷うのが「どの仕事を先にやるべきか」という点です。仕事には「重要度」と「緊急度」という2つの要素があり、これを適切に判断することで、より効果的に仕事を進めることができます。
たとえば、「すぐに対応しなければならないが、それほど重要ではない業務」と「期限まで余裕があるが、成果に大きな影響を与える業務」があった場合、どちらを優先すべきでしょうか?多くの人は、すぐに対応が必要な業務に手をつけがちですが、長期的に見て重要な仕事を後回しにすると、大きな成果を逃してしまうことがあります。そのため、仕事ができる人は、緊急度が高い仕事だけでなく、重要度の高い仕事にも適切に時間を割くことを意識しています。
優先順位をつける際には、「重要度が高く、緊急度も高い仕事」を最優先し、「重要度は高いが、緊急度が低い仕事」を計画的に進めることがポイントです。一方で、「緊急度は高いが、重要度が低い仕事」はできるだけ効率的に終わらせ、「緊急度も重要度も低い仕事」は可能な限り後回しにすることで、時間を有効に使うことができます。
タスクを整理し、無駄を省く
仕事ができる人は、ただ優先順位を決めるだけでなく、業務全体を整理しながら無駄を省くことも意識しています。やるべき仕事をリスト化し、どの業務が最も重要なのかを明確にすることで、仕事の効率が大きく向上します。
たとえば、一日の始まりにその日のタスクを整理し、「この仕事は本当にやるべきなのか?」と自問することが大切です。仕事を進める中で、無意識のうちに不要な作業に時間を使ってしまっていることもあります。そのため、優先順位を決める前に、まず「やらなくても良い仕事」を見極めることが重要です。
また、仕事の進め方を見直し、効率化できる部分を探すことも効果的です。同じ作業を何度も繰り返していたり、手間のかかる方法で仕事をしていたりすると、貴重な時間を浪費してしまいます。そうした場合は、「もっと簡単にできる方法はないか?」と考えながら、業務フローを見直すことが求められます。
すぐに取りかかれるよう準備を整える
優先順位を決めた後、すぐに仕事に取りかかれるよう準備を整えることも大切です。仕事ができる人は、事前に必要な資料や情報を揃えておくことで、業務のスムーズな進行を実現しています。
たとえば、会議の資料を前もって準備し、すぐに共有できる状態にしておくことで、無駄な時間を省くことができます。また、業務に必要なデータやツールを整理し、すぐに使える状態にしておくことで、作業の効率が上がります。
さらに、タスクごとに「次に何をするべきか」を明確にしておくことも重要です。優先順位を決めても、次のステップが曖昧なままだと、仕事の進行が遅れてしまうことがあります。そのため、仕事を始める前に、どの順番で進めるべきかを明確にし、迷わずに作業に取りかかれるようにしておくと良いでしょう。
仕事ができる人は、限られた時間の中で最大限の成果を出すために、優先順位をしっかりと考えながら仕事を進めています。重要度と緊急度を見極め、無駄な作業を省きながら、最も効率的に進める方法を選択することで、仕事の質を向上させることができます。
また、優先順位を決めた後に、すぐに取りかかれるよう準備を整えることで、時間を無駄にせず、スムーズに仕事を進めることが可能になります。日々の業務の中で、「本当にこの仕事が最優先なのか?」と考えながら行動することで、仕事の成果を高め、より良い働き方を実現することができるでしょう。
3つめ「小さな約束も守る意識を持つ」

仕事ができる人は、どんなに些細な約束でも大切にし、誠実に守る意識を持っています。信頼関係は、日々の積み重ねによって築かれるものです。ちょっとした約束を守ることで、「この人は信頼できる」と周囲から認識され、結果として仕事のしやすい環境が生まれます。一方で、小さな約束を軽視してしまうと、気づかないうちに信頼を失い、仕事の評価にも影響を及ぼすことがあります。
約束を守るというのは、決して難しいことではありません。まずは、「小さなことでも約束は約束」と意識し、それを確実に実行することが大切です。ここでは、仕事ができる人が普段から意識している約束の守り方について解説します。
約束は「できること」だけを引き受ける
仕事をしていると、同僚や上司、取引先からさまざまな依頼を受けることがあります。そのとき、無理にすべてを引き受けてしまうと、結果的に約束を果たせなくなる可能性が高くなります。仕事ができる人は、自分が対応できる範囲をしっかり把握し、「できること」と「できないこと」を適切に判断します。
たとえば、「今日中に仕上げます」と言ったにもかかわらず、実際には間に合わずに翌日になってしまうようなケースは避けるべきです。そのため、仕事を引き受ける際には、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。もし、依頼された仕事が難しいと感じた場合は、単に「できません」と断るのではなく、「〇〇日までなら対応可能です」といった代替案を提示することで、相手に対して誠実な対応ができます。
また、約束したことを忘れないように、メモやスケジュール管理ツールを活用するのも効果的です。特に、忙しいときほど細かい約束を見落としやすくなるため、すぐにメモを取り、確実に実行できるようにしておくと良いでしょう。
相手が期待する以上の行動を意識する
仕事ができる人は、ただ約束を守るだけでなく、「相手が期待する以上の行動をすること」を意識しています。たとえば、資料の提出期限を守るだけでなく、余裕を持って早めに提出したり、必要な情報を補足して提供するなど、相手が「助かる」と感じる行動を取ることで、信頼をさらに高めることができます。
また、約束の内容をただこなすのではなく、「相手が本当に求めていることは何か?」を考えながら対応することも大切です。たとえば、「〇〇のデータをまとめてほしい」と依頼された場合、単にデータを並べるのではなく、「このデータをどのように活用するのか?」を考え、より分かりやすい形でまとめることで、相手の期待を超える成果を提供できます。
こうした心がけがあると、仕事を頼みやすい人として認識され、重要な業務を任される機会も増えていきます。結果的に、キャリアアップにもつながるため、日々の仕事の中で意識していくことが大切です。
万が一、約束を守れないときの対応を考える
どれだけ気をつけていても、予期せぬトラブルや急な予定変更によって、約束を守れなくなることもあります。そのようなとき、仕事ができる人は、誠実な対応を心がけています。
まず、約束を守れないと分かった時点で、できるだけ早く相手に連絡することが大切です。「ギリギリまで頑張れば間に合うかもしれない」と考えているうちに時間が過ぎてしまうと、相手に余計な迷惑をかけてしまいます。例えば、「申し訳ありませんが、当初お約束していた〇〇の提出が、1日遅れそうです」と早めに伝えることで、相手もスケジュールを調整しやすくなります。
また、ただ謝るだけではなく、「〇〇の対応策を考えましたので、ご迷惑を最小限に抑えるよう努めます」といった解決策を提示することで、信頼の低下を防ぐことができます。たとえば、資料の提出が遅れる場合でも、「一部のデータだけ先にお渡しすることは可能です」といった代替案を提示すると、相手の負担を軽減できます。
さらに、同じミスを繰り返さないように、なぜ約束を守れなかったのかを振り返り、今後の対策を考えることも重要です。スケジュール管理を見直したり、事前の準備を徹底することで、次回から同じミスを防ぐことができます。
仕事ができる人は、どんなに小さな約束でも大切にし、それを確実に守ることで信頼を築いています。約束を引き受ける際には、自分が対応できる範囲を見極め、無理のないスケジュールを設定することが重要です。また、約束を守るだけでなく、相手が期待する以上の行動を意識することで、より良い関係を築くことができます。
万が一約束を守れなくなった場合でも、早めに連絡し、適切な対応策を提示することで、相手への影響を最小限に抑えることが可能です。信頼は一朝一夕で築けるものではありませんが、日々の小さな積み重ねが大きな成果につながります。
これからの仕事の中で、「この約束を本当に守れるか?」と自問しながら行動することで、より誠実な働き方ができるようになるでしょう。
4つめ「相手の話をしっかり聞いて対応する」
仕事ができる人は、コミュニケーションの基本として「相手の話をしっかり聞く」ことを大切にしています。これは単に聞いているふりをするのではなく、相手が伝えようとしている内容を正しく理解し、それに対して適切に対応することを意味します。
職場では、上司や同僚、取引先とのやり取りが日常的に発生します。その中で、相手の話をきちんと理解できていないと、誤解や行き違いが生じ、思わぬトラブルにつながることがあります。一方で、しっかり話を聞くことで、的確な対応ができるだけでなく、信頼関係を築くことにもつながります。
ここでは、仕事ができる人が実践している「相手の話をしっかり聞く」ためのポイントを紹介します。
相手の話を最後まで聞く姿勢を持つ
仕事の場では、相手の話を途中で遮ってしまったり、自分の意見を先に伝えようとしてしまうことがあります。しかし、話の途中で口を挟んでしまうと、相手の本当に伝えたいことを理解しきれず、誤った判断をしてしまうことがあります。
仕事ができる人は、相手が話し終わるまでしっかりと聞くことを意識しています。特に、相手が話している最中に自分の考えを巡らせすぎると、内容を十分に理解できなくなることがあります。そのため、まずは相手の話を最後まで聞き、内容をしっかり整理した上で、自分の意見を述べるようにすると、より円滑なコミュニケーションが可能になります。
また、相手が何かを説明しているときに、ただ頷くだけではなく、適度に相槌を打ったり、「なるほど」「それは興味深いですね」といった反応を示すことで、話し手に安心感を与えることができます。こうした姿勢を持つことで、相手はより安心して話ができるようになり、より深い情報を引き出すことができるようになります。
話の要点を整理しながら聞く
相手の話を聞く際には、ただ耳を傾けるだけではなく、「どの部分が重要なのか?」を意識しながら聞くことが大切です。特に、仕事の指示や重要な連絡を受ける際には、要点を整理しながら聞くことで、後で混乱することを防ぐことができます。
たとえば、上司から新しいプロジェクトの指示を受ける際、「何をするのか」「いつまでに完了する必要があるのか」「どのような手順で進めるのか」といったポイントを意識しながら聞くことで、仕事の進行がスムーズになります。こうした情報を整理しながら聞くことで、相手にとっても「この人はしっかり理解している」と安心感を持ってもらうことができます。
また、相手の話を聞きながら、「つまり、こういうことですね?」と確認することで、認識のズレを防ぐことができます。もし話の内容に不明点がある場合は、その場で質問することが重要です。後になって「実はよく分かっていなかった」となると、業務に支障をきたすことがあるため、疑問がある場合は遠慮せずに聞くことが大切です。
聞いた内容を行動に移す
相手の話をしっかり聞くことができても、それを適切に行動に移せなければ意味がありません。仕事ができる人は、聞いた情報をもとに「次に何をするべきか?」を考え、すぐに実行に移します。
たとえば、クライアントから要望を聞いた場合、単に「分かりました」と伝えるだけではなく、具体的な対応策を考え、すぐに動くことが重要です。「〇〇の資料を作成して、明日までに送ります」といったように、聞いた内容に基づいて次のアクションを明確にすることで、相手に安心感を与えることができます。
また、聞いた内容をしっかりメモしておくことも大切です。人間の記憶には限界があり、一度聞いただけではすべてを覚えておくことは難しいため、要点をまとめて記録しておくことで、後で確認しやすくなります。特に、複数の仕事を同時に進める場合には、聞いた内容を整理しておくことで、抜け漏れを防ぐことができます。
仕事ができる人は、相手の話をしっかり聞き、適切に対応することで、円滑なコミュニケーションを実現しています。話の途中で遮らずに最後まで聞き、要点を整理しながら理解することで、正確な判断ができるようになります。また、聞いた内容をすぐに行動に移し、具体的な対応をすることで、信頼関係を築くことができます。
日々の業務の中で、「本当に相手の話をしっかり聞けているか?」と振り返ることはとても重要です。しっかりと聞く姿勢を持ち、聞いた内容を行動に移すことで、よりスムーズに仕事を進めることができるでしょう。
5つめ「報告・連絡・相談を適切に行う」

仕事ができる人は、職場でのコミュニケーションを円滑にするために、「報告・連絡・相談(ホウ・レン・ソウ)」を適切に行っています。これは、業務をスムーズに進めるための基本であり、特にチームで働く場合には欠かせない要素です。情報共有が適切に行われないと、ミスが発生しやすくなり、業務の効率が下がってしまうこともあります。
ホウ・レン・ソウが適切にできる人は、周囲との連携が取りやすくなり、信頼関係を築くことができます。一方で、これを疎かにすると、仕事の進行が滞り、トラブルを引き起こす原因にもなります。ここでは、仕事ができる人が実践しているホウ・レン・ソウのポイントについて解説します。
報告は「簡潔に、分かりやすく」
報告とは、自分が担当している業務の進捗や結果を上司や関係者に伝えることです。仕事ができる人は、ただ報告をするだけでなく、「簡潔で分かりやすく伝える」ことを意識しています。
たとえば、「〇〇の業務は80%完了しており、残りの作業は□□です。完了予定日は△△になります。」というように、端的に現状を伝えることで、相手はすぐに状況を把握できます。逆に、「まだ終わっていません」といった曖昧な報告では、受け取る側が判断に困ってしまいます。
また、問題が発生した場合には、「何が原因で、どのような対応をしているのか」をセットで伝えることが大切です。「〇〇の工程で問題が発生しましたが、現在□□の方法で対応中です。解決の見込みは△△日です。」という形で報告すると、上司や関係者は適切な対応を取りやすくなります。
さらに、報告の頻度も重要です。仕事ができる人は、問題が起きてから報告するのではなく、定期的に状況を共有することで、リスクを未然に防ぐことを意識しています。特に、上司が多くの業務を抱えている場合は、簡潔な報告をこまめに行うことで、スムーズな意思決定をサポートすることができます。
連絡は「相手の状況を考慮する」
連絡は、業務の進行に関する情報を関係者に伝えることを指します。仕事ができる人は、ただ情報を伝えるだけでなく、「相手の状況を考えながら連絡する」ことを意識しています。
たとえば、メールやチャットでの連絡の場合、相手が忙しい時間帯に長文を送ると、すぐに確認してもらえないことがあります。そのため、要点を整理し、「何を伝えたいのか」を明確にすることで、相手が素早く対応しやすくなります。
また、口頭で連絡をする際も、相手が何かに集中しているときに話しかけるのではなく、タイミングを見極めることが大切です。急ぎでない場合は、「お時間のあるときに少しお話しできますか?」と一言添えることで、相手の負担を減らしつつ、スムーズにコミュニケーションを取ることができます。
さらに、連絡をする際には、「事実のみを伝える」のではなく、「相手がどう行動すればよいのか」も示すことが重要です。例えば、「〇〇の件ですが、締切が変更になりました」とだけ伝えるのではなく、「〇〇の締切が△△に変更されたため、□□の作業を前倒しで進める必要があります」と伝えることで、相手が適切に動きやすくなります。
相談は「早めに行うことが大切」
相談は、自分だけでは判断が難しい問題について、上司や同僚に意見を求めることです。仕事ができる人は、「問題が大きくなる前に、早めに相談する」ことを意識しています。
特に、新しい業務や難しいタスクに取り組むとき、すべてを自分で解決しようとすると、余計な時間がかかってしまうことがあります。こうした場合、早めに相談することで、効率的に問題を解決できるだけでなく、ミスを防ぐことにもつながります。
また、相談をする際には、「何が問題なのか」「自分が考えた対応策は何か」を整理して伝えることが大切です。例えば、「この業務の進め方について、〇〇の方法と□□の方法が考えられますが、どちらが適切でしょうか?」と具体的に相談すると、相手もアドバイスをしやすくなります。
相談をすることは決して「できない人」という印象を与えるものではありません。むしろ、適切に相談ができる人は、「状況を把握し、問題解決のために最善の方法を探している人」として評価されることが多いのです。
仕事ができる人は、ホウ・レン・ソウを適切に行うことで、業務を円滑に進めています。報告では、簡潔かつ分かりやすく状況を伝え、連絡では、相手の状況を考慮しながら必要な情報を伝えます。そして、相談は早めに行い、問題が大きくなる前に解決策を見つけることを意識しています。
これらを実践することで、職場でのコミュニケーションがスムーズになり、信頼関係を築くことができます。日々の仕事の中で、「今、この情報を誰に、どのように伝えるべきか?」と考えながら行動することで、より効果的に仕事を進めることができるでしょう。
6つめ「スケジュール管理を徹底している」
仕事ができる人は、スケジュール管理をしっかりと行い、効率的に業務を進めています。計画的に仕事を進めることで、無駄な時間を減らし、突発的なトラブルにも柔軟に対応できるようになります。一方で、スケジュール管理が甘いと、納期に追われたり、仕事の優先順位を見失ったりしてしまい、結果的にパフォーマンスの低下につながることもあります。
適切なスケジュール管理を行うことで、仕事の効率が上がるだけでなく、ストレスも軽減され、余裕を持って業務に取り組むことができます。ここでは、仕事ができる人が実践しているスケジュール管理のポイントについて解説します。
タスクを明確にし、優先順位をつける
スケジュール管理をする上で重要なのは、「何をいつまでにやるのか」を明確にすることです。漠然と仕事を進めるのではなく、具体的なタスクを洗い出し、それぞれの優先順位を決めることで、スムーズに業務を進めることができます。
たとえば、一日の業務の始めに「今日やるべきこと」をリストアップし、それぞれの優先順位をつけると、効率的に仕事を進めることができます。このとき、単に「やるべきこと」を並べるのではなく、「どの順番で進めるのが最も効果的か」を考えることが大切です。
また、仕事の種類によっては、朝のうちに集中して取り組んだ方がよいものもあります。例えば、頭を使う作業や重要な決定を伴う仕事は、午前中の集中力が高い時間帯に進めると効率が上がります。一方で、メールの返信や簡単な作業は、昼過ぎの少し疲れが出る時間帯に回すことで、全体のパフォーマンスを最適化できます。
スケジュールを「見える化」する
仕事ができる人は、スケジュールを頭の中だけで管理するのではなく、「見える化」することを大切にしています。スケジュールが視覚的に整理されていると、何を優先すべきかが一目でわかり、仕事の計画を立てやすくなります。
カレンダーアプリやタスク管理ツールを活用すると、締切や予定をすぐに確認でき、忘れることを防げます。たとえば、Googleカレンダーやタスク管理アプリを使うと、仕事のスケジュールを一元管理しやすくなります。また、プロジェクトごとに進捗を管理する場合には、TrelloやNotionなどのツールを活用することで、チーム内の情報共有もスムーズになります。
また、紙の手帳やノートにスケジュールを書き込むことで、より具体的な計画を立てることもできます。デジタルツールと手書きのメモを組み合わせることで、自分にとって最も使いやすい方法を見つけると良いでしょう。
予備の時間を確保して余裕を持たせる
仕事をしていると、予定通りに進まないことも少なくありません。急な依頼やトラブルが発生することもあるため、スケジュールを組む際には、必ず余裕を持たせることが大切です。
仕事ができる人は、「予定を詰めすぎない」ことを意識しています。たとえば、1時間の作業時間を見積もっている場合でも、あえて1時間半の枠を確保することで、予想外の事態にも対応できるようにしています。
また、スケジュールの中に「バッファ時間」を設けることで、急な対応が必要になったときでも慌てずに対処できます。特に、複数の仕事を同時に進めている場合は、ある程度の柔軟性を持たせることで、スケジュールが崩れるリスクを減らすことができます。
仕事ができる人は、スケジュール管理を徹底することで、効率的に業務を進めています。タスクを明確にし、優先順位をつけることで、仕事の流れをスムーズにし、計画的に業務を進めることができます。また、スケジュールを「見える化」することで、管理がしやすくなり、忘れやミスを防ぐことができます。
さらに、予備の時間を確保することで、突発的なトラブルにも余裕を持って対応できるようになります。無理なく仕事を進めるためには、計画をしっかり立てることが重要です。日々の業務の中で、自分に合ったスケジュール管理の方法を見つけ、効率的な働き方を目指していきましょう。
7つめ「ミスをすぐに修正し、次に活かす」

仕事ができる人は、ミスを完全にゼロにすることは難しいと理解しつつも、ミスを最小限に抑え、発生した場合にはすぐに対応し、その経験を次に活かすことを意識しています。誰でも仕事をしていれば、うっかりミスや判断ミスをすることがあります。しかし、ミスを放置してしまうと、後々大きな問題につながることもあります。
仕事ができる人は、ミスが発生した際に「どう対応するか」「どうすれば同じミスを繰り返さないか」を考え、行動に移します。適切に対処することで、信頼を失うどころか、むしろ「問題が起きても冷静に対応できる人」と評価されることもあります。ここでは、仕事ができる人が実践しているミスの対処法を紹介します。
ミスに気づいたらすぐに報告し、修正する
ミスをしてしまったときに重要なのは、できるだけ早く気づき、適切に対応することです。仕事ができる人は、「自分のミスを隠そう」と考えるのではなく、まずは状況を正直に報告し、修正のための行動を取ります。
たとえば、クライアントに送る資料の誤字や計算ミスに気づいた場合、すぐに上司や関係者に報告し、修正した資料を速やかに送ることで、大きな問題を防ぐことができます。「このくらいなら大丈夫だろう」と放置してしまうと、後になって問題が大きくなり、取り返しがつかなくなることもあります。
また、ミスを報告する際には、単に「ミスをしました」と伝えるのではなく、「〇〇の部分に誤りがありました。現在△△の方法で修正を進めており、□□までに対応を完了します」といった形で、具体的な対応策と見通しを伝えることが大切です。これにより、周囲もスムーズに対応しやすくなります。
ミスの原因を振り返り、再発防止策を考える
ミスが起きた後、同じことを繰り返さないためには、原因を分析し、適切な対策を取ることが重要です。仕事ができる人は、ただ「気をつけよう」と思うだけで終わらせず、具体的な行動を見直します。
たとえば、スケジュール管理ミスで納期に遅れてしまった場合、「なぜ遅れたのか?」を振り返ります。「作業に必要な情報が揃っていなかった」「タスクの見積もりが甘かった」などの原因を明確にすることで、次回は「事前に情報を確認する」「スケジュールを余裕を持って組む」といった具体的な対策を取ることができます。
また、ミスを防ぐために「チェックリストを作成する」「ダブルチェックを行う」「作業の流れを見直す」といった工夫をすることで、再発を防ぐことができます。特に、頻繁に同じようなミスをしてしまう場合は、作業プロセスを見直し、仕組みとして改善することが有効です。
ミスを恐れず、成長の機会と捉える
仕事ができる人は、ミスを完全に避けようとするのではなく、「ミスから学ぶ」ことを大切にしています。どれだけ慎重に仕事をしていても、人間である以上、ミスを完全になくすことはできません。大切なのは、ミスをした後にどう対応し、それを次に活かすかということです。
たとえば、新しい業務に挑戦する際には、どうしても経験不足からミスをしやすくなります。しかし、その経験を通じて新しい知識を得たり、より効率的なやり方を見つけたりすることができます。仕事ができる人は、ミスを単なる失敗と捉えず、「次にどうすれば改善できるか?」を考えながら行動します。
また、ミスをした際に必要以上に自分を責めてしまうと、萎縮してしまい、積極的な行動が取りにくくなることもあります。ミスをしたら、「この経験をどう活かせるか?」と前向きに考え、成長のチャンスに変えることが重要です。
仕事ができる人は、ミスをしたときに「どう対応するか」「どうすれば同じミスを繰り返さないか」を考え、適切に行動に移します。ミスに気づいたらすぐに報告し、迅速に修正することで、トラブルを最小限に抑えることができます。また、ミスの原因を振り返り、具体的な再発防止策を取ることで、成長の機会につなげることができます。
ミスを恐れず、「ミスは学びのチャンス」と捉えることで、より良い働き方ができるようになります。大切なのは、ミスを放置せず、誠実に対応し、その経験を活かして改善を重ねることです。日々の仕事の中で、「次に同じことをしないために何ができるか?」を意識しながら行動することで、より信頼される存在になることができるでしょう。
8つめ「周囲と協力しながら円滑に進める」
仕事ができる人は、単独で成果を出すのではなく、周囲と協力しながら円滑に業務を進めることを意識しています。仕事は個人の能力だけで完結するものではなく、多くの場合、チームや関係者との連携が不可欠です。協力し合うことで、より良い結果を生み出し、円滑な職場環境をつくることができます。
また、一人で抱え込むと作業が滞りやすくなり、ミスやストレスの原因にもなります。周囲と適切に連携しながら仕事を進めることで、スムーズに業務を遂行し、効率的に成果を上げることができます。ここでは、仕事ができる人が実践している「周囲と協力しながら仕事を進める方法」について解説します。
チーム全体の目標を意識する
仕事をする上で、自分の業務に集中することは大切ですが、それだけでは十分ではありません。仕事ができる人は、自分の役割を果たしながら、チーム全体の目標を意識して行動します。
たとえば、自分が担当している業務が完了したら、それで終わりではなく、「チーム全体の進捗はどうか?」「ほかにサポートできることはあるか?」と考えることで、より円滑に業務を進めることができます。
また、チームでの仕事では、自分の作業が他のメンバーの業務とどのように関わっているかを理解することが重要です。たとえば、自分の報告が遅れることで、他のメンバーの業務に影響を与えてしまうこともあります。スムーズに連携するためには、「この作業が終わったら、次に誰が何をするのか?」を意識しながら進めることが大切です。
積極的にコミュニケーションを取る
仕事ができる人は、積極的にコミュニケーションを取り、円滑に業務を進めることを心がけています。特に、チームでの仕事では、情報の共有がスムーズに行われているかが重要になります。
たとえば、「〇〇の案件ですが、現在△△の段階にあります」といった報告を定期的に行うことで、チームのメンバーが状況を把握しやすくなります。また、「この部分について意見をもらいたい」と相談することで、新たな視点を得ることができ、より良い結果につながることもあります。
コミュニケーションを取る際には、「相手が話しやすい雰囲気をつくる」ことも重要です。仕事ができる人は、相手の意見を尊重し、積極的に話を聞く姿勢を持っています。これにより、メンバー同士の信頼関係が強まり、チーム全体の雰囲気が良くなります。
困ったときは素直に助けを求める
仕事をしていると、どうしても自分一人では解決できない問題に直面することがあります。そんなとき、仕事ができる人は、素直に周囲に助けを求めることができます。
「こんなことで相談していいのだろうか?」とためらってしまう人もいますが、適切なタイミングで助けを求めることは、決して悪いことではありません。むしろ、問題を抱え込んでしまい、後になって大きなトラブルにつながる方がリスクが大きくなります。
また、助けを求める際には、「ただお願いする」のではなく、「自分で考えた解決策も提示する」ことがポイントです。たとえば、「この部分で悩んでいるのですが、〇〇の方法と△△の方法のどちらが良いでしょうか?」と具体的に相談すると、相手もアドバイスしやすくなります。
仕事ができる人は、周囲と協力しながら業務を進めることで、より良い成果を生み出しています。チーム全体の目標を意識しながら行動し、積極的にコミュニケーションを取ることで、スムーズに仕事を進めることができます。
また、困ったときには素直に助けを求めることで、問題を早期に解決し、より効果的に仕事を進めることができます。仕事は一人で完結するものではありません。周囲と適切に連携しながら働くことで、より充実した職場環境を作ることができるでしょう。
9つめ「常に学ぶ姿勢を持ち、成長を続ける」

仕事ができる人は、現状に満足することなく、常に新しい知識やスキルを学びながら成長を続けています。どんな業界や職種でも、時代の変化とともに求められるスキルや知識は変化していきます。そのため、仕事の成果を維持し続けるためには、学び続ける姿勢が必要になります。
一方で、日々の業務に追われてしまい、「新しいことを学ぶ余裕がない」と感じる人も多いかもしれません。しかし、仕事ができる人は、忙しい中でも効率よく学ぶ方法を取り入れ、成長の機会を逃さないようにしています。ここでは、仕事ができる人が実践している学びの習慣について解説します。
日常の業務から学びを得る意識を持つ
仕事の中には、新しい知識やスキルを学ぶ機会が数多くあります。しかし、その機会を意識していないと、せっかくの学びのチャンスを見逃してしまうこともあります。仕事ができる人は、日々の業務の中で「どんな学びがあるか?」を常に意識しながら取り組んでいます。
たとえば、新しい業務に挑戦するとき、「この仕事を通じてどんなスキルが身につくのか?」と考えながら取り組むことで、成長の機会を最大限に活かすことができます。また、ミスをしてしまったときも、「なぜこのミスが起こったのか?」「次に同じことをしないためにはどうすればよいか?」と振り返ることで、次の仕事に活かすことができます。
また、周囲の人から学ぶことも大切です。仕事ができる人は、自分だけのやり方にこだわらず、他の人の仕事の進め方を観察したり、アドバイスをもらったりすることで、新しい知識やスキルを身につけています。
学ぶための時間を確保する工夫をする
忙しい中でも学びを継続するためには、学ぶための時間を意識的に確保することが重要です。仕事ができる人は、日々のスケジュールの中に「学びの時間」を組み込み、計画的に学習を進めています。
たとえば、通勤時間を活用してビジネス書を読んだり、ポッドキャストを聞いたりすることで、効率的に学ぶことができます。また、仕事が終わった後の30分を活用して、オンライン講座を受講したり、新しいスキルを学ぶ時間に充てることも効果的です。
また、短時間でも継続することが大切です。1回に長時間学ぶのではなく、毎日少しずつ学ぶことで、無理なく習慣化することができます。たとえば、「1日15分だけでも業界ニュースを読む」「週に1回、新しいスキルについて学ぶ時間を作る」といった小さな目標を立てることで、学びを継続しやすくなります。
新しい挑戦を恐れず、経験を積む
仕事ができる人は、新しい挑戦を恐れず、積極的に経験を積むことを大切にしています。新しいことに取り組むことは、不安やプレッシャーを感じることもありますが、成長のためには欠かせません。
たとえば、新しいプロジェクトに参加する機会があれば、「自分にはまだ早いかもしれない」と思わずに、積極的に手を挙げることで、新しいスキルや知識を学ぶことができます。また、社内外の研修やセミナーに参加することで、専門的な知識を深めることもできます。
また、新しいことに挑戦すると、失敗することもあります。しかし、仕事ができる人は、失敗を恐れず、「この経験から何を学べるか?」を考えることで、次につなげる意識を持っています。
仕事ができる人は、常に学ぶ姿勢を持ち、成長を続けることを大切にしています。日常の業務の中で学びを得る意識を持ち、効率よく学ぶ方法を取り入れることで、忙しい中でも成長の機会を逃さないようにしています。また、新しいことに挑戦し、経験を積むことで、仕事の幅を広げ、より高い成果を上げることができます。
仕事は、ただこなすだけではなく、成長の機会として捉えることが大切です。日々の業務の中で、「この経験から何を学べるか?」を意識しながら取り組むことで、仕事のスキルだけでなく、キャリア全体を通じて成長することができます。学ぶ姿勢を持ち続けることで、仕事の充実感や達成感も高まり、より充実した働き方ができるようになるでしょう。
10こめ「仕事に責任を持ち、最後までやり遂げる」
仕事ができる人は、一度引き受けた仕事に対して責任を持ち、最後までやり遂げる姿勢を大切にしています。どんなに小さな仕事でも、中途半端に終わらせるのではなく、最後までしっかりとやり遂げることで、信頼を積み重ねることができます。
また、仕事をやり遂げることは、単に「最後まで終わらせる」という意味ではありません。質の高い成果を出し、周囲に安心感を与えることも含まれます。途中で困難な状況に直面しても、「どうすれば解決できるか?」を考えながら前向きに取り組むことで、仕事の成果を高めることができます。ここでは、仕事ができる人が実践している「仕事を最後までやり遂げるためのポイント」について解説します。
責任を持つとは「最後まで考えること」
仕事を引き受けることは、単に作業をこなすことではなく、「最後まで責任を持って対応すること」が求められます。仕事ができる人は、与えられたタスクを単にこなすだけでなく、その結果がどのような影響を与えるのかを考えながら進めています。
たとえば、「資料を作成する」という業務があった場合、単にデータをまとめるだけではなく、「この資料を受け取る人は何を求めているのか?」「より分かりやすい構成にするにはどうすればよいか?」といったことを考えながら作業を進めることで、より良い成果を出すことができます。
また、仕事が終わった後も、「本当にこれで問題ないか?」を確認する習慣を持つことで、ミスを防ぐことができます。最後まで責任を持って業務に取り組むことで、より高い評価を得ることができ、次の仕事にも良い影響を与えることができます。
途中で問題が発生しても諦めない
仕事を進めていると、思い通りにいかないことや、予期しない問題に直面することもあります。しかし、仕事ができる人は、そうした状況でも諦めず、解決策を模索しながら最後まで取り組む姿勢を持っています。
たとえば、納期が迫っている中でトラブルが発生した場合、「もう間に合わない」と諦めるのではなく、「どうすれば間に合わせることができるか?」を考え、優先順位を見直したり、周囲に協力を求めたりすることで、最善の結果を出せるように努力します。
また、問題が発生した際には、「誰かが何とかしてくれるだろう」と考えるのではなく、「自分ができることは何か?」を考えて行動することが大切です。問題を解決するために必要な情報を集めたり、他の人と相談しながら進めることで、状況を改善することができます。
細かい部分まで手を抜かず、質を高める
仕事を最後までやり遂げるためには、「これくらいでいいだろう」と妥協せず、細かい部分までしっかりと取り組むことが重要です。特に、仕事の質は細かい部分の積み重ねによって決まるため、細部にまで気を配ることで、より高い評価を得ることができます。
たとえば、メールを送る際に、誤字脱字がないか確認するだけでも、相手に与える印象が変わります。また、プレゼン資料を作成するときに、見やすさやデザインにも気を配ることで、より分かりやすい資料になります。こうした細かい部分に注意を払うことで、仕事の完成度を高めることができます。
また、「誰かがチェックするから大丈夫」と考えずに、自分の責任として細部まで確認することが大切です。最後の確認をしっかり行うことで、ミスを防ぎ、より良い成果を出すことができます。
仕事ができる人は、一度引き受けた仕事に責任を持ち、最後までやり遂げることを大切にしています。ただ終わらせるのではなく、細かい部分まで手を抜かず、高いクオリティを意識することで、より良い成果を出すことができます。
また、途中で問題が発生しても諦めず、解決策を考えながら最後まで取り組むことで、より良い結果を生み出すことができます。仕事を進める中で、「この仕事を最後までしっかりとやり遂げるにはどうすればよいか?」を常に意識することで、より信頼される存在になることができるでしょう。
まとめ
仕事ができる人は、特別な才能やスキルを持っているわけではなく、日々の仕事の中で「当たり前」と思われることを自然に実践しています。時間を無駄にせず、優先順位をつけて効率的に進め、約束を守り、相手の話をしっかり聞く姿勢を持つことで、円滑に業務を進めています。
また、報告・連絡・相談を適切に行い、スケジュール管理を徹底することで、仕事の質を高めています。ミスをした場合には迅速に対応し、その経験を次に活かすことで、成長し続けることができます。さらに、周囲と協力しながら仕事を進め、学ぶ姿勢を持ち続けることで、常に自己成長を意識しています。そして何よりも、仕事に責任を持ち、最後までやり遂げることで、信頼を積み重ね、より良い成果を生み出しています。
これらの行動は、特別な才能がなくても、誰でも意識することで身につけることができます。日々の業務の中で、「自分の仕事の進め方はどうか?」「より良い働き方をするために何ができるか?」を考えながら取り組むことで、仕事の質を向上させることができるでしょう。
「仕事ができる人」と言われるために、何か特別なことをする必要はありません。日々の積み重ねが、信頼や成果につながっていきます。この記事を通じて、自分の働き方を見直し、より良い仕事の進め方を実践するきっかけになれば幸いです。