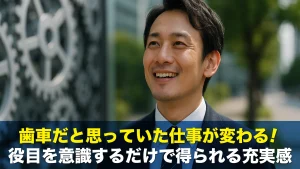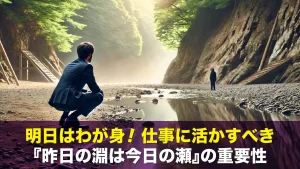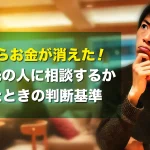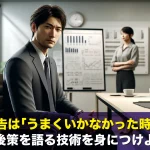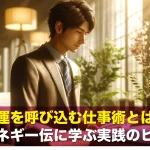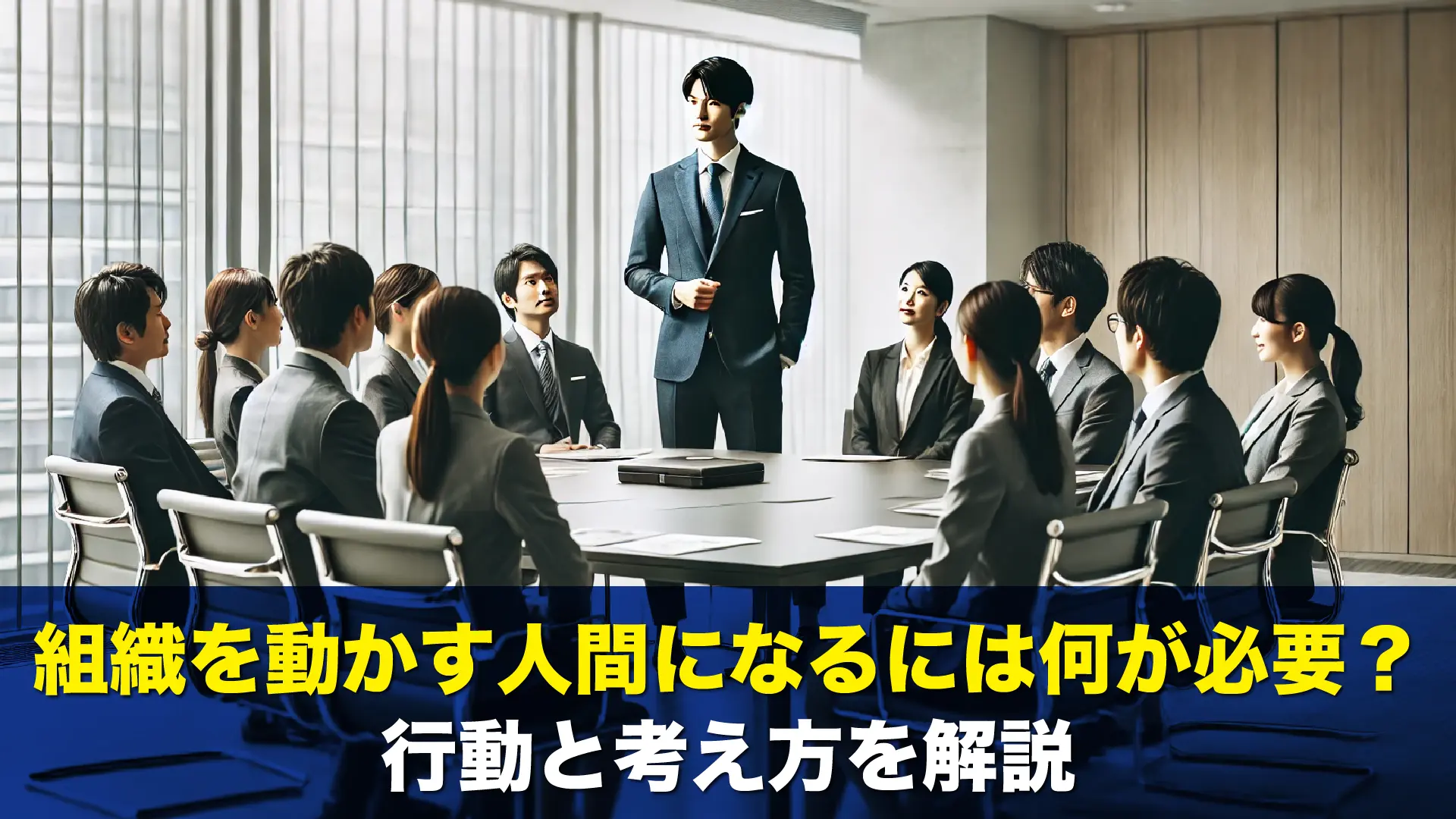
組織の中で、自然とまわりを動かしていく人がいます。大きな声で指示を出すわけでもなく、特別な役職についているわけでもないのに、その人がいると、空気が変わる。人の動きがやわらかくなり、会話が生まれ、少しずつ前に進んでいく、そんな姿にあなたも心を動かされた経験があるかもしれません。
では、そうした「組織を動かす人間」とは、どんな存在なのでしょうか。ただ成果を出す人ではなく、周囲との関係を大切にし、自らの言葉や行動でまわりの気持ちに静かに触れていく。そうした人は、自分のことを深く理解し、相手の声なき声に耳を傾け、立場を超えて人と人のあいだに橋をかけていきます。
このコラムでは、「組織を動かす人間になる」というテーマのもと、自分自身を見つめ直し、やさしく前に進んでいくための考え方やヒントを10の視点から丁寧にご紹介していきます。変化は、いつも自分の中から始まります。小さな気づきと行動が、まわりの人に、そして組織に、静かなうねりをもたらしていく。そんな可能性を信じながら、これから一緒に考えていきましょう。
この記事の目次(タップでジャンプ)
組織の中で動かす役割とはどのような存在か

組織の中で「動かす人」として見られる存在は、ただ業務を進めるだけの人とは異なります。そのような存在は、まわりの人々を自然と引きつけたり、信頼を集めたりすることができる人でもあります。しかし、ここで勘違いしてはいけないのは、「動かす」とは命令や指示を出すことではないということです。組織の中で動かす存在とは、自らが動き、率先して行動することで、周囲の人の行動や意識を変えていく力を持った人なのです。
また、その人自身が持つ人間味や誠実さ、そして思いやりが、人の心に届き、結果的に組織全体が動くきっかけになっていくのです。どんなに知識や経験があっても、それだけでは組織を動かすことはできません。人は、人の言葉や態度、行動に影響を受ける生き物です。だからこそ、自分の姿勢を見せることで、誰かに気づきを与えたり、勇気を与えたりできる人が、組織の中で「動かす人」として機能していきます。
それでは、そのような存在とはどのような特徴や考え方を持っているのでしょうか。ここからはさらに詳しく掘り下げていきましょう。
単なる指示待ちでは動かせない理由
組織の中では「言われたことだけをやる」人と、「自分から動く」人の違いがはっきりと現れます。指示待ちの状態では、状況の変化に柔軟に対応できなかったり、まわりの動きに乗り遅れたりすることが多くなります。さらに、周囲の信頼を得ることも難しくなってしまいます。
動かす人になるためには、自分の意志で考え、動く姿勢が求められます。たとえば、何か問題が起きたときに、誰かの指示を待つのではなく、自分の頭で「今、何が必要か」「どうしたら少しでも前に進めるか」を考えて行動に移すことができる人は、それだけでまわりから一目置かれるようになります。そうした行動の積み重ねが、組織を少しずつ変えていく原動力になっていくのです。
組織の中で信頼される存在とは
「動かす存在」とは、組織の中で信頼される人でもあります。信頼というのは、一朝一夕に築けるものではなく、日々の態度や言動、行動を通じてゆっくりと積み重なっていくものです。そして、信頼が生まれることで、まわりの人はその人の意見に耳を傾け、自然とついていくようになります。
そのためには、感情的にならずに冷静な判断を心がけたり、自分の失敗を素直に認めたり、他人の意見を尊重する姿勢がとても大切になります。完璧である必要はありませんが、誠実さや謙虚さを持ち続けることで、少しずつ周囲との関係が築かれ、その結果として「この人が言うならやってみよう」と思ってもらえるようになるのです。
動かす側になる意識と視点の違い
指示されたことをやるという立場と、組織を動かしていく立場とでは、ものの見方や考え方に明らかな違いがあります。動かす人は、自分の役割だけを見るのではなく、常に全体を見ながら、「このプロジェクトは今どうなっているか」「チームの雰囲気はどうか」「このメンバーは本当に困っていないか」など、広い視野で物事を見つめています。
また、自分の利益だけでなく、組織やチーム全体の成果を考え、どうすればその方向に向かって力を発揮できるかを考える習慣が身についています。そうした視点の違いが、行動にも表れます。「この作業は意味があるのか」「別の方法の方が効果的なのではないか」といった問いを持ち、常に改善や工夫を忘れない人は、自然と動かす側の存在へと育っていきます。
そういった人の姿に触れたまわりの人々が、「私もやってみよう」と思い始めたとき、組織全体が静かに、しかし確実に動き始めていきます。小さな気づき、小さな行動が、組織にとって大きなうねりとなっていくのです。
組織で信頼されるための基本姿勢
組織の中で誰かを動かすような存在になるためには、まず「信頼されること」がとても大切です。信頼というものは、いわば見えない橋のようなもので、それがしっかりと築かれていないと、どれだけ立派な意見を述べても、その声は届きにくくなってしまいます。信頼されている人の言葉は、たとえ声が小さくても、なぜか届く。そして心に残る。そんな不思議な力を持っています。
では、その信頼はどうすれば生まれるのでしょうか。それは、決して特別なスキルや才能が必要ということではなく、日々の小さな行動や人との接し方から少しずつ築かれていくものです。人は言葉だけではなく、態度や行動からその人の本質を感じ取っています。誠実に、丁寧に、まわりの人に接しようとするその姿勢が、信頼の種をまくことにつながっていくのです。
信頼される存在になるということは、無理に目立とうとすることでもなければ、いつも完璧でいなければならないという意味でもありません。むしろ、自分らしく、嘘のない態度で日々を過ごすことが、まわりにとって安心感を与え、その結果として自然に信頼が育まれていきます。ここでは、そんな信頼を築くために意識しておきたい姿勢について、さらに丁寧に見ていきましょう。
誠実な対応が信頼を築く理由
誠実さとは、言葉にすればとても簡単なように見えますが、実際にはその人の人柄や価値観が表れる部分でもあります。約束を守る、嘘をつかない、失敗をごまかさない、そうした一つひとつの行動が積み重なって、「あの人なら大丈夫」と思ってもらえるようになるのです。
特に組織の中では、個人だけではなくチームや部署の信頼関係が業務の進行に大きく関わってきます。たとえば、仕事の進捗を正直に伝えることや、自分ができる範囲とできないことをきちんと区別して話すことなど、当たり前のようでいて、意外と難しいことも多いものです。ですが、こうした誠実な態度は、まわりから「一緒に仕事がしやすい」「安心して任せられる」と思ってもらえるきっかけになります。
また、誠実であろうとする姿勢は、相手に対して「自分を大切に思ってくれている」と感じさせる効果もあります。だからこそ、完璧を目指すのではなく、自分のできる範囲で丁寧に関わろうとするその気持ちが、信頼の芽を育てていくのです。
約束を守ることがもたらす影響
小さな約束であっても、それを守るという行動はとても大きな意味を持ちます。たとえば、「明日までに資料を用意しておくね」という一言。それを本当に守るかどうかで、まわりの人の印象は大きく変わってきます。約束を守る人は、「信用できる人」としての評価を得やすくなり、次の仕事や相談ごとが自然と集まってくるようになります。
一方で、繰り返し約束を破ってしまうと、「あの人に頼んでもどうせ…」という印象がついてしまい、それが少しずつ信頼を遠ざけることにもつながります。もちろん、状況によっては約束を守れないこともあります。そのときに大切なのは、できなかったことを素直に伝え、次にどうするかをきちんと説明することです。その対応一つで、信頼を失うのではなく、逆に「誠実な人だな」と思ってもらえることもあるのです。
小さなことを大切にする人は、大きなことを任されるようになります。だからこそ、約束を軽く扱わず、一つひとつを丁寧に扱うことが、信頼という土台を少しずつ強くしていくのです。
日々の小さな行動が積み上げる評価
信頼は、ドラマチックな出来事や派手な活躍だけで築かれるものではありません。むしろ、毎日のちょっとした行動が、まわりの人たちの心にしっかりと積み重なっていくものです。たとえば、毎朝笑顔で挨拶する、会議で誰かの意見に耳を傾ける、困っている人にさりげなく声をかける、そうした一つひとつの行動が、見えないかたちで信頼の貯金を増やしていくのです。
人は誰でも、「この人と一緒にいると心地いい」と感じる相手に対して、自然と心を開いていくものです。そして、その安心感が「信頼」という言葉に結びついていきます。もちろん、すべての人と完璧な関係を築く必要はありませんが、自分ができる範囲でまわりと丁寧に関わっていくことが、結果的に組織の中での自分の立ち位置を安定させ、動かす力にもつながっていくのです。
だからこそ、特別なことをしようと気負うのではなく、今この瞬間にできる小さな行動に心を込めてみること。その積み重ねが、気づいたときには「信頼される人」への道をしっかりとつくってくれているはずです。
自ら動いて組織に変化をもたらす力

組織の中で新しい風を起こすような人というのは、ただアイデアを出すだけの人ではなく、実際に行動へと移していく力を持った人です。そしてその行動は、誰かに求められたものではなく、自らが「これが必要だ」と感じたことに対して動き出すという点が、大きな違いになります。もちろん最初は小さなことかもしれません。でも、その一歩が確かに周囲に変化をもたらし、やがては組織全体の雰囲気や動きを変えていくような、そんな力を持っています。
多くの人は、「自分ひとりが動いたところで何も変わらない」と感じてしまいがちです。しかし、実際には一人の行動が誰かの心を動かし、そこから少しずつ共感の輪が広がっていくということは、組織の中でもよく起こります。だからこそ、誰かに頼まれる前に動ける人、そして自分の意志を大切にできる人が、静かに組織を変えていく存在になっていくのです。
ここでは、自ら動くことの意味や、そこに込められた力について、具体的に考えていきましょう。
現状に疑問を持つことから始まる行動
まず最初の一歩として大切なのが、「当たり前」をそのまま受け入れずに、少し立ち止まって考えてみる姿勢です。たとえば、「どうしてこの手順でやっているのか」「もっと効率的なやり方はないのか」といった問いを、自分の中に持つことが、自ら動くためのきっかけになります。
疑問を持つことは、決して否定的な態度ではありません。むしろ、組織に対して関心を持ち、よくしたいという思いがあるからこそ生まれるものです。そして、その小さな違和感や「もう少しこうだったらいいのに」という気持ちを見逃さずに、大切にすることが、変化の種になっていきます。
たとえ今すぐには改善できないとしても、そうした視点を持つことで日々の行動が変わり、まわりの人たちも「なんだか最近、空気が変わったな」と感じ始めることがあります。現状に対して疑問を持つことは、自ら動く意志を育てるとても大切な出発点なのです。
周囲の空気を読んだ上で踏み出す一歩
自ら動くということは、ただ思いつきで行動するということではありません。組織の中では、空気を読むこと、つまり状況やまわりの人の感情、タイミングなどを丁寧に感じ取る力も求められます。その上で、自分にできることを見つけて、慎重に、でも確かに一歩を踏み出していくことが、信頼を失わずに変化を起こすための大切な視点となります。
たとえば、忙しいチームの中で「ちょっと手伝いましょうか?」と声をかけるタイミングだったり、会議の中であえて今までと違う提案をする勇気だったり、そうした一つひとつの行動が、静かに空気を変えていく力になります。
周囲を気遣う心と、自分の中にある意志のバランスをとりながら行動できる人は、まわりからの信頼も厚くなり、自然と動かす立場へと成長していきます。誰かが言ってくれるのを待つのではなく、空気を読みながらも自分の判断で動けるというのは、実はとても高度な力なのです。
継続的な改善が信頼に変わる流れ
一度だけ何かを変えるのではなく、日々の中で少しずつ改善を重ねていく姿勢も、自ら動く人に共通する特徴です。たとえば、毎日の業務の中で「今日は昨日より少し効率よくできた」「この部分を工夫したら、チームの負担が減った」といったことを繰り返していくうちに、まわりからの信頼や評価も変わってきます。
継続的に改善を意識するというのは、自分自身に対しても、組織に対しても、誠実でいようとする態度の表れでもあります。そして、それが見ている人の心にじわじわと伝わっていきます。最初は気づかれなくても、やがて「あの人はいつも前向きに工夫してくれている」と感じてもらえるようになり、それが信頼へとつながっていくのです。
また、改善を続けるためには、完璧を目指しすぎないことも大切です。うまくいかないことがあっても、「じゃあ次はどうしよう」と前を向くことができれば、それもまた自分の成長につながります。動き続けること、変化を恐れずに向き合うことが、やがて大きな変化を生み出す力になるのです。
組織を動かすために求められる思考の柔軟性
組織の中で、さまざまな人と協力しながら物事を前に進めていくには、思考の柔軟さが欠かせません。特に「動かす立場」になりたいと考える人にとっては、自分の考えに固執せず、多角的に物事をとらえたり、まわりの意見に耳を傾けたりする姿勢がとても大切です。柔軟性のある考え方ができる人は、組織に新しい視点をもたらすことができ、環境や状況の変化にも対応しやすくなります。
一方で、柔軟性を持つというのは、ただ「どんなことも受け入れる」ということとは違います。むやみに意見を変えるのではなく、自分の中にしっかりとした軸を持ちながらも、その場に応じて視点を変えたり、考え直したりできるバランスが求められるのです。その姿勢は、組織内での信頼にもつながり、「あの人なら状況をきちんと理解してくれる」と思ってもらえるようになります。
ここからは、組織を動かす存在になるために必要な、柔軟な思考とはどのようなものかを、具体的に掘り下げて考えてみましょう。
一つの答えに固執しない視点の持ち方
物事を進めていくとき、「これしかない」という考え方にとらわれてしまうと、周囲の人とのすれ違いや、無用な衝突を生んでしまうことがあります。もちろん、自分なりに考え抜いたアイデアや意見には自信を持って取り組みたいものですが、それがすべての状況において最適な答えとは限りません。
たとえば、ある場面では効率を優先することが求められても、別の場面では丁寧なプロセスを重視した方がよい場合もあります。そんなときに、「このやり方が正しい」と頑なになってしまうと、まわりの意見や変化に対応できなくなってしまいます。
一つの答えに固執しないというのは、視野を広く保つことでもあります。「こういうやり方もあるかもしれない」「この人の立場から見るとどう見えるだろう」というように、さまざまな可能性を受け止めながら考える姿勢が、結果的に組織を円滑に動かす助けになるのです。
立場を変えて物事を考える大切さ
思考の柔軟性を高めるためには、「自分の立場」からだけではなく、「相手の立場」や「全体の視点」からも物事を考えることがとても有効です。たとえば、自分が上司だったらどう感じるだろうか、あるいはチームメンバーだったらどう思うか、そうした視点の切り替えができると、判断や行動の質が大きく変わってきます。
人はそれぞれ立場や背景が違い、それによって感じ方や考え方も異なります。だからこそ、自分とは違う考え方に触れたときに「なんでそう思うのか分からない」と突き放すのではなく、「どんな気持ちでそう言っているのだろう」と想像してみることが、よりよい関係や意思決定につながっていきます。
立場を変えて考えることができる人は、まわりから見ても「信頼できる人」として映ります。それは、ただ人に優しいというだけでなく、組織全体のバランスを見ながら判断をしているという安心感にもつながるからです。視点を柔軟に切り替えることが、より多くの人にとって納得感のある方向へと導いていく力になるのです。
意見の違いを活かす考え方
組織の中では、さまざまな意見や価値観が存在します。それは時に、衝突や摩擦を生む原因にもなりますが、視点を変えると、それはとても豊かな資源でもあります。意見の違いがあるからこそ、新しい発想が生まれ、盲点に気づくことができるのです。
自分の考えと異なる意見に出会ったとき、「それは違う」とすぐに否定するのではなく、「そういう見方もあるのか」と一度立ち止まって受け止めてみる。この柔らかい姿勢が、対話の質を高め、より建設的な関係性をつくる土台になります。
また、意見の違いを恐れずに向き合える人は、まわりから見ても「冷静で落ち着いている」「感情に流されない」と映ります。そうした安心感が、結果として信頼につながり、「あの人と一緒に考えたい」「一緒に進めたい」と思われる存在になるのです。
思考の柔軟さは、一つの能力というよりも、日々の態度の積み重ねから育っていくものです。自分の考えに自信を持ちつつも、まわりの声や状況の変化にも素直に耳を傾けられる姿勢を大切にすることで、組織を動かす存在として、より深く成長していけるのではないでしょうか。
人間になるとはどういうことかを組織の中で考える

「人間になる」という言葉は、一見とても抽象的で、どこか哲学的にも聞こえるかもしれません。でも、組織の中で本当に誰かを動かす存在になりたいと考えるとき、この言葉が意外なほど深く、そして具体的に意味を持ってくることに気づくはずです。
組織にはルールがあります。役割があります。目標があります。そして、それぞれの人には立場があり、求められるふるまいがあります。けれど、その枠の中だけで行動しているだけでは、どこかぎこちなく、温かみのないものになってしまうことがあります。そんなとき、「人間としてどうあるか」という視点は、忘れてはいけない大切な問いかけになります。
組織の一員としてだけではなく、「一人の人間としてどう関わるか」を意識できる人は、周囲との関係にも、仕事の進め方にも、温度のあるやさしさや誠実さを滲ませることができます。それは、とても自然な形で周囲に伝わり、組織を動かす力として静かに広がっていきます。
では、「人間になる」とはどういうことなのか。ここからは、その意味を少しずつ掘り下げて考えてみましょう。
他者との関係性の中で生まれる「人間らしさ」
私たちは、他の誰ともまったく同じではない、個別の存在として生きています。でも、それと同時に、常に誰かとの関係の中で日々を過ごしているものでもあります。職場であれば、同僚や上司、部下や顧客との関係があり、それらの関係が複雑に絡み合いながら、組織は成り立っています。
「人間になる」というのは、この関係性の中に自分自身をしっかりと置き、ただの役割や機械的な動きではなく、「気持ち」や「思いやり」や「共感」をもって関わるということでもあります。たとえば、誰かが元気がないときにそっと声をかけること。失敗した仲間を責めるのではなく、その気持ちに寄り添って言葉をかけること。そうした行動の積み重ねが、「人間らしさ」として周囲に伝わっていくのです。
人は、誰かに理解されたい、受け入れてもらいたいという気持ちを持っています。そして、そんな気持ちに寄り添える人が、組織の中にいるというだけで、職場の空気は温かくなり、そこから小さな変化が始まっていくのです。
思考と感情と行動をつなげる意識
仕事を進めていく中では、効率や論理が重視される場面も多いでしょう。数字や目標に追われる日々の中で、感情を置き去りにしてしまうこともあります。でも、感情を無視したり抑え込んだりしてしまうと、どこかで無理が出てきます。人間は、感情の生き物です。そしてその感情が、行動や判断に大きな影響を与えるものでもあります。
だからこそ、「自分はいまどう感じているか」「なぜそのように感じているのか」を丁寧に見つめることが大切です。そして、その感情をただ振り回されるのではなく、自分の中で受けとめ、どう動くかを選び直す力。それが「思考と感情と行動をつなげる」ということなのです。
たとえば、ある場面で苛立ちを感じたとき、そのまま怒りを表に出してしまえば、まわりとの関係はギクシャクしてしまうかもしれません。でも、その苛立ちの裏にある「分かってもらえない寂しさ」や「もっと良くしたいという願い」に気づくことができれば、そこから建設的な言葉や行動を選ぶことができるようになります。
このように、自分の中の感情を無視せず、丁寧に扱うことができる人は、周囲に対しても深い共感を持って接することができます。その姿勢が、信頼を生み、組織を動かす力として少しずつ形になっていくのです。
感受性と自己理解を深めることの意味
組織の中で何かを変えたいと思ったとき、まず最初に向き合わなければならないのは、自分自身かもしれません。自分がどんな価値観を持ち、どんなときに嬉しくなり、どんなことに傷つくのか。そうしたことを少しずつ理解していくことで、他人との違いを受け入れる準備が整っていきます。
感受性とは、単に「感情的である」ということではなく、まわりの空気や人の気持ち、小さな変化に気づける繊細さや感性のことでもあります。その感受性が豊かであればあるほど、組織の中でまだ言葉になっていない声や、見過ごされがちな違和感に気づくことができ、それを丁寧に形にしていくことができるようになります。
一方で、自分の気持ちに鈍感になってしまうと、まわりの気持ちにも寄り添うことが難しくなります。だからこそ、自分をよく知り、感情の流れを大切にすることが、実は組織の中でのコミュニケーションや判断にも深く関わってくるのです。
「人間になる」という言葉には、そんなふうに自分自身との関係を深め、他者とのつながりを丁寧に築いていこうとする姿勢が込められているように思います。そしてその姿勢こそが、組織を動かすうえで欠かせない「土台」になっていくのではないでしょうか。
動かす人間として必要な対話力
組織の中で「動かす存在」になるには、自分ひとりで頑張るだけでは足りません。周囲の人たちと協力しながら、信頼関係を育み、同じ方向へ進んでいく力が必要になります。そのときに大切になるのが「対話力」です。
ここで言う対話力とは、ただ上手に話す能力のことではありません。相手の話を丁寧に聞き取り、自分の考えを一方的に押しつけるのではなく、相手の立場を尊重しながら言葉を交わしていく力のことを意味します。特に組織の中では、立場や考え方の違いがある人とも関わっていく必要があるため、対話力はあらゆる場面で大切な役割を果たします。
組織を動かす人は、言葉を通じてまわりに安心感を与えたり、関係をなめらかにしたり、新しい動きを生み出したりします。そんな対話の力を深めていくことで、目には見えにくいけれど確かな変化が起こり始めるのです。
聞く力が生む信頼の土台
対話の出発点は「聞くこと」にあります。ただ相手の言葉を耳に入れるだけでなく、「どんな気持ちでそれを話しているのか」「何に困っていて、何を伝えたいのか」を想像しながら丁寧に耳を傾けることが、本当の意味での「聞く力」です。
聞いてくれる人がいると、それだけで安心感が生まれます。「この人なら、自分の思いを受けとめてくれる」と感じると、人は自然と心を開いていきます。その安心感が信頼につながり、結果として対話の質を深めていくことができるのです。
また、ただ黙ってうなずくだけでなく、相手の話に対して適度に問い返したり、「それは大変だったね」と感情に寄り添う一言を添えたりすることで、聞くこと自体が相手への贈り物のようになります。そのやさしさは、組織の空気を静かに変えていく力を持っています。
対立を乗り越える対話の工夫
組織で仕事を進めていると、ときに意見がぶつかったり、考え方の違いから衝突が生まれたりすることもあります。そうした場面では、対話が避けられがちになりますが、むしろ対立しているときこそ、対話の力が問われます。
大切なのは、「勝つか負けるか」のような議論にしないことです。相手を打ち負かすのではなく、「どうしたらお互いにとってよい形が見つかるか」という視点で対話を重ねることが求められます。
たとえば、相手の意見を受けとめつつも、「私はこう感じています」と自分の気持ちを伝える言い方をすることで、緊張が和らぐことがあります。「あなたは間違っている」と断定するのではなく、「私はこう思っている」と自分の視点から話すことによって、相手も心を開きやすくなります。
対立は悪いことではありません。それは、多様な価値観が組織に存在している証でもあります。大切なのは、その違いをどうやって乗り越え、調和していくかという視点です。そこに対話の工夫が活かされていくのです。
沈黙や曖昧さと向き合う姿勢
対話の中には、ときに「沈黙」や「曖昧な表現」が含まれることがあります。たとえば、言いたいことがあるけれど言葉にできないまま黙ってしまう人、もしくは「まあ、そんな感じで」とはぐらかすような表現をする人もいます。
そうした場面に出会ったとき、すぐに答えを求めようとするのではなく、その沈黙や曖昧さを「大切な情報」として受けとめる姿勢が、対話力の深さにつながります。「何か言いたいことがあるのかもしれない」「うまく言葉にできないだけかもしれない」と考えながら、その空間にそっと寄り添うことで、相手は少しずつ心を開いていくようになります。
また、自分自身が曖昧な気持ちを抱えているときにも、無理に答えを出さず、「今ははっきりとは言えないけれど、少しずつ考えていきたい」と正直に伝えることも、対話の一つです。曖昧な状態をそのまま大切にすることで、相手との関係にもゆとりが生まれ、深い信頼につながっていきます。
対話とは、言葉だけで成立するものではなく、沈黙や間合い、表情や姿勢も含めた、ひとつの「関係性のかたち」です。その繊細な空気を読み取り、そこにやさしく関わっていく力が、組織をなめらかに動かしていくために欠かせないものとなっていくのです。
組織で見えない声を拾い、価値を生み出す力

組織の中で変化を起こしたい、周囲に働きかけて動かしていきたいと願う人にとって、特に大切にしたい視点があります。それが「見えない声を拾う力」です。職場では、いつも大きな声で意見を発信する人だけが組織を支えているわけではありません。声にならない小さなつぶやきや、言葉にはならない表情や態度の中にも、組織の状態を示す大切なメッセージが込められています。
たとえば、「大丈夫です」と言いながらもどこか元気がなかったり、会議で発言はしないけれど何かを言いたそうな雰囲気を漂わせていたり、そんな微細な変化に気づける人が、組織にとって貴重な存在になっていきます。そして、その小さな声を拾い、それを形にしていくことで、周囲の人が安心し、組織に信頼とあたたかさが生まれていくのです。
ここでは、そうした「見えない声」をどのように受けとめ、どうやって価値に変えていくのかを丁寧に考えていきます。
声に出さない想いを汲み取る感性
見えない声を拾う力は、いわば「感性」に近い部分です。表情やしぐさ、沈黙やちょっとした間に隠れている想いを、そっと感じ取ろうとするやわらかな感受性が求められます。人は、言葉にしないからといって何も感じていないわけではありません。むしろ、声に出せないからこそ内側で多くのことを抱えている場合も少なくありません。
職場でも、遠慮や気配りから本音を言えない人がいたり、自信が持てずに意見を控えている人がいたりすることはよくあります。そんなときに、「あ、この人、何か気にしているのかもしれないな」と察知できるかどうかは、組織の空気を読み取り、支えるうえでとても大切な力になります。
この感性は、一朝一夕に身につくものではないかもしれません。でも、日常の中でまわりの様子を丁寧に観察し、「この人は今、どんな気持ちなのだろう」と思いをめぐらせる習慣を持つことで、少しずつ育っていきます。声に出ない部分にも気づこうとする姿勢が、人と人との信頼を深めていく第一歩になります。
小さな違和感に気づく観察力
見えない声というのは、ときに「違和感」として現れます。たとえば、いつもより会話が少ない、動きが鈍い、笑顔が見られない、そんな些細な変化に気づけるかどうかが、とても重要になってきます。それはまるで、組織の体温を測るような行為です。
この違和感は、無視してしまうこともできます。でも、そこにきちんと目を向けられる人は、組織の健やかさを保つために大きな役割を果たします。たとえば、何も言っていないけれど実は疲れているメンバーに対して、休息を促すひと言をかけることができれば、それだけで安心感や感謝の気持ちが生まれます。
違和感に気づく観察力とは、決して疑いの目で人を見ることではなく、「その人の内側に、何か揺れがあるかもしれない」とそっと寄り添うような目線のことです。それは、静かだけれど、とてもあたたかいまなざしです。そのまなざしに支えられることで、声を出せなかった人が少しずつ自分の言葉を取り戻していけるようになるのです。
気づいたことを形にする実行力
見えない声に気づいたら、次に大切なのは「それをどう扱うか」です。せっかく受け取った想いをそのままにしてしまえば、それはやがて薄れてしまいます。でも、そこから一歩踏み出して、「この声を、どうすれば組織の力に変えられるだろう」と考え始めたとき、それは大きな価値となって組織の中に広がっていきます。
たとえば、発言しにくそうにしていた人に個別で声をかけて話を聞いてみたり、会議の進め方に配慮を加えてみたりするなど、小さな行動でもその影響は確実に届いていきます。気づいたことを丁寧に扱い、それを行動に移す力が、見えない声を価値に変えていくために欠かせません。
実行力と聞くと、大きなプロジェクトや改革のようなことを想像するかもしれませんが、ここでいう実行力とは、もっとさりげない、日常の中の小さな変化を生み出す行動のことです。誰かのつぶやきに耳を傾け、それを丁寧にすくい上げ、形にして返す。その循環の中で、組織は少しずつ、人の想いが大切にされる場所へと変わっていくのです。
立場を超えて周囲に影響を与える行動とは
組織の中で誰かを動かす存在になることは、必ずしも役職や肩書きが必要というわけではありません。むしろ、リーダーという名がつかなくても、そのふるまいや言葉、さりげない気づかいによって、周囲の空気を和らげたり、動かしたりできる人はたくさんいます。立場の有無に関係なく、まわりの人の心に働きかけられる力。それが、組織の中で本当の意味で影響を与える力なのです。
影響力とは、「注目されていること」や「権限があること」ではありません。むしろ、自分の在り方や日々の行動が、誰かにとっての希望になったり、背中を押す存在になったりすることのほうが、ずっと深く人の心に届くものです。ここでは、立場を超えて周囲に良い影響を与える行動とはどのようなものかについて、丁寧に考えてみましょう。
役割にとらわれない貢献のしかた
多くの人が、組織の中で自分に与えられた役割や担当の範囲内で責任を果たそうとします。それはとても大切なことであり、基本でもあります。でも、そこに少しだけ「プラスα」の視点を持てると、まわりからの信頼や評価が自然と変わっていくのです。
たとえば、自分の担当外であっても、誰かが困っていたらそっと手を差し伸べるとか、特別な知識やスキルがなくても「何かお手伝いできることありますか?」と声をかけるだけでも、それは立派な貢献になります。そして、そのような姿勢を見た人は「自分もそうしよう」と思い始め、チームや組織全体にあたたかい循環が生まれていきます。
役割にとらわれず、自分ができることを探す。無理のない範囲で少し踏み出す。そうした自然体の貢献が、まわりにポジティブな波を生み、やがては自分自身の存在感にもつながっていくのです。
チームに安心感をもたらすふるまい
安心感というのは、組織にとってとても大切な土壌です。どんなに優れたスキルや戦略があっても、職場の中に「安心していられる空気」がなければ、人は本来の力を出すことができません。そして、この安心感を生み出すのは、決して特別な立場の人だけではありません。むしろ、日常の中でまわりに気を配る人、感情の起伏が穏やかで、いつも落ち着いた態度で接する人こそが、その空気を支えているのです。
たとえば、忙しいときでも少し笑顔を見せてくれる人、誰かの意見に否定せず耳を傾ける人、話しかけやすい雰囲気を持っている人がいるだけで、職場の空気は柔らかくなり、心がほっとします。そんなふるまいが、実は大きな影響力を持っているのです。
安心感は、目に見えないけれど確実に伝わるものです。だからこそ、自分の感情や態度がまわりにどんな影響を与えているかを意識し、できるだけ穏やかであたたかい関わり方を心がけることで、自然とまわりの人の気持ちもほぐれていくのです。
自分を律し、他者に希望を与える姿勢
周囲に影響を与える人は、自分自身と向き合い続ける姿勢を大切にしています。感情に振り回されそうになったときに一呼吸おいて冷静になる、困難な状況でも丁寧に向き合う、誰かに嫌なことを言われても感情的に返さず穏やかに対応する。こうした姿勢が、まわりの人にとっての「安心」や「希望」につながっていきます。
人は、自分の姿を通じて何かを示してくれる人に心を動かされます。言葉ではなく、生き方そのものがメッセージになっているような人の姿に、静かな感動を覚えることがあります。そんな人のまわりには、自然と人が集まり、信頼され、「あの人がいると安心する」「一緒にがんばろうと思える」という感情が育まれていきます。
そしてそれは、決して完璧である必要はありません。むしろ、弱さや迷いを抱えながらも、自分にできることを一生懸命にやろうとする姿にこそ、人は共感し、励まされます。立場を超えて影響を与えるというのは、そうした「ありのままの姿」がまわりに伝わっていくことでもあるのです。
動かす人間としての成長に必要な自己理解

組織の中で誰かを動かすような存在になるためには、まず「自分自身をよく知ること」が出発点になります。自己理解が進むと、自分の中にある価値観や感情の動き、人との関係でどう反応するかといったことが少しずつ見えてくるようになります。そして、その理解は他者との関係にも大きく影響し、自分らしい関わり方や対話のあり方を築く支えとなっていくのです。
自己理解は、自信をつけるための手段でも、完璧を目指す道でもありません。むしろ、揺れたり、迷ったりする自分に対して、「そんな自分でも大丈夫」と認めることが、動かす人間としてのしなやかさにつながっていきます。ここでは、自己理解の大切さと、その成長の過程について深く掘り下げてみましょう。
自分の価値観を明確にするプロセス
私たちは日々、さまざまな選択をしています。どんな言葉を使うか、どの人とどんな距離感で関わるか、どこに力を入れるか、それらの選択は、実はすべて、自分が大切にしている価値観に影響されています。
たとえば「丁寧であること」を大事にしている人は、業務を急ぐ場面でも細かな部分を確認したり、「仲間との信頼」を重んじる人は、成果よりもチームワークを優先した行動を選ぶかもしれません。このように、自分が何を大切にして生きているのかを知ることは、迷ったときの指針になりますし、他者との関係の中でも「私はこういう考えを持っています」と伝える基盤になります。
価値観を明確にするためには、自分の過去の経験を振り返ってみるのもひとつの方法です。何に心が動いたのか、何に傷ついたのか。その背景にある思いや判断基準を見つめ直してみると、自分の中に一貫してある「大切なもの」が見えてくることがあります。
その価値観に正解も不正解もありません。ただ「自分にとって本当に大切なものは何だろう」と丁寧に向き合う時間が、少しずつ自己理解を深めてくれるのです。
内省を習慣にするためのヒント
自己理解は、一度考えれば終わるものではありません。むしろ、日常の中で継続的に「内省」をすることによって、少しずつ深まり、やがて自分の行動や言葉に自然と表れてくるようになります。内省とは、自分の行動や感情をふりかえり、「なぜそうしたのか」「どう感じたのか」を静かに見つめる作業です。
たとえば、一日の終わりに「今日、一番うれしかったことは何だっただろう」「あのとき、なぜ言葉に詰まったのだろう」と自分に問いかけてみることで、見過ごしていた気持ちや考え方に気づくことがあります。その気づきが、次に同じような場面に出会ったときの行動を変えるヒントになってくれるのです。
また、日記をつける習慣や、誰か信頼できる人との会話の中で自分の気持ちを整理することも、内省の一つの方法です。大切なのは、自分を責めるのではなく、「気づくこと」を優しく受けとめる姿勢です。そうした習慣が、少しずつ自分の内面を明るく照らし、行動にもやわらかさや落ち着きをもたらしてくれます。
動かす存在になるということは、誰かに影響を与えることでもありますが、その前に、自分自身の心の動きを丁寧に見つめることが土台になります。内省は、そのための静かな時間であり、自己理解を深めるためのあたたかい営みなのです。
弱さを受け入れたうえで進む強さ
私たちはどうしても、自分の「できていない部分」や「不完全なところ」に対して、否定的な感情を持ちやすくなります。でも実は、その弱さを無理に消そうとするよりも、「そんな部分もあるよね」と穏やかに受け入れられるほうが、ずっと強さにつながるのです。
組織の中でも、自分の弱さを隠そうとしすぎると、かえってまわりとの距離が生まれたり、必要な助けを求めにくくなったりすることがあります。けれども、素直に「ここはちょっと苦手で…」と打ち明けることができたとき、そこに信頼や安心感が生まれることがあります。そして、そんな言葉を聞いたまわりの人たちも、「自分も無理をしなくていいんだ」と感じるようになります。
弱さを受け入れるというのは、あきらめることではありません。むしろ、その事実を自分の中に置いたうえで、「では自分にできることは何か」と前を向いて考えられる力を持つということです。そういう人の姿には、どこか凛とした優しさがあり、その姿がまわりに良い影響を与えていきます。
自己理解を深め、弱さを含めた自分自身を認めること。それが、動かす存在として成長し続けていくための、静かだけれどとても大きな一歩なのです。
今すぐ始められる自己変革のヒント
「組織を動かす人間になりたい」「まわりに良い影響を与えられる存在でありたい」と思ったとき、どこか大きな挑戦をしなければならないような気持ちになるかもしれません。でも、自己変革というのは、必ずしも劇的な変化を起こすことではなく、もっと身近な、小さな一歩からでも始められるものです。
むしろ、毎日の暮らしの中にある小さな選択や心の動きに目を向けることこそが、確かな変化につながっていきます。そして、その変化は、まわりに対する関わり方をやわらかくし、自分自身にも穏やかさと芯の強さを育ててくれるものになります。
ここでは、今日からでも始められる「自分を少しずつ変えていくためのヒント」を、一緒に見つけていきましょう。
日常の選択を変える勇気
私たちは日々、さまざまな選択をしています。朝どの道を歩くか、誰に声をかけるか、メールにどんな言葉を添えるか、そのひとつひとつは小さなことのように見えて、積み重なることで大きな意味を持ってきます。
たとえば、いつもより少し早く出社してみるとか、普段あまり話さない同僚に自分から話しかけてみるとか、自分の中で「これまでやってこなかったけれど、気になっていたこと」をあえて選んでみること。それが、自分を変えるための最初のステップになります。
変わるというのは、何かをやめることではなく、「新しい自分のあり方に一歩近づくこと」です。小さな選択をひとつ変えるだけで、見える景色やまわりとの関係が少しずつ変化していきます。その積み重ねが、気がつけば「自分、ちょっと変わってきたな」と感じられる瞬間につながるのです。
自己対話で習慣を整える方法
自己変革を続けていくためには、自分自身との対話を日々の習慣として取り入れることがとても大切です。たとえば、「今日はどんな気持ちだった?」「今、一番気がかりなことは何?」といった問いを、自分の心にそっと投げかけてみる時間を持つことで、気づかなかった感情や思考のクセに出会うことができます。
このような自己対話は、紙に書き出す形でも、頭の中で静かに問いかけるだけでもかまいません。大切なのは、「正しい答えを出すこと」ではなく、「いまの自分をそのまま受けとめること」です。たとえ疲れていたとしても、焦っていたとしても、「そうなんだね」と自分に声をかけてあげることで、不思議と心が整い、落ち着いて次の行動を選べるようになります。
自分の内側と向き合う時間は、忙しい日々の中では後回しになりがちです。でも、1日数分でもいいから、静かに自分の心に目を向ける習慣をもつことで、自分自身の変化にも気づきやすくなり、自己変革への意識が自然と深まっていくのです。
小さなチャレンジを習慣にする
「変わりたい」と思うとき、最初に大きな目標を立てたくなることがあります。でも、長続きする変化というのは、むしろ「小さなチャレンジを習慣にすること」から生まれるものです。たとえば、毎日ひとつだけ新しい行動をしてみるとか、あいさつを少しだけ意識して丁寧にしてみるとか、本当にささやかなことでかまいません。
大切なのは、「続けることが目的」ではなく、「やってみてどう感じたか」に意識を向けることです。小さな挑戦を繰り返すことで、「あ、自分ってこんなふうに動けるんだ」と新しい一面を発見することができ、その発見が次のチャレンジへの原動力になります。
また、習慣化の中には「できなかった日」があっても大丈夫です。休んでも、また戻ればいいだけの話です。完璧を目指すよりも、自分のペースを大切にしながら、「ちょっとずつでいいから変わっていこう」と思えることの方が、長い目で見て大きな成長につながります。
自己変革とは、自分を否定して新しく作り変えることではなく、すでに自分の中にある可能性に気づき、それをやさしく育てていくこと。その始まりは、ほんの小さな一歩から始まるのです。
まとめ
組織を動かす存在になるということは、特別なスキルや肩書きが必要なわけではありません。むしろ、自分の内側にある声に耳を傾けながら、まわりの人との関係性を大切に育み、丁寧に日常と向き合う姿勢が、自然と周囲に影響を与える力へとつながっていくのです。
「動かす人間になる」というテーマのもとに、ここまでさまざまな視点からお話をしてきました。まずは、組織の中で信頼されるためには何が大切かを見つめ、自ら動くことで少しずつ空気が変わることを実感し、そして対話や思考の柔軟性を通じて、相手とよりよい関係を築いていく。その過程の中で、自己理解を深め、自分の弱さにもやさしく向き合いながら、ありのままの自分でまわりに貢献していく。これらの積み重ねが、結果として「組織を動かす人」へと育っていくための道なのだと思います。
声にならない想いに気づき、それを行動に移していくことは、決して簡単なことではありません。でも、だからこそ意味があります。日々の中で、ほんの少し勇気を出して声をかける、相手の表情に目を向ける、自分自身と静かに対話する。そうした一つひとつの行動の中に、確かに変化の芽が宿っています。
また、立場に関係なく影響を与えることができるという事実は、多くの人にとって希望になるはずです。「私は何者でもない」と感じる日があったとしても、誰かの安心になるような言葉をかけたり、気づかれないけれど意味のある行動を積み重ねたりすることで、あなたの存在は確実にまわりに影響を与えています。
最後にお伝えしたいのは、自己変革はいつからでも始められるということです。大きな一歩を踏み出す必要はありません。今日、ほんの少しだけ自分の選択を変えてみる。いつもよりゆっくり誰かの話を聞いてみる。そんな小さな行動の積み重ねが、やがて組織全体のあたたかさや動きにつながっていきます。
組織を動かす力は、誰か特別な人だけが持っているものではありません。あなた自身の中にも、すでにその力の種は存在しています。その種にそっと水をあげるような気持ちで、日々を丁寧に過ごしてみてください。そうすれば、いつの間にかあなたは、組織にとってかけがえのない「動かす人間」として、しっかりと根を張っているはずです。