
「毎日、仕事が思うように進まない」「集中力が続かない」「必要なものがすぐに見つからない」。そんなモヤモヤを感じるとき、もしかするとその原因は、あなたの“身のまわり”にあるかもしれません。実は、整理整頓された職場環境は、仕事の効率や集中力、そして心の余裕にまで大きな影響を与えてくれます。
この記事では、「捨てる」「決める」「もどす」という3つのやさしいステップを通じて、誰でも無理なく始められる整理整頓の方法をご紹介します。道具や仕組みの話だけでなく、どうすれば続けられるか、どんな気持ちで取り組めばよいかといった心の部分にも寄り添いながら、あなたの働く毎日を少しずつ心地よく整えていくためのヒントを詰め込みました。
「何から始めればいいのかわからない」と悩んでいる方も、「きれいにしてもすぐ元通りになってしまう」と感じている方も、大丈夫です。ほんの小さな一歩が、確かな変化につながっていきます。さあ、今日から一緒に、仕事がもっとスムーズになる“整った空間づくり”を始めてみませんか?
この記事の目次(タップでジャンプ)
職場の整理整頓が仕事に与える影響とは?

毎日繰り返される仕事の中で、「なぜか集中できない」「思ったより進捗が悪い」と感じることはないでしょうか。そんな時、原因は自分のスキルやモチベーションの低下ではなく、実は目の前の環境、つまり職場の整理整頓が関係していることがあります。周囲が散らかっているだけで、思考の流れが妨げられたり、タスクの優先順位が曖昧になったりするものです。
たとえば、書類が山積みのデスクでは、必要な情報を探すのに時間がかかり、その間に集中力が切れてしまいます。また、視界に入るものが多ければ多いほど、脳が処理すべき情報が増え、知らず知らずのうちに疲労が蓄積されていきます。このように、整理されていない職場環境は、物理的な不便さだけでなく、精神的なストレスの原因にもなり得るのです。
反対に、整った空間は心にもゆとりをもたらしてくれます。必要なものがすぐに手に取れる、机の上がスッキリしていて視界がクリア、そんな職場では、気持ちよく仕事に向き合うことができるでしょう。しかも、仕事中に起こる「ちょっとしたイライラ」を減らすことができれば、それだけで1日の満足度がぐんと高まります。
ここでは、整理整頓が具体的に仕事にどのような影響を与えるのか、「集中力」「時間の使い方」「周囲からの信頼」という3つの視点からじっくり掘り下げていきます。
散らかった職場が集中力に与える影響
人の脳は視覚から得た情報を無意識のうちに処理しています。つまり、目の前がごちゃごちゃしている状態では、目には見えないところで脳が疲れてしまっているのです。たとえば、机の上に複数の書類や文房具、飲みかけのペットボトル、過去のメモが乱雑に置かれていたとしたら、あなたはどこに意識を向けるべきかを瞬時に判断しなければなりません。
この判断が繰り返されることで、脳は徐々に疲弊し、本来注力すべき作業への集中が妨げられます。さらに、「次に何をしよう」「どれが大事な資料だったかな」と考えるたびに思考が分断され、効率はどんどん下がっていきます。集中している時間が短くなれば、当然、仕事の質やスピードにも影響が出るでしょう。
しかし、物が最小限に抑えられているスッキリとしたデスクでは、脳は余計な情報に振り回されず、やるべきことに集中しやすくなります。タスクにじっくりと向き合い、深い思考が求められる仕事にもスムーズに入り込むことができるのです。整理整頓は、いわば集中力を維持するための「環境づくり」そのものであり、自分の脳を働かせる土台となります。
整理整頓がもたらす時間的なゆとり
仕事中、何かを探している時間がどれくらいあるか、意識したことはあるでしょうか。書類を引き出しから出したり、データをフォルダの中から探したりと、1回にかかる時間はわずかでも、それが1日何回もあれば合計で10分、20分というまとまった時間を失っていることになります。
これを1週間、1ヶ月、1年と積み上げると、私たちは驚くほどの時間を「探すこと」に費やしているかもしれません。整理整頓ができていれば、必要な物や情報を探す手間がぐっと減り、その分の時間を他の業務や休息に充てることができるようになります。
また、物の場所が明確に決まっていれば、無駄な動きが減り、作業そのもののスピードも上がります。たとえば、「この資料はあの引き出しの左側にある」と分かっていれば、迷うことなく手が伸び、リズム良く仕事を進めることができます。こうした時間の短縮は、小さなことに思えても、積み重ねると大きな成果につながるのです。
周囲の印象や信頼感との関係性
職場は自分一人の空間ではありません。上司や同僚、時には取引先やお客様など、多くの人が出入りする場所です。そんな中で、自分のデスクや周辺がいつも整っている人には、「しっかりしている」「きちんと仕事ができる」という良い印象が自然とついてきます。
反対に、デスクの上が常に散らかっていたり、資料が山積みになっていたりすると、無意識のうちに「だらしない」「管理が苦手そう」という印象を持たれてしまうこともあります。それが直接的に評価に影響することは少ないかもしれませんが、信頼感を築くうえでの小さな積み重ねが、将来的に大きな差を生む可能性もあるのです。
また、整理整頓された職場環境は、チーム全体の働きやすさにも影響します。誰がどこに何を置いたかがすぐに分かれば、引き継ぎやサポートもスムーズになり、無駄な確認作業が減ります。つまり、個人の整理整頓が、チーム全体の生産性や雰囲気づくりにも良い影響を与えているということです。
「捨てる」で始める整理整頓の第一歩
整理整頓という言葉を聞いたとき、多くの人が最初に思い浮かべるのが「片づけること」や「キレイに並べること」かもしれません。しかし、本当の意味で職場の環境を整え、生産性を高めるには、まず“物を減らす”という行動から始めることがとても大切です。
つまり、「捨てる」というシンプルなステップこそが、整理整頓の出発点になります。
職場には、意識していなくても、いつのまにか溜まってしまった不要な資料や古い文房具、使っていない備品などが存在しています。これらは、使うことのないものにも関わらず、日々の視界に入り、スペースを占領し、場合によっては探し物の妨げにもなってしまいます。だからこそ、まずは「何を残して、何を手放すか」を自分なりの基準で見直すことが必要なのです。
このセクションでは、「捨てる」ことを通じて、どのように整理整頓の第一歩を踏み出せるのかを詳しく解説していきます。迷わずスムーズに進められる考え方と方法を、やさしく丁寧にご紹介します。
捨てる基準を決めて迷わないコツ
「捨てる」と言っても、何をどのように手放せばいいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。判断に迷ってしまい、「もしかしたら使うかも」「誰かが必要とするかもしれない」と考えると、なかなか決断できなくなります。
そんなときは、自分なりの“捨てる基準”を事前に決めておくことがとても有効です。たとえば「半年以上使っていないもの」「内容が古い資料」「名前や用途がすぐに分からない物品」など、自分の職場環境に合った明確なルールを設定しておくと、感情に左右されずに判断がしやすくなります。
また、「どうしても捨てるか迷うもの」は、一時的に保管するための“保留ボックス”を用意しておきましょう。一定期間内に必要な場面がなかった場合、そのときに潔く手放すという方法もあります。このように、感覚ではなくルールや期限をもって「捨てる」を進めることで、思考もクリアになり、スッキリとした気持ちで次の整理ステップに進むことができます。
書類・文房具・資料の処分方法
実際に職場で「捨てる」対象として最も多いのが、紙の書類や古くなった文房具、保管されたまま見返されることのない資料などです。これらは一見すると量が少ないように見えても、見直してみると意外なほどスペースを占めていることがあります。
まず、書類に関しては、最新のものだけを残し、それ以外は処分またはデータ化を検討しましょう。紙で残す必要がない場合にはスキャンして保存し、元の紙は廃棄することで、物理的なスペースを有効活用できます。
文房具についても、壊れていたりインクが出ないペン、使わないクリップ類などは思い切って処分しても問題ありません。なぜなら、「予備のつもりで持っているもの」が多くなればなるほど、本当に使いたいものが見えにくくなってしまうからです。
さらに、資料も「最新情報かどうか」「業務に関連しているかどうか」を基準に見直すことで、自然と優先順位が明確になり、手放すべきものが見えてきます。物が減ると、それだけで探し物の時間が減り、作業スペースも広がるため、業務全体が効率的になります。
「いつか使うかも」を手放す考え方
「もしかしたら、いつか使うかもしれない」そう思って、物をなかなか手放せない人も多いかもしれません。確かに、過去に1度だけ使った資料や、まだ使えるけど出番がないアイテムを見ると、「まだ使えるのに捨てるのはもったいない」と感じてしまうのは自然な感情です。
しかし、ここで大切なのは、「その“いつか”は本当にやってくるのか?」という視点で見直すことです。1年、2年と使われていないものは、今後も活躍する可能性はかなり低いと考えてよいでしょう。特に職場では「今の業務」に必要なものが最優先されるべきで、「過去の名残」や「未来の曖昧な可能性」だけで物を保管するのは、効率の妨げになります。
また、「もったいない」と感じたときには、その物が本来持っていた役割をすでに果たしてくれていた、という視点を持つことも助けになります。「ありがとう」と心の中で感謝しながら手放すことで、気持ちにも整理がつきやすくなります。そして、物が減ることは、新しい発想や仕事の可能性を広げてくれるスペースを生み出すことでもあるのです。
決めるで整える定位置ルールの作り方

整理整頓の第一歩として「捨てる」ことに取り組んだあとは、次のステップとして「決める」段階に移ります。この“決める”という行動は、物の定位置を決めることを指します。つまり、どこに何を置くかをしっかり決めておくことで、使うたびに迷ったり、毎回探したりすることがなくなり、日常業務の中での小さなストレスを取り除くことができるのです。
職場で整理整頓を成功させるためには、「使う物を戻す場所が明確になっているかどうか」が大きなカギを握っています。どれだけ物を減らしても、置き場所が決まっていなければすぐに散らかってしまいますし、自分以外の誰かが使うときに分からなくなってしまう恐れもあります。
このセクションでは、職場で活用できる“定位置ルール”の決め方や、その実践のポイントについて、具体的な視点でわかりやすくご紹介します。ルールを作るというと少し堅苦しく聞こえるかもしれませんが、実はちょっとした工夫で、日常の業務がぐんと快適になります。
よく使うものを最適な場所に配置する
定位置を決めるときに大切なのは、「使用頻度」と「使う場面」をしっかりと意識することです。よく使うものほど、すぐに手が届く位置にあることが理想です。たとえば、毎日何度も使うペンやメモ帳は、目の前に置いたペン立てや引き出しの一番手前など、“動作の少ない場所”に配置することで、自然と作業のリズムが整っていきます。
また、業務ごとに使用する道具が決まっている場合は、それぞれのタスクに応じた“セット化”をしておくと便利です。たとえば、会議用の資料セットや郵送業務に使う封筒・切手・住所印などをひとまとめにしておけば、業務の切り替えもスムーズになります。
物を置く場所が「何となく」ではなく「ここにあるべき理由」が伴っていれば、その空間自体が使いやすく、自然と整った状態をキープできるようになります。定位置を決めることで、仕事の段取りも自然と良くなっていくのです。
誰が見てもわかる収納ルールの工夫
自分ひとりで使うデスクやロッカーであっても、職場は基本的に共有の空間であることが多く、他の人が使う可能性を考えてルールを作ることも大切です。とくにチームで物品を共有する場面では、「自分は分かっているけれど他の人には伝わっていない」状態は、混乱やミスの原因にもなりかねません。
そこで有効なのが、「誰が見ても一目で分かる収納」の工夫です。たとえばラベルを貼る、色で分ける、透明の収納グッズを使って中身を見えるようにするなど、ちょっとした工夫を加えるだけで、整理整頓の継続がぐっとラクになります。
また、収納ルールをチームで共有することも重要です。「これはここに戻す」「ここにある物は使ってOK」といったルールを簡単にまとめて掲示しておくだけでも、共通認識が生まれ、誰もが同じように動ける環境が整っていきます。こうした“見えるルール”は、整理整頓だけでなく、チームの信頼や効率にも良い影響をもたらします。
チーム全体で共有する仕組みづくり
どれだけ個人の定位置管理がうまくいっていても、チームとしての運用が整っていなければ、時間が経つにつれて乱れが出てしまいます。そこで大切なのは、整理整頓に関する“共通ルール”をチーム全体で持つことです。チーム全体で取り組めば、「あの人だけがやっている」ではなく、「みんなで整える」という意識が生まれます。
たとえば週に1回、軽く周囲の整理状況をチェックし合う時間を設けたり、月に1度「整理整頓ミーティング」のような時間をとって、使いづらいところや改善点を共有するのも良い方法です。このようにして、全員が当事者意識を持つことで、職場の空間はより整いやすくなります。
また、新しい人が入ってきたときにも、決められたルールがあることでスムーズに馴染むことができます。誰かが特別な努力をしなくても、全体で自然と整った環境を維持できるようになるため、結果的にチーム全体の仕事の質も向上していくのです。
もどすを徹底するための意識づけ
整理整頓の3ステップ「捨てる・決める・もどす」の中でも、実は「もどす」が最も地道で、かつ習慣化のカギを握る行動です。どれだけ物を減らし、どこに置くかを明確に決めたとしても、使ったあとに元の場所へ戻すことが継続されなければ、職場はすぐに元の状態に逆戻りしてしまいます。
しかし、「もどす」という行動は、一つひとつはとても小さな動作です。ペンを引き出しに戻す、書類をファイルボックスに差し込む、使った備品を棚にしまう──どれも数秒で終わることばかり。それでも、これが日常的に忘れられると、数日でデスクの上や共用スペースは乱れ、探し物が増え、効率が落ちていきます。
このセクションでは、整理整頓を持続可能にする「もどす」習慣を、無理なく生活の中に取り入れていくための意識づけと工夫を、やさしく丁寧に掘り下げていきます。
習慣化させるための小さなルール
「使ったものは必ず元に戻す」というルールは、一見とても単純ですが、忙しい日常業務の中ではつい後回しにされてしまいがちです。たとえば「あとで戻そう」「もうすぐまた使うかもしれないから出しておこう」と思ってしまうと、それが積み重なり、いつの間にか“散らかった状態が当たり前”になってしまいます。
そこでおすすめなのが、「作業が終わったら、机をリセットする」という意識を持つことです。1つのタスクが終わった時点で、使ったものを全て元の位置に戻すという簡単なルールを取り入れるだけで、空間が整うだけでなく、気持ちの切り替えにもつながります。
たとえば、毎日業務の終わりに「3分だけ整理の時間を取る」という習慣をつけると、自然と“整った状態で次の日を始める”サイクルが生まれます。この数分が、明日の自分の集中力や効率に影響を与えると思うと、少しやる気も湧いてくるのではないでしょうか。
5秒以内に戻せる仕組みの考え方
「もどす」が面倒に感じるのは、戻す場所が遠かったり、出すのに比べて手間が多いからです。つまり、出し入れのアクションが少ないほど、人は自然と元に戻す行動を継続しやすくなります。そこで意識したいのが、「5秒以内に戻せるかどうか」という基準です。
たとえば、書類を戻すためにいちいち立ち上がって棚まで行かなければならないような配置では、忙しい時には「後でまとめて片付けよう」となってしまうことが多いです。ですが、座ったまま手を伸ばせば戻せる場所に収納しておけば、手間がかからず戻すことができ、散らかることが少なくなります。
また、引き出しの中も「戻しやすさ」を意識して工夫してみましょう。文房具は仕切りを使って定位置を明確にし、ファイル類は出し入れしやすい向きに立てて収納するなど、戻すためのアクションを減らすことで、面倒くささが軽減されます。5秒以内に戻せる仕組みは、整理整頓を“苦手”と感じる人にも続けやすい習慣づくりの土台になります。
職場全体で意識をそろえる工夫
自分だけが「もどす」ことを意識していても、周囲が同じように取り組んでいなければ、いつの間にか整った環境は崩れていってしまいます。だからこそ、職場全体で整理整頓に関する意識をそろえておくことが大切です。全員が同じルールを理解し、共有し合うことで、誰か一人に負担が偏ることもなくなります。
たとえば、部署内で使う共用の道具や書類について、「使ったらこの場所に戻す」というルールを目に見える形で掲示しておくだけでも効果があります。また、リーダーや先輩社員が率先して「もどす」姿勢を見せることで、自然とまわりにもよい影響が波及していきます。
「誰かがやってくれるだろう」ではなく、「自分が戻すことで次の人がスムーズに使える」という意識が、職場全体に根づいていけば、気持ちのよい空間と協力的な雰囲気が育まれます。それは結果として、チームの働きやすさや生産性にもつながっていくのです。
整理整頓にかける時間をどう確保するか

「職場の整理整頓が大切なのはわかっているけれど、毎日忙しくて片づける時間なんて取れない…」そんな悩みを抱えている方は少なくないかもしれません。確かに、限られた勤務時間の中で、目の前の業務をこなすだけでも精一杯という日もあるでしょう。けれども実は、ほんの少し時間の使い方を見直すだけで、整理整頓のための時間は十分に捻出できるようになります。
このセクションでは、忙しい人でも無理なく「片づけの時間」を確保するための考え方や、日常の流れにうまく組み込む工夫についてご紹介します。やみくもに時間を増やそうとするのではなく、“今ある時間の中でどう整理整頓を自然に習慣化していくか”に焦点を当ててお伝えしていきます。
1日5分から始める小さなリセット習慣
「整理整頓」と聞くと、つい“時間をかけてしっかりやるもの”という印象を持ちがちですが、実際は短時間でもコツコツ積み重ねることで、十分な効果が得られます。たとえば、毎日業務の始まりや終わりに5分だけ机の上をリセットする時間を取る──たったこれだけでも、職場環境は驚くほど整っていきます。
この「5分」は、無理をしなくても取り組める現実的な時間です。メールを1本返信するよりも短い時間で、ペンを戻す、資料をそろえる、ゴミを捨てるといった基本的な整頓作業がすべて完了します。大がかりな片づけをする必要はなく、ほんの少し“きれいな状態を意識する時間”を持つことが大切なのです。
習慣にしてしまえば、片づけは作業ではなく「呼吸のような行動」になります。「使ったら戻す」「終わったら整える」という行動が、無意識のうちにできるようになると、整理整頓に対する負担感はどんどん小さくなっていきます。まずは毎日5分、そこから始めてみるだけで十分なのです。
業務時間内で整理の時間を取るコツ
職場によっては、「片づけは勤務時間外にやるもの」といった暗黙のルールがある場合もありますが、整理整頓も立派な仕事の一部であるという意識を持つことが大切です。なぜなら、整った環境は業務効率を高めるための“基盤”になるものであり、それを整える時間を取ることは、決して無駄なことではありません。
たとえば、会議が終わった直後に使用した資料を片づける時間を含めてスケジューリングする、週初めや月末のタイミングで「整理整頓タイム」として15分ほど確保する、というように、業務の中に自然な形で整理時間を組み込むことができます。これによって、「わざわざ片づけの時間を取らなければいけない」という負担感が減り、スムーズに継続しやすくなります。
また、チーム全体でこの意識を共有することで、「片づけをすることが職場全体にとってプラスになる」という共通認識が育ちます。すると、「忙しいから片づけられない」と感じていた気持ちが少しずつ和らぎ、安心して整理整頓に取り組める空気が生まれていきます。
週1のチェックリストを活用する方法
忙しい日々の中で、整理整頓を完全にルーティン化するのは難しいこともあります。そこでおすすめなのが、「週に1回のチェックリスト」を使った見直しの仕組みです。これは、自分のデスクや身の回りのスペースが“整っているかどうか”を確認するための、簡単なチェック項目を用意しておくという方法です。
たとえば、「不要な書類が机にたまっていないか」「文房具が定位置に戻っているか」「共有物の棚が乱れていないか」といった項目を毎週金曜日の夕方など、時間を決めて振り返ることで、整頓の状態を“客観的に”見つめ直すことができます。
この習慣は、ちょうど1週間の締めくくりにぴったりのタイミングでもあり、翌週を気持ちよくスタートするための“整える時間”としても効果的です。しかも、項目が決まっていれば、短時間でも効率よくチェックできるので、手間もかかりません。自然と意識が整い、無理なく整理整頓を続けられる仕組みとなるでしょう。
デスク周りの整理整頓を見直す視点
デスク周りは、仕事の中で最も多くの時間を過ごす場所であり、集中力や作業効率に直接的な影響を与える空間です。だからこそ、机の上が整っているかどうかは、日々の業務の質を大きく左右します。とはいえ、気がつけば書類が山積みになり、文房具があちこちに散らばり、使わないものが無意識に居座ってしまっているということもあるのではないでしょうか。
整理整頓は、ただ片づけるという作業ではなく、「働きやすい環境をつくるための見直し作業」と捉えることで、デスク周りの整え方にも新しい視点が生まれます。このセクションでは、見慣れた空間を改めて見直すための考え方を、やわらかく丁寧にご紹介します。
デスクの上に置くべきもの・置かないもの
まずは、デスクの上に“何を置くか・何を置かないか”という判断から始めましょう。机の上は作業のためのスペースであり、余計なもので埋まってしまえば、肝心な仕事をするための空間が狭くなってしまいます。実際には、毎日使うものだけを最小限に置くというルールを自分の中で決めておくと、散らかりにくい環境をつくることができます。
たとえば、パソコン、メモ帳、ペン、電話、スケジュール帳──これらは日々頻繁に使うものであれば、目の前に置いておく意味があります。しかし、数日に一度しか使わない資料や参考書類は、引き出しや本棚など、別の場所に移動した方が効率的です。机の上に“今の自分に必要なものだけを残す”という意識を持つことで、作業に集中できる時間が自然と増えていきます。
また、見た目が整っていることは、それだけで気持ちを落ち着かせてくれる効果があります。スッキリとした空間は、目に入る情報が少なくなり、思考がスムーズに流れるようになります。余白のあるデスクは、それだけで仕事の質を高めてくれるのです。
引き出しや収納の中身を最適化する方法
「見えないからいいや」と後回しにされがちな引き出しの中も、整理整頓の大切なポイントです。むしろ、外から見えない部分こそ、使いやすさや作業スピードに直結しているといっても過言ではありません。引き出しや棚の中を見直すことで、よりスムーズに必要なものを取り出し、しまうことができるようになります。
まずは、引き出しの中に“用途別”で区切りをつけていきましょう。文房具は文房具、資料は資料、メモ用紙はメモ用紙といった具合に、カテゴリごとに分けて収納することで、何がどこにあるかがすぐに分かるようになります。小物類は仕切りトレーなどを活用して、定位置をつくってあげると、戻しやすくなりますし、視覚的にも整った印象になります。
収納の中に入れるものは、「いつか使うかもしれない」ではなく、「よく使う」「最近使った」ものを優先的に残していくことが大切です。手を伸ばす回数が多いものほど手前に置き、逆に使用頻度の低いものは奥へ移すという配置にすれば、使い勝手も大きく変わってきます。
仕事ごとにスペースを分けて管理する
1日の中で行う仕事は、種類によって必要な物や流れが異なります。たとえば、午前中は資料作成、午後は会議準備というように、タスクが変わるたびに使うものも変わってきます。そんなとき、机の上や引き出しの中がすべて混在していると、作業の切り替えに時間がかかったり、集中が途切れてしまったりします。
そこで有効なのが、仕事ごとにスペースを分けて管理するという方法です。たとえば、「右側は資料作成関連」「左側は会議準備用」といったように、用途によって置く場所をあらかじめ決めておくことで、仕事のスイッチを自然に切り替えることができるようになります。
また、引き出しの中も、上段は頻繁に使うタスク用、下段はストックや補助的な道具といった形で層を分けておくと、取り出す動作もスムーズになります。空間に役割を持たせることで、頭の中の整理にもつながり、無意識のうちに効率的な働き方ができるようになるのです。
デジタル整理整頓のすすめ

職場での整理整頓というと、まずはデスク周りや収納スペースといった「目に見える物理的な環境」が注目されがちですが、近年ではもう一つ見逃せない領域があります。それが、パソコンやクラウドサービスなどを活用した“デジタル空間”です。書類や備品が物理的に整理されていても、パソコンのデスクトップがファイルで溢れていたり、必要なデータがすぐに見つからなかったりすると、仕事の効率は思うように上がりません。
特にリモートワークやペーパーレス化が進んだ現代においては、デジタル整理整頓こそが仕事の質を左右する大きな要素になっています。このセクションでは、フォルダの整理、不要ファイルの削除、紙とデジタルの役割分担といったポイントを丁寧に紹介しながら、パソコンの中まで「整える」ことで、心地よく働ける環境を整えていく方法をお伝えします。
フォルダ整理のシンプルなルール
パソコンの中で「ファイルが見つからない」と感じる瞬間は、誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。フォルダの構成が複雑すぎたり、似たような名前のデータがいくつも存在していると、探す時間が増えてストレスを感じやすくなります。これを防ぐには、あらかじめ“整理のルール”を作っておくことが効果的です。
ルールは、複雑である必要はありません。たとえば、「年・月・プロジェクト名」の順にフォルダを作成し、階層を深くしすぎないように意識することで、目的のファイルに素早くたどり着けるようになります。毎回同じルールで名前を付け、同じフォルダ構成で管理していくことで、整理のストレスがぐっと減るのです。
また、フォルダ名は簡潔で一目で内容が分かるようにしておくと、他の人との共有もしやすくなります。「誰が見ても分かる整理」を意識することで、チーム内での連携や引き継ぎもスムーズになり、全体の作業効率が向上します。
不要ファイルやメールの定期削除
デジタルの世界では、「物があふれる」という実感が湧きにくいため、気づかないうちにデータが溜まりがちです。気づけばデスクトップに大量のファイルが並び、メールボックスも読み終えていないメッセージで埋め尽くされている…そんな状態では、いざというときに必要な情報を探すのにも一苦労です。
このような状況を防ぐためには、「定期的な削除」を習慣にすることが大切です。たとえば、週に一度だけでも「整理タイム」を設けて、使わないファイルをゴミ箱に移す、読了済みメールをアーカイブにする、といった簡単な作業をするだけでも、驚くほどデジタル環境が整っていきます。
また、「保留」「作業中」「完了」といったラベルをメールに付けて分類しておけば、処理状況が一目で分かるようになり、頭の中も整理されます。ファイルも同様に、仮置きフォルダと確定フォルダを使い分けることで、迷うことなく管理できます。削除する勇気は、「後回しにしていた作業を終えたような爽快感」を与えてくれます。
デジタルと紙の使い分けを見直す
整理整頓の本質は、“必要なものを、必要な場所に、必要なときに取り出せる状態にしておく”ことにあります。デジタルか紙かという形式の違いではなく、それぞれの特性を理解し、上手に使い分けることが大切です。
たとえば、急ぎのメモや思いついたアイデアなど、一時的な情報は紙のメモ帳に書いた方がすぐに確認できて便利です。一方で、後から参照する必要のある資料やチームで共有する情報は、デジタルで保存・管理しておく方が効率的です。このように、目的や使用頻度に応じて“使い分ける視点”を持つことが、無駄を省き、整理された業務フローを生み出します。
また、紙からデジタルへの移行には「スキャンして保管」「共有フォルダにアップロード」などの習慣を取り入れることで、段階的にデジタル整理整頓が進んでいきます。必要以上に完璧を目指す必要はありません。少しずつ整えることで、心も作業も軽くなっていきます。
整理整頓を継続するモチベーション維持法
整理整頓は「やって終わり」ではありません。むしろ一度きれいにしたあとの“維持”こそが本当の勝負と言えるでしょう。最初の数日は整った状態を保てても、時間が経つといつの間にか元通りになっていた…そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。片づけを続けるには、根性だけではなく、自然と続けたくなる“仕組み”と“気持ちの持ち方”が大切です。
このセクションでは、無理なく整理整頓を続けるための小さなモチベーションの保ち方や、仲間と一緒に取り組むアイデア、日々の達成感を感じる工夫などをやさしく丁寧にご紹介していきます。「頑張る」よりも「心地よく続ける」ことを目指して、気持ちのハードルを下げながら整理整頓の習慣を育てていきましょう。
ご褒美や可視化でやる気をキープ
人は、目に見える成果や変化があると、自然とやる気が湧いてくるものです。たとえば、「今日は机の上を3分間きれいにできた」という小さな行動でも、それを記録して目に見える形にすると、達成感や充実感が得られます。チェックリストやカレンダーに「整理整頓した日」を印として残しておくだけでも、継続への意欲が育ちます。
また、自分にちょっとした“ご褒美”を設定するのも効果的です。「1週間続けられたら好きなスイーツを買う」「月末まで整った状態を維持できたら文房具を新調する」など、モチベーションを上げるきっかけになる仕組みを自分の性格に合わせて取り入れてみましょう。がんばりすぎず、楽しみながら続けることが、長く続ける最大のコツになります。
仲間と一緒に取り組む仕組みづくり
整理整頓は、ひとりでやるよりも、誰かと一緒に取り組むことで習慣化しやすくなります。職場では、同僚やチームのメンバーと「一緒にきれいにしてみよう」と声をかけ合うことで、互いに励まし合いながら前向きに続けられるようになります。まわりの人も取り組んでいる姿を見れば、自分もやってみようという気持ちが自然と湧いてくるものです。
たとえば、毎週金曜日の業務終了前に「みんなで5分片づけタイム」を設けるだけでも、整理整頓への意識は大きく変わります。また、きれいになった様子を写真に撮って共有したり、「整ってるね!」と声をかけ合ったりすることで、小さな達成感をチームで味わうことができるようになります。
こうした“仲間との関わり”を通じて続けることは、職場全体の雰囲気を明るくし、整理整頓を単なる作業ではなく、気持ちのよい文化として定着させることにもつながります。
小さな成功体験の積み重ねが自信に
整理整頓を続けるうえで大切なのは、「全部完璧にしよう」と思いすぎないことです。たとえば、デスクの上が毎日完璧に片づいていなくても、引き出しの中が少しずつ使いやすくなってきたり、週1回の整理が習慣になっていたりするなら、それは立派な進歩です。
大事なのは、自分が取り組んだことを“成功体験”として認識すること。最初は気づかなくても、少しずつ積み重ねていくうちに、「前より資料を探す時間が減った」「仕事のリズムが整ってきた」といったポジティブな変化を感じられるようになります。
そしてその変化に気づいたとき、「自分でもできた」という自信が生まれます。自信は新しい習慣を育てる大きなエネルギーです。完璧であることよりも、続けられること、そして小さな変化を喜べることが、整理整頓を心地よく習慣にしていく第一歩となるでしょう。
整理整頓が職場全体にもたらす効果

ここまで「捨てる・決める・もどす」を中心に、整理整頓を個人の習慣として取り入れる方法をお伝えしてきましたが、実はその積み重ねは、個人の効率を高めるだけでなく、職場全体の雰囲気や連携にも良い影響をもたらします。一人ひとりの行動が少しずつ整っていくことで、結果としてチーム全体の生産性や信頼感が高まり、より働きやすい空間へと育っていきます。
このセクションでは、整理整頓がどのように職場の空気を変え、チーム全体にプラスの作用を与えるのかを、「業務効率」「ストレスの軽減」「人へのやさしさ」という視点から丁寧に見つめていきます。自分のためだけではなく、まわりの人のためにも整える。そんな気持ちを持つことが、よりよい職場づくりにつながっていきます。
業務効率とチームの連携向上
物の場所が明確になっていて、誰が見ても使い方が分かる環境は、チームで仕事をするうえで大きな武器になります。たとえば、会議用の備品がいつも同じ場所にあれば、担当者以外でも準備や片づけがスムーズに行えますし、業務の引き継ぎやサポートも滞りなく進めることができます。
また、必要な資料を探すのに時間がかからなかったり、どこに何があるかを説明しなくても伝わるようになれば、それだけで業務全体の流れが整っていきます。整理整頓によって生まれる“時間のゆとり”や“説明の手間の削減”は、チーム全体の業務効率を着実に底上げしてくれます。
さらに、整った空間は思考の切り替えや作業の集中を助けるため、自然と一人ひとりのパフォーマンスも向上しやすくなります。こうした効果が重なり合うことで、チーム全体が“助け合える状態”になり、より柔軟で生産性の高い働き方が可能になっていくのです。
ストレス軽減とメンタルヘルスへの好影響
散らかった職場では、「どこに何があるのか分からない」「誰が使ったのか確認しなければならない」といった小さなストレスが日常的に発生しがちです。こうしたストレスは、積み重なると知らず知らずのうちに疲労や苛立ちの原因となり、仕事への集中力やモチベーションを下げてしまうことがあります。
一方、整理された職場では、必要な物がすぐに見つかり、使ったものは誰でも簡単に元の場所に戻すことができるため、無駄な心配や確認が減り、安心して仕事に取り組めるようになります。また、スッキリとした視界は精神的にも安らぎをもたらし、自然と心が落ち着いた状態になりやすくなります。
職場の環境が整っていることは、単なる利便性だけでなく、メンタルヘルスの面でも大きな支えになります。疲れを感じたときに、整った机を見るだけで少し心がほっとした、という体験は、きっと多くの人が共有できるはずです。
新人や来客にもやさしい環境づくり
整理整頓された職場は、その場所に初めて訪れる人にとっても、安心感を与えるものです。たとえば、新しく入社した社員が最初に目にする職場が、清潔で整った環境であれば、「ここはきちんとした会社だ」「安心して働けそう」と感じることでしょう。また、物の配置が分かりやすく整っていれば、どこに何があるかをすぐに覚えられ、業務へのスムーズな適応にもつながります。
さらに、外部からの来客に対しても、整っている職場は良い印象を与えます。打ち合わせスペースが清潔で、資料や備品がきちんと管理されているだけで、「丁寧な対応が期待できる」「安心して任せられる」と感じてもらえる可能性が高くなります。第一印象は想像以上に大切であり、その一端を担っているのが職場の環境整備なのです。
こうしたやさしさや気づかいが表れる空間は、周囲との関係性をスムーズにし、社内外問わず円滑なコミュニケーションを育む土壌になります。誰もが心地よく過ごせる場を目指すためにも、整理整頓の習慣はとても価値のある取り組みです。
失敗しないために気をつけたいポイント
整理整頓に取り組み始めたとき、多くの人が最初はやる気に満ち、机の上もスッキリと片づいて満足感を得られるものです。しかし、その気持ちが長続きしないこともまたよくあることです。「やろうと思っても続かない」「片づけたのにすぐに散らかってしまった」──こうした悩みが出てくると、整理整頓そのものが負担のように感じられてしまいます。
けれども、その多くは“やり方”ではなく“考え方”に少し工夫を加えるだけで解消できるものです。このセクションでは、整理整頓を始める際によくあるつまずきポイントと、その乗り越え方をやわらかく、かつ実践しやすい視点でご紹介していきます。失敗を恐れず、安心して取り組めるようになるヒントをお伝えします。
完璧主義にならないための心構え
整理整頓を始めると、「全部を完璧にきれいにしなければ」と思ってしまうことがあります。たとえば、「引き出しの中も全部分類しなきゃ」「デスクの上は常に何も置かないようにしたい」と意気込むあまり、少しでも乱れると「もうダメだ」と感じてやめてしまう、ということもあります。
でも実際には、整理整頓は“少しずつ整えていくもの”であり、完璧を目指す必要はありません。たとえば、今日は机の右側だけ、明日は引き出しの上段だけ、といったように、無理なく続けられる範囲で取り組めば良いのです。
少しだけ整っただけでも、その変化はしっかりと実感できますし、「これだけできた」と感じることで、心も前向きになります。完璧よりも継続を意識し、自分が気持ちよく過ごせる状態を目指していくことが、何より大切です。
一気にやろうとせず段階的に進めるコツ
「整理整頓するぞ!」と決めたときに、あれもこれも一気にやろうとして途中で疲れてしまう…そんな経験はありませんか?最初からあらゆる場所を完璧に片づけようとすると、気持ちばかりが先走り、途中で集中力が切れてしまったり、逆に散らかってしまったりすることもあります。
だからこそ、大切なのは“段階的に進める”という考え方です。まずは目につく場所、よく使うスペースから手をつけて、「ひとつ整えるたびにひと息入れる」というペースで進めていきましょう。
たとえば、1週間ごとにテーマを決めて進める方法も効果的です。今週は書類、来週は文房具、その次はパソコンのフォルダ整理…といったように、少しずつ範囲を広げていけば、無理なく全体が整っていきます。ゴールは焦らず、日々の中でじっくり育てていくものとして捉えると、気持ちも軽やかになります。
人によって考え方が違うことを受け入れる
整理整頓には、正解が一つだけあるわけではありません。人によって「使いやすい」と感じる配置や、「きれい」と思う基準は異なります。職場では、共有のスペースを誰もが使うため、「自分にとってベストなやり方」が、必ずしも他の人にとっても最適とは限らないということを、まずは理解しておくことが大切です。
たとえば、自分が「こう置くのが使いやすい」と思っても、他の人にとっては取り出しにくい配置であるかもしれません。そうしたときに、「なんで戻してくれないの?」と感じるよりも、「それぞれにやりやすさがあるんだ」と受け止め、話し合いの機会を持つことで、お互いの理解が深まります。
誰かを変えるのではなく、まずは自分が柔軟であること。それが、職場全体に心地よい整理整頓の文化を育てる第一歩になります。小さなすれ違いを対話で解消しながら、みんなが気持ちよく働ける空間を一緒につくっていきましょう。
まとめ
「仕事の生産性を高める整理整頓術」というテーマでお届けしてきた本記事では、「捨てる・決める・もどす」という3つの基本的なステップを中心に、職場の環境を整えるための具体的な方法や、その背景にある考え方を丁寧に掘り下げてきました。
最初の一歩となる「捨てる」では、本当に必要なものを見極めることで、自分にとって大切なスペースと時間を取り戻すことができます。次に「決める」によって物の定位置が定まり、迷いのない行動が可能になります。そして最後の「もどす」を習慣化することで、整理整頓された状態が無理なく続いていくようになります。
この3つの流れは、ただ物を片づけるための手段ではなく、毎日の仕事に向き合う姿勢や、周囲との関係を大切にするための意識を育てるものでもあります。整理整頓された職場は、視界がスッキリするだけでなく、心に余白をつくり、集中力や効率を高める支えとなってくれるのです。
さらに、整理整頓は個人だけでなく、職場全体の空気にも影響を与えます。整った環境は連携をスムーズにし、ストレスを軽減し、新人や来客にとっても安心できる場所を提供します。そうして生まれた信頼や快適さが、職場全体のパフォーマンスを静かに後押ししてくれるのです。
もちろん、完璧を目指す必要はありません。むしろ「ちょっとだけ整えてみる」という小さな一歩を大切にしながら、自分にとって無理のないやり方を見つけていくことが、整理整頓を自然に続けていく秘訣です。ご褒美を決めたり、仲間と声をかけ合ったり、小さな達成を喜んだり──そんな日々の積み重ねが、気づけば心地よい習慣となって、自分自身と職場を支えてくれるでしょう。
もしこの記事を読みながら、「ちょっとデスクを整えてみようかな」と思えたのなら、そこがすでに素晴らしいスタート地点です。ほんの少しの意識が、未来の働き方を静かに変えていきます。
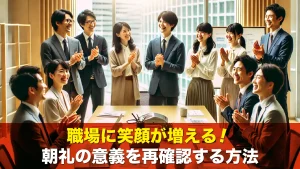


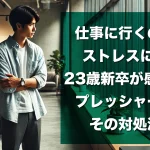



![保健師のお仕事とは?仕事内容・やりがい・スキル・経験、どんな資格がいかせるの?[職種図鑑]](https://hatachie.com/wp-content/uploads/2024/11/job-category-table0004-150x150.webp)
![医療機器販売会社のお仕事とは?仕事内容・やりがい・スキル・経験、どんな資格がいかせるの?[職種図鑑]](https://hatachie.com/wp-content/uploads/2024/11/job-category-table0014-150x150.webp)


