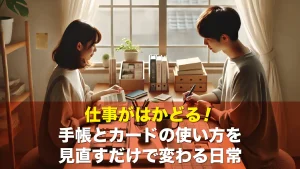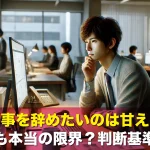職場で電話が鳴ったとき、「自分が出ても大丈夫かな」「うまく対応できるだろうか」と不安に感じたことはありませんか?顔の見えない相手とのやり取りは、緊張を伴うことが多く、特に新人や職場に慣れない方にとっては、電話を取ること自体がひとつのハードルに感じられることもあるかもしれません。
ですが、電話対応は「やっていくうちに慣れる」というだけではなく、基本の流れやマナーを知っておくことで、不安をぐっと軽減することができる業務でもあります。ちょっとした準備や言葉遣いのコツ、状況ごとの受け答えの工夫を知っておくことで、職場での電話対応はもっと安心できるものになっていきます。
この記事では、「電話をかけるとき」「受けるとき」の基本的なマナーから、つまずきやすい場面での改善方法、不安を和らげる考え方、そして電話対応を通じて得られる気づきや自信について、やさしく丁寧に解説しています。電話に慣れていない方にも寄り添いながら、一つひとつの場面を想定し、すぐに役立つポイントを盛り込んでいますので、「電話は苦手かも」と思っている方にも安心して読み進めていただけます。
日々の電話応対を「こなす業務」ではなく、「自分を育ててくれる経験」として受け止めてみると、不思議とやり取りの中に気づきが増え、会話の一言一言が少しずつ変わってくるものです。電話が苦手な方も、これから少しずつ上達したいと考えている方も、ぜひこの機会に、電話対応の基本から実践までをゆっくりと学んでみませんか?
この記事の目次(タップでジャンプ)
職場での電話対応が求められる理由とその役割

職場では、日々さまざまなコミュニケーションが行われています。メールやチャットツールが普及している現代においても、電話は依然として重要な連絡手段のひとつです。とくにビジネスの現場では、緊急性が高い内容や、文章では伝わりづらい感情やニュアンスを含む場合など、声のトーンや間の取り方を通じてより的確に情報を届けることができる電話の役割は決して小さくありません。
電話対応は、職場の中でも早い段階から任されることの多い業務です。入社して間もない新人であっても、電話が鳴ったら対応しなければならないという状況は日常的にあり、「まだ慣れていないから」といった言い訳が通用しにくいのも特徴です。だからこそ、基本をしっかりと押さえたうえで、電話を通じて丁寧かつ正確なコミュニケーションが取れるようになることが、職場で信頼を得るための第一歩となります。ここでは、電話対応がなぜ求められるのか、どのような役割を果たしているのかについて、丁寧に考えていきます。
社会人としての基本マナーに含まれる電話対応
社会人として働く以上、まず身につけておきたいのが「マナー」です。そしてその中には、職場の内外を問わず多くの場面で必要となる「電話対応」も含まれています。たとえば、電話に出た際に自分の会社名と名前を名乗り、用件を正確に聞き取って対応する流れは、ビジネスの世界では当然のものとされています。こうした動作や受け答えの積み重ねが、社会人としての信頼感や安心感を相手に与えることにつながります。
電話応対は、ただ言葉をやりとりするだけではありません。相手の話を丁寧に聞き取る姿勢、わからないことをそのままにせず確認する意欲、話す声の明るさやトーン、言葉選びの丁寧さなど、さまざまな要素が含まれています。これらを通じて、目の前にいない相手に対しても礼儀正しく、思いやりを持った対応ができる人としての印象が自然と形成されていきます。
また、電話対応は職場内での評価にも影響を与えます。電話応対がしっかりできている人は、上司や先輩から「任せても安心だ」と信頼されやすくなり、業務の幅も広がりやすくなります。その反面、基本的なマナーが身についていない場合には、「まだ一人前とはいえないな」と思われてしまう可能性もあります。このように、電話対応は社会人としての基礎を築くうえで欠かせない要素のひとつなのです。
電話を通じて相手に伝わる会社や自身の印象
電話は、自分自身だけでなく、所属する会社全体の印象にも直結するという側面を持っています。たとえば、明るくはきはきとした対応ができると、「この会社は対応が良い」「丁寧な人が多い」といったポジティブな印象を与えることができます。その逆に、声が小さかったり、聞き取りづらかったり、話し方に自信がなさそうだったりすると、「この会社は少し頼りないかも」と感じさせてしまうかもしれません。
特に、電話は対面とは違い、視覚的な情報がないぶん、声や言葉のみによって印象が形成されます。だからこそ、話し方ひとつ、対応の仕方ひとつが、相手の中に強く残ることもあるのです。その意味で、電話応対は「会社の顔」であるともいえます。新人であっても、電話に出たその瞬間から会社の代表として話しているのだという自覚を持つことが大切です。
さらに、電話を受けたときに適切な対応ができると、それだけで「しっかりしているな」「教育が行き届いているな」と感じてもらえることもあります。このように、電話を通じて相手に与える印象は、個人の評価にとどまらず、企業全体のイメージにも深く関わっているという点を忘れてはいけません。
業務円滑化のために欠かせないコミュニケーション手段
電話は、職場での業務を円滑に進めるための重要なツールです。たとえば、社内の他部署との連絡や、急ぎの依頼事項、トラブルの共有、商談の調整など、さまざまな場面で電話は活躍します。メールやチャットで連絡を取り合うこともできますが、それらはどうしても「相手が読むまで待たなければならない」「文章のニュアンスが伝わりにくい」といった点で不便さを感じることもあるのです。
一方、電話であれば、相手とすぐに話すことができ、内容を確認しながら進められるため、認識のズレが起きにくくなります。また、やりとりがスムーズに進めば、その場で判断を仰いだり、次の行動に移すための合意を得たりすることも可能になります。つまり、電話は業務効率を高めるために必要な手段であり、正確でスピーディーな対応が求められるビジネスの現場において、なくてはならない存在といえるのです。
さらに、電話によるやり取りを通じて、相手との信頼関係が築かれていくという面もあります。人は、直接話をして、声のトーンやリアクションを感じながらやりとりをすることで、相手の人柄や気配りに気づくことができます。その積み重ねが「またこの人にお願いしたい」「この会社と取引を続けたい」といった関係づくりにもつながるのです。
このように、電話は単なる連絡手段ではなく、信頼を生み、仕事を前に進めるための大切なコミュニケーション手段なのです。そしてその第一歩を担うのが「電話のかけ方」と「受け方」なのです。
職場での電話のかけ方を身につける基本ステップ
職場で電話をかける機会は、新人でも想像以上に多くあります。たとえば、外部の取引先に資料の送付を確認するための連絡をしたり、先輩や上司に代わって来客対応の確認をしたりするなど、電話を通じて円滑な業務連携が求められる場面は日常的に存在しています。そのため、「電話をかける」という行動に対して、緊張や不安を抱くことは決して珍しいことではありません。
とはいえ、電話をかけること自体は特別なスキルを持つ人だけに与えられるものではなく、正しい流れとマナーを理解して実践すれば、誰でも安心して対応できるようになります。このセクションでは、職場での電話のかけ方を基礎からわかりやすく丁寧に解説していきます。
かける前の準備と確認すべきポイント
電話をかける際、ただ受話器を取って番号を押せばよいというわけではありません。ビジネスの現場では、あらかじめしっかりと準備をしてから電話をかけることが基本とされています。まず大切なのは、相手の部署名や担当者名、連絡先を正確に把握しておくことです。事前に名前を確認しておくことで、電話口で「誰宛に」かけているかを明確に伝えることができ、相手にもスムーズに対応してもらいやすくなります。
また、要件を簡潔にまとめたメモを手元に準備しておくと、電話中に焦ることなく話を進めることができます。伝えるべき内容や確認したい事項を事前に書き出しておくことで、話が前後したり、重要な情報を漏らしたりすることを防げます。さらに、相手が不在の場合の対応策(誰に伝言を残すか、いつ改めて連絡を入れるかなど)も想定しておくと、より落ち着いて電話をかけられるようになります。
電話をかける時間帯にも配慮が必要です。始業直後や昼休み直前、終業直前などは相手が忙しいことが多いため、なるべく避けるのがマナーとされています。社内外問わず、相手の状況に配慮した時間に電話をかけることで、「気遣いができる人だな」という印象を持ってもらいやすくなります。
電話のかけ始めに気をつけたい言葉とトーン
電話をかけて相手が出たら、最初に会社名と自分の名前を名乗るのが基本です。その際の声のトーンや話し方には、特に注意を払う必要があります。相手に聞き取りやすく、かつ明るく丁寧な印象を与えるためには、口を大きく開けてはっきりと発音すること、語尾を丁寧に伸ばさず言い切ることを意識するとよいでしょう。
「お世話になっております。〇〇株式会社の△△と申します」という言葉は、ビジネス電話でよく使われるフレーズです。この一言を自然に使えるようになると、電話対応全体が落ち着いた印象になります。また、相手が名乗るのを待ってから話し始めることも大切です。焦って要件に入るのではなく、「〇〇様はいらっしゃいますでしょうか」や「担当の方におつなぎいただけますか」といった丁寧な表現を用いることで、礼儀正しい印象を残すことができます。
さらに、電話をかけるときは「自分が話す側」であることを意識することも重要です。相手が何を求めているか、どう聞いたらわかりやすいかを考えながら話すことで、ただ情報を伝えるだけでなく、配慮ある対応ができるようになります。話すスピードはややゆっくりめを意識すると、相手が理解しやすくなり、全体の印象も落ち着いたものになります。
要件を明確に伝えるための話し方と配慮
電話の中で最も大切なのが、用件をわかりやすく、丁寧に伝えるということです。相手に内容をしっかりと伝えるためには、結論から話すことを意識するのが基本です。たとえば、「〇〇の件でご連絡差し上げました」というように、なぜ電話をかけたのかを最初に述べることで、相手も話の流れを理解しやすくなります。
そのうえで、必要な情報を順序立てて説明するようにすると、スムーズにやりとりが進みます。たとえば、資料の送付について確認する場合は、「先ほどメールでお送りした資料について、内容をご確認いただけたかお伺いしたくお電話いたしました」といった具合に、背景と目的を一緒に伝えると、より丁寧で伝わりやすい印象になります。
会話の中では、相手の反応をしっかり聞き取りながら、相槌を打つことも忘れてはいけません。「はい、承知しました」「ありがとうございます」といった言葉を適度に挟むことで、電話のやりとりにリズムが生まれ、安心感を与えることができます。
最後に、電話を切る際には必ずお礼の言葉を述べ、「失礼いたします」と一礼の気持ちを込めた一言で締めくくることが望ましいです。こうした一連の流れが自然にできるようになることで、電話対応に対する苦手意識も薄れ、職場内でも自信を持ってコミュニケーションが取れるようになるでしょう。
職場での電話の受け方で意識したい対応マナー

電話は、職場で日々鳴り響くもののひとつであり、出るタイミングや受け答えの仕方次第で、相手に与える印象は大きく変わります。特に受ける側は「対応の入口」となるため、最初の一言で会社全体の雰囲気や対応品質を感じ取られてしまう場面も少なくありません。そのため、電話を受けるときには、単に「出る」だけではなく、どう応対するかを意識する必要があります。
たとえ新人であっても、電話が鳴ればまず率先して対応する姿勢が大切ですし、その上で丁寧で的確な受け答えができれば、周囲からの信頼にもつながります。このセクションでは、職場で電話を受けるときに大切にしたいマナーについて、基本から具体的にご紹介していきます。
最初の一言で印象を左右する受け方とは
電話を受けた際の第一声は、相手にとってその会社の「第一印象」そのものです。そのため、最初の一言には特に注意を払い、明るくはっきりとした声で受け答えをすることが求められます。たとえば、「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社でございます」というように、感謝の気持ちを込めて丁寧に名乗ることで、相手は安心感を覚え、スムーズな会話のスタートが切れます。
このときの声のトーンも重要です。声が小さすぎると聞き取りづらくなり、相手を不安にさせてしまいますし、逆に大きすぎても威圧感を与えてしまうことがあります。適度な音量で、はっきりとした発音を心がけましょう。また、電話に出るまでの時間も気を配るポイントです。一般的には、電話が鳴ってから3コール以内に出ることが望ましいとされており、それより遅れると相手に不安や不信感を与える可能性が出てきます。
最初の一言を丁寧に伝えるだけで、相手の心は自然とほぐれ、良好なコミュニケーションが生まれやすくなります。だからこそ、電話の受け方はただの習慣ではなく、相手との信頼を築くための大切なきっかけとして、大切にするべき場面なのです。
聞き取りやすさとメモの取り方のポイント
電話では、相手の顔が見えないぶん、話の内容を正確に把握することが求められます。とくに、話すスピードが速かったり、聞き慣れない専門用語が出てきたりする場面では、しっかりと聞き取る努力が欠かせません。聞き漏らしを防ぐためには、電話に出る際に紙とペン、またはメモアプリなどを手元に準備しておき、必要な内容をすぐに書き留められる状態にしておくことが基本です。
相手の名前や会社名、電話番号などの連絡先情報、要件や伝言の内容は、特に注意して正確に記録する必要があります。間違った情報を社内で伝えてしまうと、相手に迷惑をかけたり、社内での信用を損なったりする恐れがあるため、一語一句を丁寧に確認する姿勢が大切です。もし聞き取れなかった場合や、曖昧な部分があった場合には、「恐れ入りますが、もう一度お名前をお願いできますか?」などと、丁寧に聞き直すことをためらわないことが大切です。
また、話の途中で復唱を入れることも有効です。たとえば「〇月〇日の午前10時にご来社ですね。かしこまりました」といったように、相手の発言を確認しながら進めることで、双方の理解を一致させることができます。このようなやりとりを丁寧に行うことで、相手に対しても誠実な対応をしている印象を与えることができ、信頼関係の構築につながります。
取り次ぎや折り返し対応の丁寧な伝え方
電話を受けた際、自分が用件に直接対応できない場合は、担当者への取り次ぎや折り返しの対応が必要になります。このときにも、丁寧さや正確さが求められるため、焦らず落ち着いて対応することが大切です。
まず、担当者が電話に出られない場合には、「申し訳ございません。ただいま〇〇は席を外しております」といった表現で状況を伝え、その上で「戻り次第、折り返しご連絡させていただいてもよろしいでしょうか」と確認を取ります。その際、相手の名前、連絡先、用件、折り返しの希望時間などを漏れなく確認し、しっかりとメモに残しておくことが大切です。
もし社内の担当者にすぐに取り次げる場合には、「少々お待ちくださいませ。ただいまおつなぎいたします」と伝え、保留にしてから社内の内線で呼び出します。その際も、相手の名前や会社名、要件を簡潔に伝えると、担当者も状況を把握しやすくなります。
また、折り返しの連絡を依頼する場合には、メモを残すだけでなく、口頭やチャットなどで確実に担当者に伝える習慣をつけておくと、情報の伝達漏れを防げます。自分が直接応対できない場面でも、丁寧な言葉づかいや対応によって、相手に誠実な印象を残すことができ、会社全体の信頼感にもつながっていきます。
新人がやってしまいがちな電話対応のNG例と改善策
職場で電話応対を経験する中で、多くの新人がつまずきやすいポイントがあります。それは、知識やマナーが十分でないことによるミスだけではなく、緊張や焦りから起こる思わぬ対応の乱れでもあります。特に、入社したばかりの頃は「どうすればいいのか分からない」「間違ったらどうしよう」という不安が大きく、冷静に対応することが難しく感じられることも少なくありません。
しかし、失敗を恐れるあまり電話を避けてしまうと、なかなか成長の機会が得られず、結果としてさらに苦手意識が強まってしまう可能性もあります。ここでは、新人が陥りがちな電話対応のNG例を取り上げながら、その具体的な改善策を丁寧に見ていきます。うまくいかなかった経験を次につなげることで、確実に電話対応の力を高めることができます。
曖昧な返答で相手を不安にさせてしまうケース
電話対応においてよくあるミスのひとつが、曖昧な返答をしてしまうことです。たとえば、相手の質問に対して「多分そうだと思います」「そうかもしれません」といったあいまいな言い回しを使ってしまうと、相手は「本当にこの情報で合っているのか?」と不安になり、会社全体の信頼感にも影響を与えかねません。
新人の立場では、分からないことに直面したときに、つい適当な返事をしてしまうことがあります。「分からない」と言うことが失礼にあたるのではと感じてしまい、無理に答えてしまうのです。しかし、実際には、間違った情報を伝えることの方が相手にとっては困るものであり、正しく対応するには、「少々確認いたしますので、お待ちいただけますか?」といった表現で、分からないことを正直に伝えた上で、先輩や上司に確認するのが最も丁寧な方法です。
相手にとっては、正確で丁寧な情報提供の方が何よりも大切です。「今は分からないけれど、きちんと確認して伝える」という姿勢を見せることで、誠実な印象を残すことができます。たとえ即答できなかったとしても、誠実に対応する姿勢は、信頼感につながるのです。
声が小さい、早口など聞き取りづらさの改善
電話応対のときに多いもうひとつの悩みが、「声が小さい」「早口で聞き取りづらい」といった点です。特に緊張していると、どうしても声のトーンが沈んでしまったり、言葉が早くなったりしてしまいがちです。自分ではしっかり話しているつもりでも、相手には聞こえていなかったということは、意外と多くあります。
このような場合には、まず自分の話し方のクセを客観的に認識することが大切です。たとえば、周囲の人に「今の話し方どうだった?」と聞いてみたり、自分の声を録音して確認してみると、「思っていたよりも早口だな」「語尾が小さくて聞き取りづらいな」といった気づきが得られます。
話すスピードについては、少し意識してゆっくり話すことを心がけると、それだけで相手には丁寧な印象を与えることができます。また、はっきりとした声で話すためには、口をしっかり開けて話すことも有効です。無意識のうちに小さな声になってしまう人は、電話に出る直前に軽く深呼吸をしてから対応することで、声のトーンも安定しやすくなります。
一番大切なのは、「相手がどう聞こえているか」を常に意識することです。聞き取りやすく話すことは、単に伝達の手段としてだけでなく、相手への気遣いのあらわれでもあるのです。
メモを取らないことで起きるミスと対処方法
新人にとってありがちな失敗として、「電話中にメモを取らない」ことで情報があいまいになり、あとから困ってしまうというケースがあります。話の途中で覚えておこうとしても、別の要件が入ってくるとすぐに忘れてしまったり、取り次ぐべき相手の名前を思い出せなかったりして、焦ってしまうことがあります。
こうした事態を防ぐためには、電話を取るときには必ずメモを取る体制を整えておくことが基本です。机の上には常に筆記用具とメモ帳を用意し、すぐに書き留められるようにしておきましょう。話の最中に記録することが難しい場合は、電話を切った直後に簡潔に内容をまとめるだけでも、あとで確認する際に役立ちます。
また、メモを取る習慣が身についてくると、聞き取った内容をその場で整理しながら受け答えができるようになります。さらに、復唱や確認をしながらメモを取ることで、相手にも「しっかり話を聞いてくれている」という安心感を与えることができます。
電話応対の精度は、こうした地道な積み重ねによって着実に高まっていきます。最初はうまくいかないことがあっても、改善の姿勢を持って少しずつ慣れていくことで、確実に自信につながっていくのです。
電話対応がうまくなるための練習と心構え

電話応対に自信を持てるようになるためには、マナーや言葉遣いを知識として覚えるだけでは不十分です。実際の対応場面を想定しながら、繰り返し練習を積み重ねること、そして「うまくやらなければ」と気負いすぎず、失敗も含めて成長の糧と考える柔軟な心構えを持つことがとても大切です。職場では予期しないタイミングで電話が鳴ることも多く、その都度、慌てず落ち着いて対応するには、日ごろの準備がものを言います。
また、最初のうちは完璧を求めすぎず、少しずつ「できること」を増やしていく意識で取り組むことが、自信を育てるうえで重要なステップとなります。このセクションでは、電話対応のスキルを向上させるための具体的な練習方法と、日常のなかで意識したい前向きな心構えについて、実践的に解説していきます。
ロールプレイで実践力を高める方法
実際の電話対応に近い状況を再現して練習できる方法として、ロールプレイはとても効果的です。たとえば、先輩や同僚に協力してもらい、役割を分けて「かける側」「受ける側」となって模擬的な電話対応を繰り返すことで、理論ではなかなか身につかないリアルな会話の流れや対応の感覚を養うことができます。
ロールプレイでは、あらかじめシナリオを用意しておくと練習がしやすくなります。たとえば「資料の到着確認をする電話」「担当者不在時の取り次ぎ対応」「クレームを受ける場面」など、現実にありそうなシチュエーションを想定することで、より実践的な練習ができます。
また、ロールプレイ後に振り返りの時間を設けて、「この言い回しは分かりづらかった」「声のトーンが聞き取りづらかった」といったフィードバックをもらうことで、自分では気づきにくいクセや改善点を見つけることができます。反復することで「体にしみこむ」感覚が育ち、実際の場面でも緊張せずに対応できるようになっていきます。
このような練習は、回数を重ねるごとに自然な話し方やタイミングの取り方が身につき、電話対応に対する抵抗感が薄れていくことを実感できるでしょう。
先輩や上司からのフィードバックを活用する
職場には、すでに多くの電話応対を経験してきた先輩や上司がいます。自分一人では気づけない細かな表現の工夫や、相手の気持ちを汲んだ言葉遣いなど、経験を通じて蓄積されたノウハウがたくさんあります。だからこそ、そういった方々からのアドバイスを素直に受け取り、自分の成長に生かす姿勢がとても大切です。
電話対応を終えたあと、「今の対応、聞いててどうでしたか?」といったように自分からフィードバックを求めると、相手も具体的な指摘をしてくれることが多くあります。また、他の人の電話対応をそばで聞いて「この言い方、すごく丁寧だな」と感じたことがあれば、それを真似してみるのも良い方法です。先輩たちの実際のやりとりには、多くのヒントが詰まっているのです。
フィードバックを受けた際は、すぐにその場で改善点を意識し、次の電話で実践してみることが大切です。少しずつでも修正を繰り返すことで、自分なりのスタイルが確立され、自然と「この人に任せておけば安心」と思ってもらえるようになります。
そして何より、誰かに学びを求める姿勢は、職場内での信頼構築にもつながります。自分の成長のために努力する姿を周囲が見ていれば、応援してくれる人も増え、結果として電話対応だけでなく、日々の仕事全体がうまくまわるようになっていくはずです。
緊張しないための心の整え方とリラックス法
電話が鳴るたびに緊張してしまうというのは、多くの新人が抱える悩みです。しかし、緊張を完全にゼロにすることは難しいものの、その感情をうまくコントロールすることは可能です。まず大切なのは、「多少の緊張は悪いことではない」と受け入れる姿勢を持つことです。緊張しているからこそ集中力が高まり、丁寧な対応ができるという側面もあります。
心を落ち着ける方法としては、深くゆっくりとした呼吸を意識することが効果的です。電話を取る前に一呼吸おき、肩の力を抜いて「大丈夫、自分は準備してきた」と心の中で繰り返すことで、不安感を軽減することができます。
また、あらかじめよく使うフレーズを声に出して練習しておくと、本番でも自然に言葉が出てきやすくなり、緊張が和らぎます。例えば、「お電話ありがとうございます」「少々お待ちくださいませ」といった定型文を口になじませておくことで、スムーズな第一声が出やすくなります。
さらに、うまくいった対応を記録に残すこともおすすめです。「今日はきちんと相手の名前を聞き返せた」「落ち着いて電話を取り次げた」といった小さな成功体験を振り返ることで、少しずつ自信が蓄積されていきます。緊張は、経験を重ねることで徐々に小さくなっていきます。その過程を焦らず、自分のペースで歩んでいくことが、電話対応の上達につながるのです。
場面別に見る職場での電話対応の実践例
電話対応の基本を学び、繰り返し練習を重ねたとしても、実際の業務では想定外の出来事が起こることもあります。職場での電話応対は常に「正解がひとつではない」状況があるため、その場その場での判断力や、状況に応じた対応力が問われる場面も少なくありません。
そのため、基本的なマナーに加えて、さまざまなシチュエーションを想定しておくことが、より安心して電話対応に臨むための準備になります。ここでは、職場でよくある代表的な3つの場面を取り上げ、それぞれでどのように対応するのが望ましいかを、実際のイメージとともに解説していきます。自分が実際に電話を受けたときに役立てられるよう、ひとつひとつ丁寧に考えてみましょう。
お客様からのクレーム電話に出たときの対応
職場では、時にお客様からクレームや不満の声が寄せられることがあります。電話口でそのような内容を受け取るのは、特に新人にとって大きなプレッシャーに感じるかもしれません。しかし、こうした場面でも冷静に対応することができれば、信頼を回復し、むしろプラスの印象を与えることも可能です。
まず大切なのは、相手の言葉に耳を傾け、途中でさえぎらずにしっかりと最後まで話を聞くことです。感情が高ぶっている相手に対しては、反論せず、まずは共感を示す姿勢が求められます。「ご不快なお気持ちにさせてしまい、申し訳ございません」といった言葉を伝えることで、相手の気持ちが少し落ち着きやすくなります。
自分がすぐに対応できない内容であれば、「担当部署にて詳細を確認し、早急にご連絡させていただきます」といったように、社内での対応につなげるための案内を丁寧に行うことが重要です。その際、伝言の内容は正確にメモし、誰がどのようなことで困っているのかを具体的に記録しておくことで、社内の担当者もスムーズに対応しやすくなります。
クレーム対応は、冷静さと誠実さが何より大切です。緊張してうまく話せなかったとしても、真摯に向き合う姿勢は必ず伝わります。新人であるからこそ、「丁寧に対応しよう」という心を持ち続けることが、信頼につながる第一歩になるのです。
上司不在時の連絡の受け方と伝言の残し方
電話がかかってきたとき、対応すべき上司や担当者が不在ということもよくあります。そんなときには、自分が一時的な窓口となり、連絡内容をきちんと受け取り、正確に伝えることが求められます。
まず、相手に対しては「〇〇はあいにく席を外しております」と丁寧に状況を説明し、「ご用件をお伺いしてもよろしいでしょうか」と相手の意向を確認します。メモを取る際には、相手の名前、会社名、連絡先、伝言の内容、そして可能であれば折り返しの希望時間なども聞いておくと、後の対応がスムーズになります。
また、「〇〇より改めてご連絡させていただきます」と伝えることで、相手も「ちゃんと対応してくれるんだな」と安心することができます。電話を切ったあとは、必ずすぐにメモの内容を上司や担当者に共有し、言い忘れや誤解が生じないように注意しましょう。可能であれば、メールやチャットなど記録が残る方法で連絡すると、伝達ミスを防ぐことができます。
自分自身が対応できない内容であっても、「一時的な橋渡し役」としての意識を持つことが大切です。正確で丁寧な伝言対応ができる人は、周囲からも信頼され、社内での評価にもつながっていきます。
社外に電話をかけるときに気をつけたい言葉遣い
自分から社外に電話をかける場面では、言葉遣いや態度に特に注意を払う必要があります。とくに、相手が取引先やお客様の場合、こちらの言葉ひとつで関係性に影響が及ぶこともあるため、慎重さと丁寧さを常に意識しましょう。
電話をかける際には、まず「お忙しいところ恐れ入ります」といった配慮のある一言を添えると、相手にとっても負担を感じさせにくくなります。そのうえで、「〇〇株式会社の△△と申します」「本日は〇〇の件でお電話いたしました」と、目的を簡潔に伝えることが重要です。
また、言葉遣いの中でありがちなのが、「伺わせていただきます」や「おっしゃられたように」など、丁寧すぎるあまり二重敬語になってしまう表現です。こうした表現は一見丁寧に見えますが、相手によっては不自然に感じられてしまうこともありますので、基本的な敬語の使い方を確認しながら、自然な表現を意識して話すようにしましょう。
自信が持てないうちは、事前に話す内容をメモにまとめておくと安心です。話すべきポイントが整理されていれば、言葉に詰まることも少なくなり、スムーズな会話ができるようになります。誠実で丁寧な話し方を心がけることで、相手に安心感と信頼を届けることができ、円滑なやりとりへとつながっていきます。
職場で信頼される電話応対の共通点とは

職場での電話対応に少しずつ慣れてきたころ、「どうすればもっと信頼されるような対応ができるのだろう」と考える方も多いかもしれません。ただ単に正しく話すだけではなく、相手に安心感を与え、丁寧な印象を残す対応を積み重ねていくことが、信頼を得るための近道となります。
電話応対は、言葉の選び方、声のトーン、反応のスピード、そして細やかな気配りなど、さまざまな要素が重なり合って成り立っています。それらひとつひとつに意識を向けることで、自然と「信頼される人」の振る舞いに近づいていくことができます。このセクションでは、職場で評価される電話応対に共通するポイントを、具体的にご紹介していきます。
相手への思いやりを意識した言葉選び
電話のやりとりにおいて、もっとも印象を左右するのが「言葉の選び方」です。同じ内容を伝えるにしても、言い回しひとつで相手が感じる印象は大きく異なります。たとえば、「今、〇〇さんはいません」と言うよりも、「あいにく〇〇はただいま席を外しております」と表現するほうが、ぐっと丁寧な印象になります。
また、言葉に含まれるトーンや気持ちも相手に伝わるため、「申し訳ございません」「お手数をおかけします」といった一言を添えることで、配慮や感謝の気持ちがしっかりと伝わります。これにより、相手も心を開きやすくなり、対話が柔らかく、スムーズなものになっていきます。
相手が話しているときには、適度な相槌や復唱を交えて、「ちゃんと聞いていますよ」という姿勢を示すことも、信頼を築くうえで欠かせない要素です。「はい、承知いたしました」「そのようにお伺いしております」といった言葉を入れることで、会話に安心感が生まれます。電話越しでも、気遣いや誠意はしっかりと伝わるのです。
常に丁寧な姿勢を保つことの積み重ね
電話対応が上達するには、特別なスキルを習得するよりも、日々の丁寧な姿勢をいかに維持できるかが大きなポイントになります。たとえば、どれだけ忙しいときでも、電話が鳴ったらすぐに手を止めて丁寧に応対するという行動には、相手に対する誠意が表れます。
言葉の使い方だけでなく、声のトーンや話すスピード、言葉の切り方に至るまで、丁寧さは細部に宿ります。そして、それらは日々の中で自然と積み重なっていくものです。ある日突然できるようになるのではなく、毎日の応対のなかで少しずつ身についていきます。
また、社内外問わず、すべての相手に同じ丁寧さを保つことも重要です。たとえ気心の知れた取引先であっても、基本的なマナーは崩さず、誰に対しても誠実に対応することが、長期的な信頼を築く基盤となります。
そして、電話が終わったあとにも、もう一度内容を確認したり、社内の担当者に正確に引き継いだりするなど、電話後の対応も丁寧に行うことで、仕事全体への信頼が高まります。日々の小さな丁寧さが積み重なることで、「この人に任せておけば安心」と思われる存在へとつながっていくのです。
忙しい時でも落ち着いた対応が信頼を生む
仕事が立て込んでいるときや、次々に電話が鳴る中で、つい声が早口になったり、返答がそっけなくなってしまうこともあるかもしれません。しかし、そんなときこそ、落ち着いた応対を心がけることが、信頼される電話対応には不可欠です。
相手は、こちらの状況を見ているわけではないため、電話越しに感じる雰囲気がすべてになります。どれだけ多忙であっても、「今ちょっと急いでるんだな」と感じさせてしまえば、それだけで不快に思われる可能性もあります。そんな中でも、いつも通りのトーンで、丁寧にゆっくりと話すことで、相手は安心し、円滑なやりとりが生まれやすくなります。
落ち着いた対応をするためには、まず自分の心の余裕を確保することも大切です。深呼吸をしたり、手元のメモで話のポイントを整理したりすることで、焦らず対応できるようになります。また、「急いでいるときほどゆっくり丁寧に」を合言葉のように意識しておくと、どんな場面でも一定のクオリティを保つことができます。
そして、電話を終えたあとには、「落ち着いて話せたか」「相手に安心感を与えられたか」を振り返ることで、さらに対応力を高めていくことができます。忙しさに流されず、常に落ち着きを忘れない人は、職場の中でも一目置かれる存在となっていきます。
電話マナーと連動するビジネスマナーの基本
電話対応における丁寧さや言葉遣いは、単にその場限りの応対スキルにとどまるものではありません。実は、こうした電話マナーの中には、ビジネスマナーの基本がぎゅっと詰まっています。つまり、電話対応がしっかりとできるようになるということは、ビジネスパーソンとしての土台がしっかりと築かれていることの表れでもあるのです。
職場で求められるマナーは、電話に限らず、メール、対面、社内外のやりとりすべてに共通する部分があります。電話マナーを丁寧に身につけることで、自然と他のビジネス場面でも落ち着いた対応ができるようになり、総合的な信頼感を育てていくことができます。このセクションでは、電話マナーがどうビジネスマナーと結びついているのかを見ながら、日常業務に役立つ基本的な考え方を丁寧にご紹介していきます。
メールや対面対応にも活きる基本姿勢
電話応対で大切にしている「丁寧さ」「的確な受け答え」「相手の立場を考える姿勢」といった要素は、メールや対面でのやりとりにおいてもまったく同じように求められるものです。たとえば、電話での丁寧な言葉遣いや分かりやすい説明は、メール文面の構成や敬語の使い方にもそのまま反映されます。
また、電話で相手の話をしっかりと聞く姿勢は、対面の場面でも相手の表情や反応にしっかりと意識を向けるという「傾聴の姿勢」に通じます。どのようなコミュニケーションでも、「相手がどう感じているか」に意識を向けられる人は、それだけで信頼されやすくなります。
さらに、相手の時間を奪わないように配慮した話し方、要点を整理して伝えるスキルは、会議や報告、日常のやりとりでも重宝されます。電話応対で培った「話す・聞く・伝える」の力は、すべてのビジネスシーンの基盤となり得るのです。
敬語の使い方と適切な言い換え表現
ビジネスマナーの中でも特に重要なのが「敬語の正しい使い方」です。電話応対では、相手と顔を合わせずに言葉だけでやりとりを行うため、言葉遣いの違和感がより強く印象に残りやすい傾向があります。だからこそ、基本的な敬語を正しく理解し、自然に使えるようにすることが大切です。
たとえば、「伺わせていただきます」というような二重敬語になってしまう言い回しは、ついやってしまいがちなミスのひとつです。また、「了解しました」はカジュアルな印象を与えるため、ビジネスの場では「承知いたしました」と言い換える方が丁寧です。
電話対応を通じてこうした敬語の使い方に意識が向くようになると、対面での会話や文書作成においても自然と正しい表現を使えるようになります。敬語に苦手意識がある場合でも、よく使うフレーズをいくつか覚え、それを繰り返し使ううちに、徐々に語彙が広がっていきます。
適切な言い換え表現を習得することで、相手に伝えるメッセージがより明確になり、誤解のないコミュニケーションが可能になります。言葉の選び方ひとつで、自分の印象が変わり、信頼される場面が増えていくことを実感できるようになるでしょう。
TPOに応じた対応力の身につけ方
ビジネスマナーの中でも、場の状況(Time)、場所(Place)、相手(Occasion)に応じて柔軟に対応できる力は、とても大切な素養です。電話対応も例外ではなく、相手が急いでいると感じたときには要点を簡潔に伝える、逆に丁寧に話を聞いてほしそうなときには、焦らずゆっくり対応するなど、状況に合わせた対応が求められます。
たとえば、電話でのやりとりが夜遅い時間帯になった場合は、「遅い時間に申し訳ございません」といった配慮を込めた一言を添えることで、相手の印象が大きく変わります。また、社内の人と話す場合と社外の取引先に話す場合とでは、言葉遣いや話すトーンにも違いが求められます。
このような「場に応じたふるまい」を意識する習慣は、電話以外のビジネスシーンでもとても役立ちます。たとえば来客対応、会議の発言、メール文面の書き方など、すべてのやりとりにおいてTPOに応じた対応力が問われます。
電話マナーを通じてTPOの感覚を磨いていくことで、臨機応変な対応ができるようになり、さまざまな場面で「頼れる存在」として認識されるようになっていきます。
職場の電話対応における不安を減らすヒント

職場で電話に出ることが、どうしても緊張の原因になってしまうという方は少なくありません。とくに新入社員や転職したばかりの方にとっては、声のトーンや言葉遣い、相手とのやり取りのすべてが不安の対象になりやすく、「うまくできるだろうか」「間違えたらどうしよう」という思いがつきまといます。
しかし、電話対応における不安は、多くの場合経験不足や準備不足からくるものです。逆にいえば、少しずつ経験を積み、対応のパターンを知り、自分なりの対応方法を見つけていくことで、その不安は確実に和らいでいきます。このセクションでは、電話対応に不安を感じている方が、少しでも安心して対応できるようになるためのヒントを、やさしく丁寧に解説していきます。
失敗しても落ち込まず改善へつなげる思考
電話対応で失敗してしまったと感じるとき、つい自分を責めてしまいがちです。「どうしてあのときうまく言えなかったのか」「もっと丁寧にすればよかった」と後悔の気持ちが募ることもあるでしょう。しかし、実は電話応対の失敗は、成長のきっかけとして非常に価値のあるものです。
たとえば、名前を聞き逃してしまった、言葉が詰まってしまった、取り次ぎに時間がかかってしまった——こういった失敗は誰もが通る道です。大切なのは、そのとき何が起きていたのかを冷静に振り返り、「次はこうしてみよう」と前向きに考えることです。
「うまくいかなかった」という経験を、次の行動に結びつけることで、自分自身の成長を実感できるようになります。失敗を恥じるのではなく、それをもとに改善策を試してみる——この繰り返しが、やがて自然な電話対応へとつながっていきます。
そして何よりも、「完璧な対応ができる人はいない」という事実を受け入れることが大切です。ベテランの社員であっても、相手の状況や内容によって迷うことはあります。だからこそ、失敗を責めるのではなく、「次はもう少しうまくやれたらいいな」というやわらかな気持ちで向き合う姿勢が、不安を軽くする第一歩になります。
困ったときはどうする?適切な助けの求め方
電話対応をしていると、自分ではどう対応したらいいか判断に迷う場面に出くわすこともあります。たとえば、相手が怒っている、専門的な内容を話し始めた、重要そうな話だけど判断がつかない——そんなときに「助けを求めてもいいのかな」とためらってしまう人も多いかもしれません。
でも、職場での電話対応は一人で抱え込むものではありません。むしろ、分からないときにすぐ相談できることは、仕事をスムーズに進めるうえでとても大切な行動です。対応に迷ったら、「すみません、この内容について確認させてください」と電話を保留にし、近くの先輩や上司に助けを求めるようにしましょう。
そのときのポイントは、電話の相手に対しても誠実に伝えることです。「確認いたしますので、少々お時間をいただけますか?」とひとこと添えるだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。誰かに相談することは、決して「頼りないこと」ではなく、「正確に対応したい」という誠意の表れでもあるのです。
また、日ごろから「こういう場合はどう対応していますか?」と先輩に尋ねておくことで、いざというときの判断材料を増やしておくことも不安軽減につながります。電話応対の不安を一人で抱えず、「確認していいんだ」「聞いても大丈夫なんだ」という安心感を得ることが、心の余裕を育てるカギになります。
緊張を味方に変える考え方の工夫
電話が鳴るたびに緊張してしまう人にとって、「緊張=悪いこと」という思い込みが不安をより強めてしまうことがあります。しかし、緊張そのものは人間の自然な反応であり、決して消すべきものではありません。むしろ、その緊張をうまく付き合いながら、少しずつ「味方」に変えていくという考え方が大切です。
たとえば、「緊張しているからこそ丁寧に話そう」「慎重に確認しよう」という気持ちは、実際にはとても大事な対応につながっています。心臓がドキドキしていたとしても、それが電話越しにそのまま伝わるわけではありません。むしろ、意識してゆっくり話すことで、相手には落ち着いた印象を与えることができます。
緊張を和らげるためには、自分自身に優しい言葉をかけることも効果的です。「大丈夫、少しずつ慣れていけばいい」「今日は昨日より落ち着いて話せた」というように、ポジティブな視点を持つことで、自然とプレッシャーが和らいでいきます。
また、電話に出る前に深呼吸をしたり、簡単なストレッチをすることで体の緊張をほぐすことも、心を落ち着ける方法としておすすめです。緊張を感じるたびに「またひとつ慣れるチャンスがきた」と考えることで、不安は次第に経験へと変わり、自信へとつながっていきます。
日々の電話応対から得られる学びと自信
電話対応という業務は、表立って評価されることが少なく、時には地味な作業のように感じられるかもしれません。しかし、日々の中で電話に出て、相手の話を丁寧に聞き、自分の言葉で受け答えをするという行為の積み重ねは、着実に社会人としての基礎力を育ててくれます。
自分ではあまり意識していなくても、電話の対応を通して得ている学びや気づきは確実に存在しています。そして、その小さな積み重ねがやがて「自分でもしっかり対応できる」という自信へとつながっていきます。このセクションでは、電話応対を通じて得られる学びと、それがどのように自信につながるかについて、あらためて丁寧に考えてみましょう。
コミュニケーション能力の向上を実感する瞬間
電話対応を続けていくうちに、「相手の話が自然と聞き取れるようになってきた」「自分の言葉でうまく伝えられるようになった」と感じる瞬間が少しずつ増えていきます。こうした実感は、コミュニケーション能力の向上を表す確かなサインです。
特に電話は、相手の表情や態度が見えない中で言葉だけでやりとりを進める必要があるため、相手の言葉選びや声のトーンに耳を傾け、的確に反応する力が自然と養われていきます。これは、日常の対面での会話や会議、プレゼンテーションなどでも生かすことができる、大きな財産となるスキルです。
「相手の意図をくみ取って応える」という力は、一朝一夕で身につくものではありません。だからこそ、日々の電話応対の中で繰り返し経験を重ね、ひとつひとつの対応を丁寧に行うことで、知らず知らずのうちに大きな力が育っていくのです。自分がスムーズに対応できるようになったとき、その変化を感じる瞬間こそが、日々の努力が実を結んだ証でもあります。
ビジネスパーソンとしての成長を振り返る
電話対応の経験は、振り返ってみると、ビジネスパーソンとしての成長そのものといえるかもしれません。入社したばかりの頃には、電話が鳴るたびにドキドキし、相手の言葉にうまく対応できなかったとしても、少しずつ慣れていく過程の中で、確かな変化が生まれます。
たとえば、相手が何を求めているのかを予測して動けるようになったり、話し方に余裕が出てきたりするのは、経験を通じて磨かれた力です。また、自分が感じていた不安を後輩に伝えたり、サポートしたりする側に回れるようになると、自分がどれほど成長してきたかを実感することもあるでしょう。
電話というシンプルなツールの中に、実は「聞く力」「伝える力」「判断力」「対応力」といった多くの要素が詰まっていることに気づいたとき、改めてその奥深さと、自分の成長を支えてきた存在としての電話応対に、感謝の気持ちすら芽生えるかもしれません。
一見目立たない日々の積み重ねこそが、成長の礎であり、やがて大きな信頼へとつながっていくのです。
自信を持って「任せてもらえる」存在になる
電話対応における成功体験が増えてくると、次第に職場の中でも「この人なら任せても大丈夫」と思われるようになっていきます。たとえば、取引先とのやりとりを任されたり、大切な電話を最初に受ける役割を担ったりすることが増えてくると、それは周囲からの信頼の証であり、自分の中に芽生えた自信をさらに後押ししてくれるようになります。
「自分が電話に出ると、安心してもらえる」という実感は、仕事へのモチベーションにもつながり、「もっと上手に対応したい」「より相手に寄り添った言葉を使いたい」といった前向きな気持ちを育ててくれます。これは単なる業務の一部ではなく、職場の中での自分の役割を広げていく、大きなステップともいえるでしょう。
誰かに頼られること、任せられることは、自信の源になります。そしてそれは、日々の電話応対という一見地味な業務の中に、確実に宿っているのです。
まとめ
職場での電話対応は、業務の中では決して派手な存在ではありませんが、だからこそ誠実さや丁寧さがまっすぐに表れる、非常に大切なコミュニケーションのひとつです。相手の顔が見えないからこそ、言葉遣いや声のトーン、反応のスピード、そして細やかな配慮といったすべてが、相手に与える印象に直結します。
本記事では、電話を「かける」「受ける」といった基本的なステップから、不安を感じたときの心の整え方、場面ごとの具体的な対応方法、さらに電話マナーを通じて得られるビジネスマナーまでを、段階的にお伝えしてきました。どの内容も、すぐに完璧にできるようになる必要はありません。むしろ、少しずつ繰り返し、毎日の中で自然に身につけていくことが、確かな成長につながっていきます。
電話対応に苦手意識を持っていたとしても、その気持ちを否定する必要はありません。不安を感じるということは、それだけ丁寧に、真面目に取り組もうとしている証拠です。その姿勢こそが、相手にも伝わり、やがて「この人と話すと安心する」と感じてもらえるようになります。
そして、電話応対ができるようになることで得られるのは、単なるスキルの習得にとどまりません。言葉を丁寧に選ぶ力、相手に配慮する姿勢、冷静に物事を判断する習慣。それらすべてが、あなた自身の信頼を育て、職場での存在感を少しずつ広げてくれるはずです。
どんなに小さな経験でも、それは確実に前に進む一歩になります。電話を通じて誰かとつながり、伝え合い、仕事を動かしていく。そんな日々の中にこそ、あなたの成長の種がしっかりと息づいているのです。