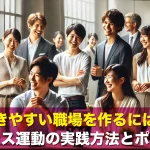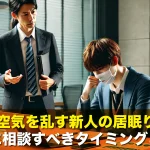毎日の仕事の中で、「なぜうまくいかないのか分からない」「やるべきことが多すぎて整理できない」と感じたことはありませんか?忙しい現場では、とりあえず目の前の業務をこなすだけで精一杯になってしまい、気づかないうちに本来の目的や優先順位を見失ってしまうこともあります。
そんなとき、頼りになるのが「5W1H」という考え方です。5W1Hとは、「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」という、6つのシンプルな疑問から構成される思考のフレームワークです。
一見、学校の作文や報告書で使うような基本的な構成に思えるかもしれませんが、実はこの問いを日々の仕事の中で意識することで、驚くほど頭の中が整理され、判断力や伝える力がぐっと磨かれていきます。さらに、自分の気持ちや行動の背景を見つめ直すきっかけにもなり、仕事への向き合い方そのものが少しずつ変化していくのです。
この記事では、「5W1H」をただの言葉として覚えるのではなく、実際の業務や自己分析にどう活用できるのかを丁寧にご紹介していきます。毎日の仕事をもっと前向きに、もっと納得感のあるものにするためのヒントを、ぜひ見つけてみてください。
この記事の目次(タップでジャンプ)
5W1Hとは?仕事にどう役立つのか

仕事の中で「何がうまくいかないのか分からない」「考えがまとまらない」「話が噛み合わない」そんなもどかしさを感じたことはありませんか?忙しい日々の中で、なんとなく目の前のタスクをこなしていると、自分が本当にすべきことを見失ってしまったり、同じようなミスを繰り返してしまったりすることがあります。そうした状況に気づき、立ち止まって状況を見つめ直すときに役立つのが、「5W1H」という考え方です。
5W1Hとは、英語の6つの基本疑問詞、「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の頭文字を並べたものです。これらは文章や報告の構成要素として知られており、ニュースやレポートなどで使われることが多いですが、実は日常の仕事の中でも大いに力を発揮してくれるフレームワークです。
それぞれの疑問を丁寧に投げかけながら物事を整理していくことで、自分が今取り組んでいる仕事の意味や背景、進め方の妥当性などを客観的に見つめることができるようになります。また、自分の頭の中だけでなく、チームで共有する際にもこの6つの視点をもとに説明を構成すれば、相手に伝わりやすく、誤解を生みにくくなるという大きな利点があります。
それでは、この「5W1H」について、まずは基本的な部分から丁寧に見ていきましょう。
5W1Hの基本をおさらいする
「5W1H」は、昔から使われてきた普遍的な思考の枠組みです。そのルーツをたどれば、教育の現場から報道の現場、ビジネスやマーケティングの場面にいたるまで、あらゆる分野で活用されてきた歴史があります。特に仕事の現場では、問題解決や意思決定、コミュニケーションの整理など、さまざまな場面で役立ちます。
まず、「When(いつ)」は、時間やタイミングに関わる疑問です。業務の締切や予定の見直し、進捗状況の報告などで、「いつ」という観点を持つことで、時間に対する意識が明確になります。
「Where(どこで)」は場所の確認です。作業場所や会議の場所、対応が必要な現場など、場所を明示することで情報の誤解や混乱を防ぐことができます。
「Who(誰が)」は、担当者や関係者を特定する視点です。プロジェクトにおいては、誰が何をしているかが曖昧だと責任の所在が分かりにくくなります。この視点を使うことで、役割分担を明確にすることができます。
「What(何を)」は、対象となる内容そのものを確認するものです。何の業務か、何の目的で行っているのかなど、仕事の核となる部分を整理します。
「Why(なぜ)」は、目的や理由の確認です。なぜこの仕事をするのか、その背景や動機を理解することで、行動の意味がはっきりします。これはモチベーションにも大きく関わってきます。
最後の「How(どのように)」は、方法や手段の確認です。仕事のやり方を決める際、無理なく、かつ効率的に進められる方法を検討するために不可欠な視点です。
このように、5W1Hは一見シンプルな問いかけに見えますが、実際には非常に奥深く、すべての業務に応用できる柔軟さを持っています。
仕事における情報整理の土台になる理由
仕事では、日々さまざまな情報が飛び交います。その中には、社内での連絡事項、取引先とのやりとり、進行中のプロジェクトの詳細など、重要な要素が詰まっていますが、それを正しく受け取り、解釈し、行動に結びつけるのは簡単ではありません。
情報が多くなると、人はつい全体像を見失いがちになります。細部に目を奪われると、本来の目的を見誤ったり、手段ばかりに目がいってしまうこともあるでしょう。そこで5W1Hを用いると、自然と情報を分類しやすくなります。
例えば、受け取ったメールを読み解く際に「これはいつの話?」「誰が関係しているの?」「なぜこの対応が必要なの?」と自問しながら読むことで、ただ流し読みするよりも遥かに理解が深まります。このプロセスは、資料を読むとき、議事録を整理するとき、あるいはタスクを管理するときにも応用できます。
また、複雑な問題を解決するときにも、5W1Hをベースに考えれば、何が明確で、何が不明なのかが浮き彫りになります。問題を要素ごとに切り分けて考えることで、感情に振り回されず冷静に対応できる土台が整います。
つまり5W1Hは、思考の型をつくるだけでなく、情報の「迷子」にならないように導いてくれる地図のような役割を果たしてくれるのです。
チーム間の認識共有にも役立つ考え方
仕事の多くは、チームで協力して進めることが求められます。一人で完結する業務は少なく、誰かと連携しながらタスクを遂行していく場面がほとんどです。そんなときに起こりやすいのが、認識のずれです。
「伝えたつもりだった」「わかっていると思っていた」――そうした思い込みが、結果的に誤解を生み、ミスやトラブルの原因になってしまうこともあります。このような認識の違いを防ぐために、5W1Hの視点で確認することは非常に効果的です。
たとえば会議の中で「この件、進めておいてください」と伝えた場合、それだけでは「いつまでに?」「どこで?」「誰と?」「なぜその業務をするのか?」といった重要な情報が抜け落ちてしまっているかもしれません。そんなときに、5W1Hを意識して伝えるだけで、相手との共通認識が驚くほどクリアになります。
また、複数人で同じプロジェクトに取り組む場合、情報共有のルールとして「報告は5W1Hに沿って行う」という共通ルールを設けることで、全員が同じ情報をもとに判断・行動できるようになります。これは特にリモートワークやオンラインでのやりとりが中心になっている今の働き方において、より重要になってきている視点です。
5W1Hは、相手に思いやりを持って情報を伝える工夫でもあり、自分の理解を深める助けにもなります。話し手と受け手、両方にとって安心できる仕事環境をつくる土台となってくれるのです。
6つの疑問で状況を明確化する方法
日々の仕事のなかで、「状況がよくわからない」「なぜこれをしているのかあいまい」「誰がやるべきか決まっていない」など、何となくもやもやした状態で物事が進んでしまうことは少なくありません。そんなときに、明確にすべきポイントを整理するうえで役立つのが「5W1H」による6つの疑問です。
この6つの疑問を1つずつ丁寧に投げかけていくだけで、全体像が見えてきたり、優先順位がつけられたり、次に取るべき行動が明らかになったりすることがあります。とてもシンプルな問いかけであるにもかかわらず、その効果は想像以上です。
特に忙しいときや複雑なプロジェクトを抱えているときほど、あえて立ち止まって6つの疑問を使うことが、結果的にスムーズな進行を助けてくれます。ここではそれぞれの疑問が、どのように仕事に役立つのかを順に見ていきましょう。
「なぜ?」を問い直すことで見える本質
「Why(なぜ)」という疑問は、5W1Hのなかでもとくに奥深い問いです。なぜこの仕事をするのか、なぜこの手順なのか、なぜ今なのかという問いは、表面的な行動や現象の裏にある目的や意味に目を向けさせてくれます。
たとえば、ある資料の提出を急かされたとします。そのときに「なぜ急いでいるのか」という理由を確認していないと、ただ作業を急ぐことに集中してしまい、かえってミスが増えたり、相手の期待とずれてしまう可能性があります。
「なぜそれが必要なのか?」を丁寧に確認することで、場合によっては別の方法で対応できたり、優先順位を変更したりする判断も可能になります。このように、「なぜ?」という疑問は、物事の根底にある動機や背景を知るための大切な入り口なのです。
また、自分自身の仕事に対しても「なぜ私はこの仕事をしているのか」「この業務に意味を感じられているか」といった問いを投げかけてみると、日々の働き方への向き合い方や、将来の方向性を見直すきっかけになることもあります。
「誰が?」「何を?」で責任と役割を明確に
仕事を進めるうえで、役割分担があいまいなままになってしまうと、作業が滞ったり、同じことを別の人が重複して対応してしまったりと、非効率な結果になりがちです。そういった混乱を防ぐために意識したいのが、「Who(誰が)」「What(何を)」という視点です。
「誰が」そのタスクを担当するのかを明確にすることで、責任の所在がはっきりし、無用なトラブルを回避できます。加えて、「何を」するのかを具体的に言葉にすることで、指示や依頼が曖昧にならず、相手にとっても行動がとりやすくなります。
たとえば、「明日の準備をお願いね」という依頼があったとき、「誰が?」「何を?」が抜けていれば、複数人が「誰のこと?」「どの準備?」と戸惑ってしまいます。一方で、「〇〇さんに、△△の資料を印刷しておいてほしい」と言えば、相手にとっても何をどうすればよいかが明確になります。
また、チームで働く場合は、それぞれのメンバーがどの部分を担うのかを5W1Hで分けて整理しておくと、全体の進行がスムーズになります。特に新人や異動したばかりのメンバーがいるときには、「誰が何をするのか」の説明を明文化しておくことで、早期の理解と適応を助けることにもつながります。
「どこで?」「いつ?」で時間と場所の管理を強化
「Where(どこで)」と「When(いつ)」は、業務を現実の行動として進めるうえで非常に実務的な要素です。どこで仕事をするのか、いつまでに仕上げるのか――これらが曖昧なままだと、せっかく考えたプランも実行されないまま終わってしまうかもしれません。
仕事には、報告の期限、会議の予定、納品のタイミングなど、さまざまな「時間の決まりごと」が存在します。それに加えて、物理的な場所の指定や、どの環境で行うかも重要な要素です。これらの条件が揃っていないと、どんなに準備をしていても「思っていた場所ではなかった」「時間が合っていなかった」というズレが生じてしまいます。
たとえば「午後までに仕上げてください」と言われたとしても、人によって「午後」の解釈は異なることがあります。13時を指しているのか、16時なのか。こうした曖昧さを避けるために、「いつ」「どこで」という情報は、可能な限り具体的にしておくことが大切です。
また、働き方が多様化している現代では、「どこで仕事をするか」も重要なテーマになっています。テレワークやフリーアドレスの導入により、場所にとらわれない働き方が増えていますが、それだけに「どこで作業するのか」を明示することが、組織内での混乱を避けるうえでも必要です。
5W1Hのなかでも、特に「どこで」「いつ」は、計画を実行段階へと移すための仕上げの問いともいえます。きちんと答えを出しておくことで、仕事の実行力が格段に高まるのです。
具体的な業務での5W1Hの活用例

5W1Hの考え方は、仕事における基本的な思考の整理ツールでありながらも、実際の現場でどう活用するかが難しく感じられることもあるかもしれません。「知ってはいるけれど、日常業務にどう落とし込めばいいかわからない」という声も少なくありません。ですが、5W1Hは、実はあらゆる業務の中に自然と溶け込ませることができる、とても実用性の高いフレームワークです。
この章では、日々の仕事のなかでもよくあるシーンを取り上げながら、5W1Hをどのように活かしていけるかを具体的に掘り下げていきます。難しいことを覚えたり、新たなツールを導入したりする必要はありません。今すぐできる、シンプルで続けやすい使い方を意識することで、自然と仕事の流れが整っていきます。
報告・連絡・相談をスムーズにするコツ
社会人として基本とされる「報連相(ほうれんそう)」ですが、頭ではわかっていても、いざ実践となると伝え方やタイミングに悩むことは多いものです。そんなとき、5W1Hを意識して伝えることが、相手にとってわかりやすく、受け取りやすい報告や相談の形になります。
たとえば「〇〇の件ですが、遅れそうです」とだけ伝えると、受け取る側は「何が?」「どれくらい遅れるの?」「なぜ遅れているの?」と疑問が次々に浮かんできます。しかし、「〇〇の納品作業(What)が、機材トラブルにより(Why)、15時までに完了できない見込みです(When)。今はサポート部署(Where)に依頼して復旧作業をお願いしており(How)、私(Who)が状況の報告と調整を行っています」と伝えれば、聞き手はスムーズに状況を理解でき、対応の準備も進めやすくなります。
報告や相談の内容を頭の中で5W1Hの形に整理してから言葉にするだけで、自分の中でも状況がクリアになり、不安や混乱が減る感覚が得られるはずです。相手と認識を共有するためにも、自分自身の心を整えるためにも、5W1Hはとても役立ちます。
会議の議題設定や進行に使う方法
会議というのは、複数の人が集まり、それぞれの立場や意見を出し合いながら、物事を前に進めるための大切な時間です。しかし、会議が終わっても「何を決めたのかわからない」「時間ばかりが過ぎた」という印象を持つことも少なくありません。こうした会議の場面にも、5W1Hはとても有効に機能します。
まず、会議の議題を考えるときに、「何を話すのか(What)」「なぜその議題を取り上げるのか(Why)」「誰が関係しているのか(Who)」という3つの視点を意識すると、それだけでテーマの軸が明確になります。さらに、「いつまでに意思決定が必要なのか(When)」「どの会議室やツールを使って行うか(Where)」「どういった形式で進めるのか(How)」という要素を整理しておくことで、会議そのものの質が格段に上がります。
たとえば、プロジェクト進行に関する会議なら、「どこまで進捗が出ているか」「課題は何か」「次にどんな対応が必要か」といった話題を、5W1Hのフレームに当てはめて発言することで、話が脱線しにくくなり、参加者全員の意識もそろいやすくなります。
進行役が5W1Hをもとにファシリテートすることで、会議全体の空気が引き締まり、話す内容にも深みが出てきます。そして最後には、「誰が何をいつまでにするのか」といったアクションを具体的に残すことで、実のある会議として成果が見える形になります。
トラブル対応で冷静に対処するための枠組み
仕事にトラブルはつきものです。想定外の出来事が起こったとき、どうすれば冷静に対処できるかは、経験やスキル以上に、状況を把握するための「考え方」が影響します。そのときこそ、5W1Hの出番です。
たとえば、クライアントからクレームが入った場合、「何についてのクレームか(What)」「誰が対応しているのか(Who)」「いつから問題が起きているのか(When)」「どこでの対応が必要なのか(Where)」「どんな対応をしてきたのか(How)」「なぜこの状況になったのか(Why)」という形で情報を整理していけば、事実関係が明確になり、感情に流されることなく対処が可能になります。
特に「なぜ?」の部分を深掘りできると、表面的な原因ではなく、根本的な原因にたどり着くことができ、再発防止につなげることも可能になります。また、「誰が悪いか」を探すより、「何が起こったか」を軸に考えることで、対話のトーンも穏やかになり、チーム内の信頼関係も守ることができます。
冷静な状況整理ができる人は、周囲からの信頼も厚くなります。5W1Hというシンプルなフレームを手に入れておくことは、トラブル時の安心材料にもなるのです。
5W1Hで成果を上げる考え方のポイント
5W1Hは、ただ質問を並べるだけのツールではありません。その本質は、問いを通して自分の思考を整理し、相手に伝え、行動につなげていくプロセスにあります。つまり、5W1Hをどのように「考えるか」が、最終的な成果を大きく左右します。
仕事の成果というのは、ただ多くのことをこなすだけでは得られません。一つひとつの行動の意味や背景を理解し、必要なことに集中して取り組むことで、質の高い成果につながります。ここでは、5W1Hを効果的に使って成果を上げるための考え方を、具体的な観点から掘り下げていきます。
問いの質を高めるために意識すべき視点
仕事における問題解決や判断の場面で、5W1Hのようなフレームワークは「問いを立てる力」を養うための道具としても使えます。ただし、このときに重要なのは「どんな問いを立てるか」という視点です。
たとえば、「なぜ売上が伸びないのか?」という問いに対して、ただ表面的な原因を探すのではなく、「その売上とは具体的に何の売上なのか」「どの期間を比較しているのか」「どんな要因が関わっているのか」といった補助的な問いを重ねていくことで、本質的な問題に近づくことができます。
質の高い問いは、答えを引き出す力を持っています。逆に、曖昧な問いや抽象的すぎる問いは、行動を迷わせたり、時間だけが過ぎてしまうことにもつながります。そのため、問いを立てるときには「具体性」「目的」「対象の明確さ」を意識することが、非常に大切です。
また、問いの言葉選びにも気を配ることで、思考の深さが変わってきます。たとえば「どうやってやるか?」という問いに対して、「どんな順番で進めるか?」「どのリソースを活用するか?」「誰に協力を求めるか?」といったように、より踏み込んだ問いを展開していくと、行動に結びつくヒントが見つかりやすくなります。
5W1Hは、その6つの枠に従うだけでも有効ですが、さらに一歩踏み込んで「より良い問いとは何か」を考えることで、使い方に深みが増していきます。
問いの順序を工夫して議論を深める
5W1Hを活用する際には、「どの順番で問いかけるか」によって、思考の流れや議論の方向性が大きく変わることもあります。順序を変えるだけで、話が広がったり、逆に絞られたりすることがあるのです。
たとえば、新しい企画を考える場合、「What(何をするか)」から入ると具体的なアイデアが出やすくなりますが、「Why(なぜそれをするのか)」からスタートすれば、目的や背景に重きを置いた深い議論が可能になります。また、現場でのトラブル対応では、「When」「Where」といった事実確認から入ることで、冷静な状況整理がしやすくなります。
このように、問いの順序は状況によって柔軟に使い分けることが求められます。すべての問いを必ず同じ順番で並べる必要はありません。むしろ、その場にふさわしい順番で問いを立てることで、よりスムーズに物事を掘り下げていくことができます。
特に、複数人で話し合いをするときには、話が脱線しがちな場面で「今はWhyに集中しよう」「ここではWhatに立ち返って考えよう」といった形で流れを整える手段としても活用できます。問いの順番を意識するだけで、議論の進行が驚くほどスムーズになることを実感できるはずです。
情報過多を防ぎ、要点を絞る技術
現代のビジネス環境では、情報があふれかえっており、「何を選べばよいか」「どこに注目すべきか」が分からなくなることがよくあります。そんな中で5W1Hは、情報を選び取り、要点を絞るための「フィルター」としても使うことができます。
たとえば、会議の報告資料を作成する場面で、すべての情報を詰め込もうとすると、結局何を伝えたいのかがぼやけてしまうことがあります。そこで、「Whoが関係していて、Whatが起きて、WhenとWhereで対応があって、Whyそれを実施して、Howで行ったのか」と、あらかじめ答えるべき要素を5W1Hで整理しておけば、必要以上に情報を盛り込みすぎることなく、伝えるべきポイントを絞ることができます。
また、メールや報告書のように短く的確に伝える必要がある場合でも、5W1Hを意識しておけば、相手が知りたいことをきちんと網羅した、わかりやすい文章を作成することができます。これは読み手の理解を助けるだけでなく、書き手自身が情報の優先順位をつける訓練にもなります。
つまり、5W1Hは情報を「足していく」だけでなく、「削っていく」ための思考ツールでもあるということです。必要な情報だけを的確に伝えることで、相手にとっても、自分にとっても心地よいコミュニケーションが実現します。
5W1Hを定着させるための習慣と工夫

どんなに優れた考え方やツールも、知識として頭の中にあるだけでは十分に活かされているとはいえません。5W1Hも同様で、日々の業務のなかに自然と溶け込ませ、繰り返し使うことで初めて、その力を実感できるようになります。言い換えれば、5W1Hは「身につけるもの」であり、「使いこなす技術」なのです。
とはいえ、最初から完璧に使いこなそうとする必要はありません。大切なのは、小さな場面から少しずつ意識していくことです。そして、それを続けていくうちに、自分でも気づかないうちに思考や行動の中に自然と根づいていきます。この章では、5W1Hを無理なく習慣として身につけるための工夫について、実際の仕事に馴染む形でご紹介していきます。
毎日の業務に自然と取り入れる習慣
5W1Hを定着させるための第一歩は、「毎日、無理なく続けられるタイミング」を見つけることです。たとえば、朝の始業前にその日の予定を確認するとき、「今日は誰と何をする予定か?」「なぜこの仕事が今必要なのか?」と、自分に問いかけてみるだけでも十分な訓練になります。
このとき、すべての問いに答えを出そうとしなくても構いません。「そういえば“Why”の部分は少し曖昧だな」「“How”がまだ見えていないかも」と気づけることが、すでに価値ある一歩です。問いを立てること自体が思考の訓練であり、そこから何を見直すべきかが明確になるからです。
また、1日の終わりにちょっと立ち止まって、「今日の業務を5W1Hで振り返ってみよう」としてみるのもおすすめです。行動を見直すことで、自分の仕事の進め方や、考え方の癖にも気づきやすくなり、明日への改善につながっていきます。
このようなちょっとした習慣の中に、5W1Hを「問いの型」として取り入れることで、自然と視野が広がり、仕事への向き合い方にも前向きな変化が生まれてくるのです。
チーム全体で使うための共有方法
5W1Hの考え方は、自分だけで使うよりも、チームで共有しながら使うことで、より大きな効果を発揮します。特にチームでプロジェクトを進めている場合や、業務の分担が複雑になっている組織では、情報の行き違いや解釈のズレが起こりやすくなります。
そんなとき、チーム全体で「5W1Hを意識して話すようにしよう」とルール化するだけでも、会話や報告の質が大きく変わります。会議やチャットの中でも、「その“Why”の部分をもう少し教えてほしいな」「“Who”が決まっていないから、もう一度確認しようか」といった言葉が自然に飛び交うようになれば、お互いの認識のずれをその場で調整できるようになります。
また、新人や異動者への業務引き継ぎの際に、「この業務は5W1Hで整理するとわかりやすいよ」と伝えることで、相手にとっても業務の全体像がつかみやすくなります。業務マニュアルや手順書を作成する際にも、5W1Hを意識して構成することで、読み手にとって理解しやすいドキュメントになります。
このように、個人だけでなくチーム全体で「5W1Hを共通言語にする」ことは、情報共有を円滑にし、信頼感のある職場づくりにもつながっていきます。
定期的な振り返りでブラッシュアップする
どんなスキルも、一度使って終わりではなく、繰り返し振り返ることで精度が上がっていきます。5W1Hもまた、日々の仕事の中で「これはうまく使えたな」「もう少し問いの立て方を工夫できたかもしれない」と振り返ることによって、自分の使い方が洗練されていきます。
たとえば、週に一度のミーティングや日報の中で、「今週はどんな“Why”にこだわって仕事をしたか」「“How”の部分で工夫したことは何か」などを共有する機会を持てば、自分の行動を言葉にすることで理解が深まり、他のメンバーの工夫から新たなヒントを得ることもできます。
また、失敗したと感じた場面にも5W1Hをあててみることで、「どこに原因があったのか」「誰が関係していたのか」「どうすればよかったのか」を客観的に見直すことができます。これは責任を追及するのではなく、次への改善策を見出すための前向きな振り返りとして、とても有効です。
定期的な振り返りを続けていくことで、5W1Hの問いがどんどん深まり、言葉の選び方や伝え方にも磨きがかかっていきます。最初は意識的に使っていたフレームが、次第に自分の考え方や行動に自然と組み込まれていく。その過程こそが、スキルとしての5W1Hが「自分のものになる」プロセスなのです。
仕事の種類に応じた5W1Hの使い分け
5W1Hは、あらゆる仕事に対応できる柔軟なフレームワークですが、実際の業務の種類や目的によって、その使い方には微妙な違いがあります。たとえば、全体を俯瞰して指揮をとる仕事と、現場での作業に直接関わる仕事とでは、必要とされる問いや視点が異なるのです。
大切なのは、自分の業務内容に合わせて、どの問いを中心に据えるかを調整することです。それぞれの業務に適した問いを選び、使い方を工夫することで、5W1Hはより実践的で効果的なツールとなります。この章では、仕事の性質ごとに異なる5W1Hの活用の仕方をわかりやすく掘り下げていきます。
マネジメント系業務での活用
マネジメントに関わる仕事は、組織やチーム全体の方向性を整え、目標に向かって人や時間、資源を適切に配分することが求められます。そのため、ただ情報を集めるだけでなく、「なぜそれが必要なのか」「何を優先すべきなのか」といった判断軸を明確にする必要があります。
ここで活きてくるのが「Why(なぜ)」「What(何を)」「Who(誰が)」という視点です。たとえば、ある施策をチームで実行しようと考えたとき、「なぜその施策が今必要なのか」「それによって何を実現したいのか」「誰にどんな役割を担ってもらうのか」と問いを立てていくことで、プロジェクト全体の構成が見えてきます。
さらに、マネジメントでは「How(どのように)」の問いも非常に重要です。計画を具体的なアクションに落とし込むときや、チームメンバーの負担や能力に配慮しながら進め方を考える際に、この視点があることで現実的なプランを立てることができます。
このように、マネジメントでは5W1Hを使って状況を整理し、判断の精度を高めながら、人と組織の動きを整えていくことが求められます。
現場や実務系タスクでの応用
現場での実務を中心とした仕事では、スピード感と正確さが求められることが多く、5W1Hの問いもより実践的で具体的な使い方が必要になります。たとえば、作業内容の把握や手順の確認などでは、「What(何を)」「When(いつ)」「Where(どこで)」の問いが中心になります。
作業に取りかかる前に「何をすればよいのか」を明確にし、「いつまでに完了すべきか」「どこで行うか」を把握しておくことで、行動に迷いがなくなり、無駄なやり直しや確認が減っていきます。
また、「How(どのように)」の問いも、現場の安全性や効率性を左右する重要な視点です。機械の操作手順や、資料のまとめ方など、実際の動きや手順を具体的にイメージすることが、仕事の質を安定させるポイントになります。
特に、繰り返し行うルーチンワークであっても、5W1Hを使って毎回の作業を振り返ることで、小さな改善点や無駄に気づくことができます。こうした細やかな見直しを積み重ねることが、現場の成長と安定につながるのです。
クリエイティブや企画業務に使う視点の違い
アイデアを生み出したり、新しい企画を立ち上げたりするような仕事では、5W1Hを「自由な発想を整理するツール」として活用するのが効果的です。クリエイティブな業務は感覚や直感が重視される反面、それを形にして他人に伝えたり、実行可能なプランに落とし込むことが難しいと感じることがあります。
そんなとき、「Why(なぜ)」と「What(何を)」の問いを深く掘り下げることで、アイデアの背景やコンセプトが明確になってきます。「なぜこのアイデアを選んだのか?」「このアイデアが提供する価値は何か?」といった問いを繰り返すことで、発想がブレずに深まっていく感覚を得られるでしょう。
また、最終的には「How(どのように)」という視点を通して、アイデアを現実的な企画に整える作業も必要になります。企画は思いつきだけでは終わらず、スケジュールやリソース、手段を伴って初めて実現可能になります。ここに5W1Hの整理力が活きてくるのです。
一方で、クリエイティブ業務では「Who」や「Where」「When」の問いが直接的に関わらないこともありますが、それでもあえて問いを立ててみることで、想像力が広がることもあります。たとえば「この企画は“誰に”届けたいのか」「“どこで”体験してもらいたいのか」と考えることで、より具体的で伝わりやすいコンセプトに進化していくのです。
5W1Hと他の思考フレームとの組み合わせ方

5W1Hは、シンプルでありながら非常に汎用性の高いフレームワークです。ですが、より深い思考や多角的な視点が求められる場面では、5W1Hだけでは整理しきれない情報や判断軸が生まれてくることもあります。そんなときに有効なのが、他の思考フレームと組み合わせて使うという方法です。
それぞれのフレームには得意な用途や切り口があります。5W1Hを軸にしながら、それを補完する形で他のフレームを活用することで、思考の幅が広がり、より深く、具体的なアウトプットにつながっていきます。この章では、代表的な3つの思考法と5W1Hを掛け合わせることで得られる相乗効果についてご紹介していきます。
ロジックツリーとの併用で課題を深掘る
「ロジックツリー」とは、ひとつの問題やテーマに対して、「なぜそうなったのか」「どのような要因があるか」を分解して整理していくためのフレームです。原因分析や要素分解に優れており、問題の本質を見抜くための手助けとなります。
ここに5W1Hを組み合わせることで、より実践的な分析が可能になります。たとえば、ある商品の売上が伸び悩んでいるという課題があった場合、まず「What=売上減少」という事象を起点に、ロジックツリーで「顧客数の減少」「単価の低下」「リピート率の悪化」などに分解していきます。そのうえで、それぞれの要素に対して「なぜ?」「いつから?」「どこで?」と5W1Hの問いを重ねていくと、数字やデータだけでは見えなかった背景が浮かび上がってきます。
ロジックツリーが縦に掘り下げていく道なら、5W1Hは横に広げて視野を確保する役割を果たします。この2つを組み合わせることで、論理的かつ多角的な視点から問題にアプローチできるようになるのです。
PDCAとの連動で改善を加速させる
業務改善やプロジェクト管理の現場でよく使われる「PDCA」は、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のサイクルを回し続けることで、成果を少しずつ高めていくためのフレームです。このPDCAと5W1Hを組み合わせることで、それぞれのステップの中身がより具体的かつ明確になります。
たとえば、「Plan」の段階では、「なぜこの計画を立てるのか(Why)」「誰が何をするのか(Who/What)」「いつまでにどこで実行するのか(When/Where)」などを5W1Hで整理しておくことで、曖昧な計画にならず、行動に移しやすい形になります。
「Do」の段階では、「どのように進めるのか(How)」という視点を軸に、実行手順を具体的に詰めることが求められます。そして「Check」では、「何ができたか」「なぜできなかったのか」「どこに問題があったのか」といった問いを立てながら評価していきます。
このようにPDCAの各フェーズに5W1Hを組み合わせることで、改善活動のサイクルがぶれずに、かつ実効性のあるものになっていきます。継続的な改善には「問いを繰り返す習慣」が欠かせません。5W1Hはそのための頼もしい土台となります。
マインドマップとの統合で発想を広げる
発想を広げたいときや、アイデアを自由に出したいときに役立つのが「マインドマップ」です。中心となるキーワードから枝を伸ばすように関連するアイデアや情報を可視化していくことで、思考が活性化され、見落としていた視点に気づけることがあります。
マインドマップと5W1Hを組み合わせることで、発想の幅と構造の明確さを同時に得ることができます。たとえば、マインドマップの中心に「新商品開発」と書き、その周囲に「What(どんな商品?)」「Who(誰のために?)」「Why(なぜ必要?)」など、5W1Hの問いを枝として配置します。そこからさらにアイデアを広げていくと、思いつきの段階であっても自然と整理された形になります。
この方法は、会議のブレインストーミングや個人の企画メモとしても使いやすく、「自由な発想」と「構造的な整理」という一見相反する要素を、バランスよく共存させることができます。5W1Hを枠組みとして使いながら、マインドマップで創造性を伸ばす。この組み合わせは、特に柔軟な発想が求められる現場で力を発揮します。
自己分析にも活かせる5W1Hの考え方
5W1Hは、ビジネスや現場の業務を整理するためのツールとして知られていますが、その活用範囲は実はもっと広がりがあります。たとえば、自分自身の考えや感情、これからのキャリアについて深く見つめ直す「自己分析」の場面でも、このフレームは非常に役に立ちます。
自分の内面を見つめるという行為は、ときに漠然としていて掴みどころがなく、不安を伴うものです。しかし、そこで「何が起きているのか」「なぜそう思ったのか」「どうすればよかったのか」と丁寧に問いを重ねることによって、混乱していた思考がだんだんと整理され、気づきが生まれていきます。
この章では、5W1Hを自己分析に応用する方法について、具体的な観点ごとにご紹介していきます。
自分の行動を振り返るフレームとして
日々の仕事や生活のなかで、「なんとなくうまくいかなかった」「どうしてもモヤモヤする」という場面は誰にでもあります。そんなとき、ただ感情に流されるのではなく、行動の背景や意味を5W1Hで見つめてみると、自分でも驚くほど冷静になれることがあります。
たとえば、あるプレゼンがうまくいかなかったと感じた場合、「What:何がうまくいかなかったのか」「Why:なぜそうなってしまったのか」「Who:誰に対して伝えたのか」「When:どのタイミングだったか」「Where:どの場面だったか」「How:どう進めていたのか」という問いをひとつずつ自分に投げかけてみると、失敗の原因や改善のヒントが見えてきます。
このような振り返りを繰り返すことで、ただの失敗や後悔が、次への学びとして積み重なっていきます。何気ない日常の出来事にも、自分自身の癖や傾向が表れていることに気づけるようになると、より柔軟で前向きな自己理解が進んでいくのです。
キャリア設計の道筋を明確にする
将来のキャリアについて考えるとき、「どうしたらよいか分からない」「やりたいことがはっきりしない」と感じることもあるかもしれません。そんなときにも、5W1Hの問いはとても有効なサポートになります。
たとえば、「What:自分はどんな仕事をしていきたいのか」「Why:なぜその仕事に惹かれるのか」「Who:どんな人たちと働きたいのか」「When:どのタイミングで変化を望んでいるのか」「Where:どの場所や環境で働くのが理想か」「How:どうすればその状態に近づけるのか」と問いを重ねていくと、自分の価値観や願望が徐々に形になっていきます。
このプロセスを通して、漠然とした「不安」や「焦り」が、「方向性」や「優先順位」へと変わっていきます。具体的な答えがすぐに出なくても構いません。問いを立てて、それについて考え続けること自体が、自分の中にある想いや軸を見つけていくきっかけになります。
また、定期的にこの問いを見直すことで、環境の変化や自分自身の成長に合わせてキャリア設計をアップデートしていくこともできます。人生は一度きりですが、そのなかで自分が本当に納得できる道を選ぶためのヒントは、こうした日々の問いの積み重ねのなかにあるのかもしれません。
価値観の整理に使う方法
仕事をする上でも、プライベートでも、人はそれぞれに大切にしている価値観を持っています。でも、ふだんはあまりそれを意識することなく、目の前の出来事に追われて過ごしてしまいがちです。そんなとき、5W1Hを使って自分の価値観を掘り下げてみると、驚くほどクリアに自分の本音と向き合えるようになります。
たとえば、「なぜその発言に引っかかったのか」「なぜこの仕事にやりがいを感じるのか」「誰との時間が自分にとって心地よいのか」「どんな場面で安心できると感じるのか」など、日常のなかで心が動いた瞬間に対して問いを投げてみると、自分が何を大切にしているかが浮かび上がってきます。
このようにして見つけた価値観は、自分が選択や判断をするときの指針になります。たとえば、「人との信頼関係を大切にしたい」という価値観を意識している人は、転職や異動の際にも、「どんな職場なら信頼を築きやすいか」という視点で判断できるようになります。
自分の心の中にあるものを言語化するのは、最初は少し勇気がいる作業かもしれません。でも、それを丁寧に問いかけることで、無理に答えを出さなくても、自分の輪郭が少しずつはっきりしてくる感覚を持てるようになります。
5W1Hを学びたい人におすすめの習慣やツール

5W1Hは、非常に身近でありながらも奥深い考え方です。その効果を十分に引き出すためには、ただ知識として理解するだけでなく、日々の中で何度も使い、自分の中で馴染ませていくことがとても大切です。そのためには、自然と身につけられるような「習慣」や「ツール」を活用することが大きな助けとなります。
この章では、5W1Hの思考を生活や仕事のなかに無理なく取り入れ、少しずつ使いこなせるようになるためのヒントをご紹介していきます。小さな工夫を積み重ねていくことで、やがて5W1Hはあなた自身の思考の癖として定着していくはずです。
紙に書くことで思考が整理される理由
頭の中だけで考えていると、思いついたことがあちこちに飛び散ってしまい、なかなか整理がつかないことがあります。そんなときにとても効果的なのが、「紙に書き出す」というシンプルな方法です。
たとえば、何か問題や悩みを感じているとき、ノートやメモ帳に「Why」「What」「Who」「When」「Where」「How」と6つの問いを書き出し、それぞれに対して自分なりに答えてみるだけでも、頭の中が驚くほどすっきりしてくることがあります。
この作業の良いところは、言葉にすることで自分の考えを客観的に見ることができる点です。特に、感情が先行しているときや、選択に迷っているときには、紙に書きながら「自分はこう感じていたんだ」と気づけることが多々あります。
また、手を動かして書くという行為そのものが、考える時間をつくり、焦りや不安を落ち着かせてくれる作用もあります。特別なスキルは不要で、必要なのは紙とペンだけ。ほんの数分で始められるこの習慣は、思考力を育てる最もシンプルで効果的な方法のひとつです。
フレームワークノートやアプリを活用する
もし紙に書くことが苦手だったり、もっとデジタルで効率的に管理したいという方であれば、フレームワークを活用したノートやアプリもおすすめです。最近では、「5W1Hの問いに沿って記録する」ことに特化したテンプレートノートや、考えを整理するためのアプリが多く登場しています。
たとえば、手帳の1ページを6つに区切って、それぞれに「Why」「What」などのラベルをつけて日々の出来事や気づきを書き込んでいくと、数週間後には自分の考えのパターンや行動の傾向が見えてくるようになります。
アプリの場合は、思いついたときにすぐにメモできるという利点があります。通勤中や空き時間など、ちょっとしたすき間を使って、ふと浮かんだ疑問や感想を5W1Hで分類してメモしておくと、それが後の大きなヒントになることもあるでしょう。
重要なのは、記録を「きれいに整えること」ではなく、「自分にとって役立つ問いを残すこと」です。道具にこだわるよりも、気軽に始められて、続けやすいことを第一に考えると、習慣として根づきやすくなります。
学習会やワークショップに参加する意義
もっと深く5W1Hを学びたい、他の人の使い方を知ってみたいと感じたときには、セミナーやワークショップなどに参加してみるのもよい方法です。特にビジネススキルや思考整理をテーマにした講座では、5W1Hを中心としたフレームワークの実践方法を学べる場が数多くあります。
こうした場の魅力は、実際に手を動かして考えたり、他の参加者と意見交換をしたりする中で、自分では気づけなかった視点や使い方に触れられることです。「自分は“Why”の視点に偏りがちだったな」「“When”を曖昧にしていたせいで行動が遅れていたのかも」といった気づきが得られることもあります。
また、他人の問いや考え方を聞くことで、自分の視野が広がり、「問いをつくる力」が磨かれていきます。これは、ひとりで学ぶだけでは得がたい学びの形です。
さらに、学習会で得た知識や経験を持ち帰り、日常の業務や生活に応用することで、5W1Hが「特別なもの」ではなく「自分の一部」として機能し始めるようになります。学びの場に一歩踏み出すことで、5W1Hがより深く、実感をともなって定着していくのです。
5W1Hの活用で変化する仕事への向き合い方
毎日の仕事に追われていると、「とりあえず目の前のことをこなすだけで精一杯」と感じてしまうことがあります。やるべきタスクは次から次へと発生し、考える暇もなく動いているうちに、いつの間にか目的を見失ったり、仕事がただの作業になってしまったりすることもあるでしょう。
そんな時こそ、5W1Hというシンプルな問いかけが、仕事との向き合い方をそっと整えてくれる存在になります。何かを始めるとき、迷ったとき、立ち止まって考えるべきタイミングで、6つの疑問を心に浮かべてみる。それだけで、今の自分の位置や向かいたい方向が少しずつ見えてくるのです。
この章では、5W1Hを活用することによって、仕事との関係性にどんな変化が生まれるのかを、感情面や思考面、そして人間関係の側面から掘り下げていきます。
不安や迷いが減ることで自信が生まれる
仕事に対して不安や迷いを感じるとき、それは「今、自分が何をしているのかがよくわからない」という状態から生まれていることが多いものです。何となく進めているけれど、これでいいのだろうかと不安になる。相手がどう感じているのか分からず、自分の判断に自信が持てない。そんな気持ちは、誰にでもあるものです。
そんなときに、5W1Hの問いを自分に投げかけてみると、不思議なほど心が落ち着いてきます。「今やっている仕事は、何のために(Why)?」「自分は何をする役割だったのか(What/Who)?」といった問いを重ねていくことで、少しずつ霧が晴れるように道筋が見えてきます。
そして、自分の中で納得できる答えが見つかると、「これでいいんだ」「ここから始めればいいんだ」と、気持ちがスッと前を向くようになります。この小さな安心感の積み重ねが、やがて大きな自信へと変わっていきます。
自信は、「うまくやれる」という確信ではなく、「自分の考えや行動に意味があると感じられること」から生まれます。5W1Hを通じて、自分の中に答えを見つけていく過程そのものが、心の支えになってくれるのです。
論理的に考えられるようになるメリット
仕事を円滑に進めるうえで、論理的に物事を整理して考える力はとても重要です。感覚的な判断に頼りすぎると、周囲との意識にズレが生まれたり、伝えたいことがうまく伝わらなかったりすることがあります。
5W1Hを習慣的に使うようになると、自然と「何が問題なのか」「なぜこの方法を選んだのか」「どこに注目すべきか」といった思考が、順序立てて整理されるようになります。これは、ロジカルシンキングの基礎を育てる上でも非常に有効なアプローチです。
また、自分の考えを誰かに伝えるときにも、5W1Hを意識して話すだけで、ぐっと分かりやすくなります。「それってどういうこと?」「結局どうしたいの?」といった指摘を受けることが減り、信頼を得やすくなるでしょう。
このように、5W1Hはただ思考を整理するだけでなく、相手との対話の質も高めてくれる存在です。論理的に話すことは、決して堅苦しいことではありません。むしろ、相手を思いやるやさしさの表れでもあります。考えが伝わるということは、それだけで人との関係をスムーズにし、仕事をより快適にしてくれます。
他人との関係性にもポジティブな影響が生まれる
5W1Hは、自分自身のための思考ツールでありながら、実は他人とのコミュニケーションにおいても大きな力を発揮します。なぜなら、このフレームは「相手に正確に、わかりやすく伝えるための問い」でもあるからです。
たとえば、指示を出すときに「これをやっておいて」とだけ言うよりも、「いつまでに」「どこで」「どのように」と具体的に伝えることで、相手は迷うことなく動けるようになります。そして、そうしたやり取りを続けるうちに、お互いの信頼や安心感が少しずつ育っていきます。
また、相手が困っている様子のとき、「何に困っているの?」「いつからそうだったの?」と優しく問いかけることで、相手の状況を理解しやすくなり、寄り添うコミュニケーションが可能になります。これは、上司と部下、同僚同士、さらには顧客や取引先との関係性にも通じる大切な姿勢です。
5W1Hを使うことは、単に情報を整理するためだけではありません。それは、相手の立場を想像し、言葉の奥にある気持ちをくみ取るための、やさしいまなざしでもあるのです。
まとめ
仕事の中で何かに迷ったり、立ち止まって考えたくなったりする場面は、誰にでも訪れるものです。そんなとき、複雑な状況を無理に解決しようとするのではなく、まずは「何が起きているのか」「なぜそうなったのか」「どうすればよいか」と、シンプルな問いを自分に投げかけてみることが、実はとても力強い一歩になります。
5W1Hは、そんな問いをやさしく導いてくれる枠組みです。報告や説明をわかりやすく整えるための道具であるだけでなく、悩みを整理し、自信を取り戻し、人とのつながりを深めるための橋にもなってくれます。
今回ご紹介したように、5W1Hは使い方ひとつで、実務、企画、マネジメント、そして自己理解にまで応用することができます。そしてそのすべてに共通しているのは、「問いを立てることは、自分と向き合うこと」だという点です。
慌ただしく過ぎていく日々のなかで、つい見過ごしてしまう大切なことに気づくために。人と仕事との関係を、もう一度見直してみるために。5W1Hは、決して派手ではないけれど、静かに、そして確かに役立ってくれる思考の道具です。
これからの仕事を、もっと納得感のあるものにしたい。もっと自分らしい働き方を見つけたい。そんな気持ちが少しでも芽生えたとき、ぜひ5W1Hをそばに置いてみてください。きっと、あなたらしい答えにたどり着く手助けをしてくれるはずです。
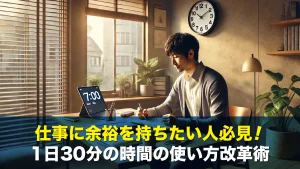

![診療情報管理士のお仕事とは?仕事内容・やりがい・スキル・経験、どんな資格がいかせるの?[職種図鑑]](https://hatachie.com/wp-content/uploads/2024/11/job-category-table0018-150x150.webp)