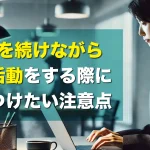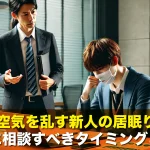仕事をしていると、「なんだか判断がうまくいかない」「段取りが狂ってばかり」と感じることはありませんか?実はその背景には、「計画力の弱さ」や「視点の偏り」が潜んでいるかもしれません。
多面的な見方を持ち、状況に応じた柔軟な判断ができる人ほど、仕事の中で的確に動き、周囲との信頼関係も築きやすくなります。また、その思考をもとにした計画力は、限られた時間とリソースの中で成果を上げるうえで、欠かせない土台となるのです。
この記事では、「計画力がないことで起こる落とし穴」から、「仕事に役立つ多面的な思考の育て方」「計画力を無理なく鍛えるコツ」までを、やさしく丁寧に解説していきます。視野を広げ、先を見通しながら働くためのヒントを探している方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
この記事の目次(タップでジャンプ)
多面的な思考が仕事で求められる理由とは

仕事をしていると、目の前のタスクに集中するあまり、つい一つの視点だけで物事を捉えてしまうことがあります。しかし、現代の職場環境は非常に多様で変化が激しく、さまざまな人や考え方が入り交じる中で判断を求められる場面が多くなっています。そのような状況では、一面的な見方だけでは正確な判断が難しく、結果的に仕事の質やスピードに影響してしまうこともあるのです。そこで求められるのが「多面的な思考」です。
多面的に考えるとは、物事をいくつかの異なる角度から見たり、複数の視点で状況を分析したりすることを意味します。それは、単に情報を多く集めるという意味だけではなく、「自分とは違う価値観に目を向けること」「立場や背景の異なる人の意見を想像すること」「先入観を脇に置いて状況を見ること」など、柔軟で開かれた思考のスタンスを指します。このような思考を身につけることで、複雑な問題にも冷静に対応できるようになり、仕事の精度や人間関係にも良い影響を与えるようになります。
多面的な思考は決して特別な才能ではなく、日々の小さな意識や習慣によって誰でも少しずつ育てることができます。たとえば、ある業務でトラブルが起きたとき、「誰の責任か」と考えるのではなく、「なぜこうなったのか」「どうすれば防げたのか」「ほかの部署からはどう見えているか」など、複数の視点から状況をとらえることが、次の一手を考える上でとても役に立ちます。特にチームで仕事を進める場面では、他の人の立場や考え方を理解しようとする姿勢が、信頼関係や成果につながる場面も多くあります。
この章では、多面的な思考がなぜ仕事において求められているのか、どのような力が働いているのかを、3つの観点から丁寧に見ていきます。
視点の数が判断の質を左右する
一つの判断を下す際に、どれだけの視点を持てるかは、その判断の精度や納得感に大きく影響します。たとえば、業務の改善を提案する場面でも、自分のやりやすさだけでなく、同僚や顧客、コスト面、時間面など、複数の側面から考えることができれば、より現実的で受け入れられやすい提案になります。視点が多ければ多いほど、リスクの見落としを防ぎ、説得力のある選択肢を用意することができるのです。反対に、一つの視点しかないと、自分では正しいと思っていても他者からは不合理に見える可能性もあります。
特に、リーダーやマネジメント層に近い立場になると、あらゆる場面で多様な判断を求められるため、視点の広さが直接的に成果につながります。ただし、この力は一朝一夕では身につきません。日々の業務やコミュニケーションの中で意識的に取り組むことが、視点を育てる第一歩となります。
他者理解と状況把握力の向上
多面的な見方ができるようになると、自然と他人の意見や背景を理解する力も高まります。たとえば、職場での会話の中で「なぜこの人はこう言ったのだろう?」と立ち止まって考えることは、ただ聞くよりもずっと深い理解につながります。これは単に思いやりを持つということだけではなく、仕事上の信頼関係を築くうえで非常に大切な視点です。相手の事情や考え方に寄り添って接することで、誤解や摩擦を減らすことができ、チーム全体の雰囲気も良くなっていきます。
また、状況を全体として把握する能力も向上します。目の前の作業だけでなく、その背景にある目的や全体の流れを意識することで、業務の質が高まります。たとえば、上司からの指示が少し曖昧でも、その意図や全体像を考えながら行動できれば、的確なアウトプットを出すことが可能になります。このような状況把握力は、周囲からの信頼にもつながり、仕事をスムーズに進める大きな支えになります。
柔軟性と応用力を持つ働き方へ
最後に、多面的な思考を持つことで、仕事の進め方にも柔軟性と応用力が生まれます。一つの方法に固執せず、状況や相手に応じて方法を変えることができれば、どんな変化にも対応しやすくなります。これは、特にトラブルや急な予定変更など、予測が難しい場面で大きな強みになります。
また、これまでの経験を応用する力も養われます。たとえば、以前に別の部署でうまくいった手法を、現在の仕事に応用することで、思わぬ成果が得られることがあります。多面的に物事をとらえる習慣があると、「このアイデアは今の仕事にも使えるかもしれない」という気づきが自然に生まれやすくなるのです。このようにして、柔軟で応用力のある働き方ができるようになると、変化に強く、自分の持ち味を発揮できる環境でより豊かに働けるようになります。
一面的な思考がもたらすリスク
日々の仕事の中で、誰しもが時間に追われ、効率やスピードを重視するあまり、物事を単一の視点で判断してしまうことがあります。しかし、一見効率的に見えるその思考は、長い目で見れば思わぬミスや誤解、組織全体の停滞を招く可能性があります。一面的な思考とは、ある一つの見方だけで物事を判断し、他の可能性や視点を無視したり軽視したりする傾向のことを指します。たとえば、自分の経験だけに基づいて判断する、目の前の数字だけで良し悪しを決める、または誰かの意見に偏りすぎて他の意見を聞かなくなるなど、思考の幅が狭くなった状態です。
仕事においてこのような状態が続くと、問題の根本原因にたどり着けなかったり、関係者との意思疎通が不十分になったりして、結果的にトラブルの発生や信頼の低下につながります。ここでは、一面的な思考がもたらす具体的なリスクについて、3つの角度から考えていきましょう。
見落としによるミスやトラブルの増加
一つの視点にとらわれてしまうと、重要な情報や可能性を見落とすリスクが高まります。たとえば、クライアントとの打ち合わせで、費用面だけを重視して提案を決定した場合、納期や品質、サポート体制といった他の要素が疎かになり、結果として顧客の満足度が下がってしまうことがあります。さらに、社内においても、前回うまくいった方法だからといって同じ手順を繰り返した結果、状況が違うことに気づかずトラブルを招くこともあるのです。
見落としは必ずしも注意不足からだけ起きるものではありません。むしろ、思い込みや過去の成功体験が強すぎることで、ほかの視点を拒んでしまうという心理的なバイアスが原因になることが多くあります。このような落とし穴を避けるためにも、常に「ほかに見えていないことはないか?」「別の角度から見たらどう見えるか?」と問いかけながら行動することが大切です。
偏見や先入観が業務効率を下げる理由
一面的な思考には、偏見や先入観も深く関わっています。たとえば、「この部署はいつも遅い」「あの人は頼りない」といったラベリングがあると、本来その人や部署が持っている力や背景を正しく評価できなくなります。そうなると、本来スムーズに協力できるはずの仕事も、無駄な遠回りをしてしまったり、意図せぬ摩擦を生む原因となってしまいます。
また、偏見は判断力そのものを曇らせます。ある案件で以前ミスをした社員に同じ仕事を任せたくないと考えたとしても、成長の機会や現在の実力を見ようとしなければ、その人の変化を正当に評価することができません。その結果、過去の失敗がずっと尾を引き、チームのモチベーション低下につながる可能性もあります。偏見を取り払うには、自分が持っている思い込みを一度疑ってみる姿勢が必要です。そして、感情や印象だけでなく、客観的な事実に目を向けて判断するように意識することで、より公平で建設的な仕事の進め方ができるようになります。
単純な判断が人間関係にも影響する
一面的な考え方は、業務の進行だけでなく、人との関わり方にも影響を及ぼします。たとえば、ある同僚が遅刻をしたときに、「だらしない人だ」と即座に決めつけてしまうと、その人に対して冷たい態度を取ってしまうかもしれません。しかし、実際には家庭の事情や突発的なトラブルがあったのかもしれません。事情を聞かずに表面だけで判断すると、相手の信頼を損ない、職場全体の雰囲気がぎくしゃくしてしまうこともあります。
また、上司や部下との間でも、背景を深く理解しようとせずに一方的な見方だけで行動すると、意思疎通がうまくいかなくなり、すれ違いや誤解が生まれることになります。こうした小さなズレが積み重なることで、職場の人間関係にヒビが入り、ストレスや離職の原因になるケースもあるのです。多面的な思考があると、こうした場面でも冷静に状況を見極め、相手に配慮した対応が取りやすくなります。相手の立場を思いやりながら対応することは、働くうえでとても大きな安心感と信頼感を育む要素となります。
多面的な見方を日常で身につけるには

多面的な見方が仕事において大きな役割を果たすことは理解していても、それをどうやって自分の思考に根付かせるかはまた別の課題です。特に、これまでの習慣や考え方に無意識の偏りがある場合は、新たな視点を取り入れることに抵抗を感じることもあるかもしれません。しかし、多面的に考える力は、特別な訓練や才能が必要なわけではなく、日々のちょっとした意識や習慣によって少しずつ育てていくことができます。ここでは、日常生活や業務の中で実践できる工夫を3つの観点から紹介していきます。
意見の違いに価値を見出す習慣
まずは、他人と自分の意見が異なったときに「なぜそう思うのか?」と相手に対して興味を持つ姿勢を大切にすることが、多面的な視点を育む大きな第一歩になります。自分の考えと違う意見に出会うと、人はついそれを否定的に捉えてしまいがちです。しかし、そこで一度立ち止まり、相手の意見の背景や意図を探ろうとすることで、自分の視野が一気に広がることがあります。
たとえば、会議中に自分の提案に対して否定的な意見が出たとき、「なぜ反対するのか」を掘り下げていくことで、リスクへの気づきや視点の偏りに気づける可能性があります。こうした対話の積み重ねが、自然と多面的な考え方を身につける土台となります。自分とは異なる考えを持つ人がいることを前提にし、違いから学ぶという意識を持つことが、柔軟で奥行きのある思考を形作ってくれるのです。
情報を分けて整理するトレーニング
日常の中で入ってくる情報をそのまま受け取るのではなく、「これはどんな側面があるのか」「どんな見方ができるのか」といった問いを立てながら分類していくことも、多面的な視点を育てるうえで非常に有効です。たとえば、新しいプロジェクトの説明を聞いたときに、「顧客にとっての価値」「社内での負荷」「スケジュールの現実性」など、いくつかの観点に分けてメモを取る習慣を持つだけで、自然と複数の視点で物事を見るクセがついていきます。
こうした情報の分け方は、慣れてくると直感的にできるようになりますが、最初は意識的に「切り口を変えてみる」ことが大切です。たとえば、「自分が新人だったらどう思うか」「管理職だったらどんな点に注目するか」といった仮想的な立場に立って情報を見直してみるのもよい方法です。日常のちょっとしたニュースや出来事に対しても、「これは一つの側面だけで判断していないか?」と問いかけてみることで、自然と視野が広がっていく感覚がつかめるようになります。
複数の立場で物事を考える思考練習
最後に紹介するのは、「自分以外の立場に立って物事を考える」という思考のシミュレーションです。これは、まさに多面的な視点を身につけるための実践的なトレーニングであり、仕事の中でも非常に役立つ考え方です。たとえば、あるプロジェクトの進行において、「上司の立場だったら何を最優先にするか」「クライアントの視点から見ると不安な点はどこか」「同僚が感じるであろう負担は何か」といったように、立場ごとの思考を丁寧に想像していくことで、よりバランスの取れた判断ができるようになります。
この練習は、実際の業務の中でも応用しやすく、自分の意見を主張するだけでなく、「A案にはこういう良さがあり、B案にはこうした懸念がある」といったように、対比的に考える力も養われていきます。さらに、こうした視点をもとに提案や会話を組み立てると、相手の納得を得やすくなるため、コミュニケーションの質も自然と高まります。日常の中で「もし自分があの人の立場だったら」と想像する習慣を持つことが、多面的な思考を定着させるうえでとても有効です。
仕事の中で計画力が問われる場面
仕事を進める上で、計画力というのは単なる予定表作成の能力を超えた、大切な基盤のひとつです。計画力とは、ゴールに向けて具体的な手順やタイミングを考え、状況に応じて調整を加えながら目的を達成するための力を指します。計画を立てるだけでなく、それを実行に移し、柔軟に運用していくことまでを含むスキルです。
この力がしっかり備わっていると、突発的な変更があっても混乱せずに対応でき、他者との連携もスムーズになります。一方、計画力が弱いと、仕事の優先順位が曖昧になったり、納期を守れなかったりと、信頼にも影響を及ぼすことが出てきます。この章では、実際の業務の中で計画力がどのように問われるのか、その具体的な場面を3つの角度から見ていきましょう。
タスクの優先順位を決めるとき
複数の仕事が同時に舞い込んできたとき、どれから手をつけるべきかを見極める力が求められます。すべての業務が「重要」に見えてしまう中で、期限・関係者・影響範囲・業務量といった要素を冷静に比較しながら優先順位を定めることが必要です。
たとえば、同時に3件の依頼を受けた場合、納期が一番近いものを最優先にするのが基本ですが、それだけでは判断できないこともあります。クライアントの信頼関係を築くために一つひとつ丁寧に進めたいケースもあれば、社内調整が必要な案件は早めに着手しないと後々自分がボトルネックになる可能性もあります。このように、ただ早いものから順に対応するのではなく、全体を俯瞰して順番を決めるには計画力が必要です。そして、その判断には経験と柔軟な思考が欠かせません。
納期や予算とのバランス調整
多くの業務は、時間や費用といった制約の中で成り立っています。その中で成果を最大化させるには、限られたリソースの中でどこに力を入れ、どこを削るかを見極める必要があります。ここで問われるのが「計画的にやりくりする力」です。
たとえば、10日で終わらせなければならないプロジェクトがあるとして、その中に優先度の高い5つの工程があるとします。すべてを完璧にこなそうとすると時間が足りない可能性があるため、最初の段階で各作業にどのくらい時間を割くのかをあらかじめ決めておくことが非常に重要です。予算面でも同様で、すべての工程に同じコストをかけるのではなく、成果に直結する部分には多少多めに投資し、他は効率化や外部活用で抑えるという視点が求められます。
計画力が高い人は、こうした制約条件を前提に置いたうえで現実的なスケジュールを組み、全体を調整することで質の高いアウトプットを実現しています。想定外の変更が起きた場合にも、その影響範囲と代替案をすぐに考えられるため、結果としてチームやクライアントからの信頼も高まっていきます。
チームでの連携や業務設計
計画力は、自分の仕事を整えるだけでなく、チーム全体の働き方にも深く関わります。たとえばプロジェクトを複数人で進める場合、誰がいつ何をやるのか、各工程がどのようにつながっているのかを整理する必要があります。そこに無理や抜けがあれば、どこかの工程で停滞が起こり、結果的に全体の遅れやトラブルに発展することもあります。
そのため、仕事を前に進めるうえで「設計図のような役割」を果たすのが、計画力を持った人の存在です。役割分担を明確にすることや、相手の作業完了を前提に自分のスケジュールを組むといった「つなぎの意識」を持つことが、スムーズなチーム運営に直結します。
また、スケジュールや進行状況を可視化するツールを活用しながら、チーム全体が同じ目線で動けるようにするのも大切なポイントです。こうした全体像を見渡しながら細部を調整できる力は、ただ段取りが上手というレベルを超えて、職場全体のパフォーマンスに大きく貢献します。個人としてだけでなく、周囲の力を引き出す計画的な設計ができる人は、組織にとって非常に頼もしい存在となります。
計画力を養うための基本ステップ

計画力は、あらかじめ備わっている能力ではなく、意識的な行動と工夫の積み重ねによって育てていくことができます。ただし、日々の忙しさの中では「とにかく目の前の仕事をこなすだけで精一杯」と感じてしまい、計画を立てること自体が後回しになることも少なくありません。しかし、仕事の質とスピードを両立させたいと考えるならば、自分に合った方法で計画力を鍛えていくことはとても価値のある取り組みです。
ここでは、誰でも実践できる「計画力を養うための基本ステップ」を3つの視点から紹介していきます。日常の中で少しずつ取り入れていくことで、確実に考える力と行動の整合性が高まっていくはずです。
目標設定と逆算思考の基本
計画力を高めるうえで、まず必要なのは「ゴールを明確にすること」です。目的が曖昧なままでは、途中でブレが生じたり、手順を見失ってしまう可能性が高まります。そこで意識したいのが、逆算思考です。これは「ゴールから逆に手順をたどって、今やるべきことを明らかにする」考え方であり、計画的な行動の核となる考え方です。
たとえば、ある仕事を2週間後の会議で発表する必要があるとき、まず発表当日までに何を準備すべきかをすべて書き出し、それぞれに必要な時間と順序を考えます。そのうえで、「では今日すべきことは何か」「来週までに終わらせておくべき項目はどれか」を整理していきます。こうして「今やるべきこと」が明確になると、焦りや迷いが減り、行動の質も安定していきます。
目標設定は大きく構えすぎると現実味がなくなってしまうため、まずは「できる範囲の具体的なゴール」を決めることが大切です。そして、ゴールに近づくためのステップを少しずつ積み上げていく意識を持つことで、自然と行動に芯が通り、ブレの少ない進行ができるようになります。
スケジューリングと時間配分の考え方
計画力の中でも特に実践的な要素が、スケジューリングと時間配分です。どんなに素晴らしい計画を立てたとしても、実際に動ける時間や他の仕事との兼ね合いが考慮されていなければ、計画倒れになる可能性が高まります。そこで意識したいのは、「時間の見積もり」と「余白の確保」です。
まず、ひとつの作業にどれだけ時間がかかるのかを見積もる力は、経験を重ねることで徐々に磨かれていきます。最初は予想が外れることもありますが、「この作業には毎回これくらいの時間が必要だった」と振り返ることで、次回以降の計画精度は確実に上がります。また、予定が詰まりすぎていると、少しの遅れが全体に影響を与えてしまうため、あえて「余白」をスケジュールの中に設けておくことも重要です。
さらに、仕事の優先順位によって、時間の使い方を変えることも大切です。大きな決断やクリエイティブな仕事には、集中力が高い時間帯を割り当てるなど、自分のコンディションに応じて柔軟に組み替える意識を持つと、計画がより現実的なものになっていきます。
振り返りと改善で精度を高める方法
計画力は、一度身につけたら終わりというものではありません。計画を立てて実行したあとは、必ず「振り返り」を行うことが、次の計画の質を高める鍵となります。この振り返りによって、自分の思考や行動のクセ、時間配分の誤差、予定外の要因などを客観的に見直すことができます。
たとえば、1週間の終わりに「どの作業に時間がかかりすぎたか」「予定どおり進んだ理由は何か」「予想と違った点はどこか」といった質問を自分に投げかけ、簡単にメモするだけでも十分です。この習慣を続けていくと、計画を立てるときに無意識にそれらを考慮できるようになり、より現実的で無理のない予定が組めるようになります。
また、振り返りの場面では、失敗を否定するのではなく「学びの種」として受け取ることが大切です。うまくいかなかった原因を冷静に分析し、次に同じ状況が来たときにどう対応するかを考えることで、経験が確実に自分の力になっていきます。継続的な改善を繰り返すことこそが、計画力を本質的に強くしてくれるのです。
多面的な視点と計画力をつなぐ思考回路
多面的な視点と計画力という2つの力は、それぞれが独立しているように見えて、実は非常に深く関わり合っています。物事をいろいろな角度から見る力があっても、それを計画に落とし込めなければ、実行にはつながりません。一方で、どんなに優れた計画を立てても、その根拠となる視点が偏っていれば、結果は想定から外れてしまうことがあります。だからこそ、両者を結びつけた「思考の流れ」を自分の中に築くことが、仕事の成果を高める上で非常に大切になります。
この章では、多面的な視点と計画力をどう結びつけていくかという思考回路について、具体的なプロセスを3つの観点から掘り下げていきます。これを意識することで、よりバランスの取れた計画と、確実性のある行動が可能になります。
複数の視点をもとに仮説を立てる
最初に大切なのは、いくつかの異なる視点から情報を集め、そこから「こうなる可能性が高い」「こうしておくとよい」という仮説を立てる力です。たとえば新しい企画を提案する際には、顧客のニーズ、競合の動き、社内リソース、現場スタッフの負担など、あらゆる視点から状況を見ていくことが求められます。そして、それぞれの視点で見えてきた事実をもとに、「この方向性なら現実的だろう」という仮説を立てていきます。
このように、仮説を立てる段階で視点を増やしておくと、後から想定外の事態が起こったときにも柔軟に対応できます。また、複数の視点を最初に意識することで、計画の精度も自然と高まり、「準備していてよかった」という安心感にもつながります。このプロセスは、仕事の進行だけでなく、問題解決や業務改善などにも応用が可能です。
情報と状況に応じて柔軟に修正する
仮説をもとに計画を立てた後も、実際の仕事の現場では常に変化が起こります。そのときに大切なのが、「一度立てた計画に固執しすぎないこと」です。たとえば、当初は順調に進む予定だったプロジェクトが、予想外の要因で遅れてしまったとします。そんなときでも、「今の状況を多面的に見直す」という視点を持っていれば、すぐに現実に合わせた調整ができます。
計画を柔軟に修正する力は、「間違いを認める勇気」でもあります。一度立てた予定を変えるのは気が引けるかもしれませんが、それをタイミングよく見直せる人こそが、チームにとって安心できる存在になります。多面的な思考が身についていれば、「他部署はどう感じているか」「この変更は顧客にどう影響するか」など、判断材料も豊かになり、納得のいく修正が可能になります。
そして、その柔軟性があるからこそ、最終的にはスムーズに成果へとつながっていくのです。計画を「絶対のもの」として扱うのではなく、「今の状況に合った最善の流れ」として捉えることで、行動がしなやかになり、結果として失敗のリスクも減っていきます。
実行と検証を繰り返して精度を上げる
最後に、多面的な視点と計画力を結びつける上で忘れてはならないのが、「実行して終わりにしない」という姿勢です。計画を実行したあとは、「どの部分がうまくいったか」「どの視点が役に立ったか」「どこを見落としていたか」といったことを丁寧に検証する必要があります。この「振り返りの質」が、次の計画に大きく影響を与えるからです。
たとえば、顧客対応においてA案とB案のどちらを提案すべきか迷った結果、多面的な視点からB案を選び、実行したとします。その結果、思ったほどの反応が得られなかった場合、「なぜその結果になったのか」を視点ごとに丁寧に見直していくことで、次に同じような場面に直面したとき、より精度の高い判断ができるようになります。
この実行と検証のサイクルを丁寧に回すことが、思考と計画の質を根本から高める方法です。多面的な視点があるからこそ、多角的に振り返ることができ、そこから得た知見がまた新たな行動へとつながっていくのです。計画力を単なる段取りの技術ではなく、思考力と組み合わせた柔軟な仕事術として活かすには、このサイクルを意識することが欠かせません。
日常業務で使えるトレーニング法

多面的な思考や計画力といったスキルは、特別な場面だけで活用するものではなく、日々の業務の中で少しずつ磨いていくことができます。そのためには、普段の仕事の進め方にちょっとした工夫を取り入れるだけで十分です。自分の中に「問いを立てる」「振り返る」「観察する」といった習慣を根づかせることで、自然と視野が広がり、行動の質が変わっていきます。
この章では、忙しい毎日でも実践できるシンプルなトレーニング方法を3つご紹介します。時間をかけずに、そして無理なく継続できる工夫ばかりですので、ぜひ自分に合った形で取り入れてみてください。
ロールプレイングによる視点切替の練習
ロールプレイングとは、本来は演習や訓練を目的に、ある役割を演じることで状況理解や対応力を高める手法ですが、これは視点を切り替える練習にも非常に効果的です。たとえば、自分が上司や取引先の立場に立って今の業務を見直してみるだけでも、新たな発見や改善点が見えてくることがあります。
たとえば、ある報告書を作成する場面で「この資料を受け取る人はどこに注目するだろう」「読みやすくするためにはどんな構成がよいだろう」といった問いを持つだけで、相手の立場に立った視点が身につきます。これは同時に、伝える力や相手への配慮にもつながっていきます。
このようなロールプレイングの考え方を応用すれば、メールの文面、会議での発言、日報の書き方など、あらゆる場面で「他者の視点を想像する力」が育まれていきます。実際に誰かと役割を交換してみるのも一つの手ですが、まずは「この業務を別の人がどう見るか」を日々考えてみるところから始めると、無理なく習慣化できます。
事例分析で思考の幅を広げる
日常業務の中で起こったことを「事例」として捉え、それを分析するという方法も、多面的な思考を育てるうえで非常に効果的です。たとえば、あるプロジェクトで思うような成果が出なかったとき、その原因を「時間が足りなかった」や「他部署との連携が悪かった」といった単一の理由で片付けるのではなく、「いくつもの視点から」要因を洗い出してみるのです。
このとき、「誰が」「どのように感じていたか」「どのタイミングで何が起きたか」「どんな前提がズレていたのか」など、要素を細かく分解して考えることが大切です。さらに、成功した事例も同じように分析することで、何がうまく作用したのかを整理できます。この習慣を持つと、似たような状況に再び直面した際に、多角的な視点から選択肢を検討する力が自然と養われます。
このトレーニングは、ひとりで行うこともできますし、チームメンバーと共有して話し合う形でも効果的です。日常の振り返りを「単なる感想」で終わらせず、「構造的に分析する場」として活用することで、視野が広がり、計画の質も次第に高まっていきます。
記録とメモで思考を可視化する
もう一つ、多面的な視点と計画力の育成に有効なのが、「記録すること」です。頭の中だけで物事を考えていると、どうしても同じ思考のパターンに偏りがちですが、文字にすることで客観的に自分の考えを見つめ直すことができます。
たとえば、朝の時点で「今日の業務の優先順位と予想される課題」を簡単にメモしておく。夕方に「実際にどうだったか」「予想外だったことは何か」「改善できる点はあるか」と振り返りを書く。このようなサイクルを継続することで、自分の思考の癖や、計画とのズレに早く気づくことができます。
また、複数の視点から書き分けてみるのも効果的です。「自分の立場」「相手の立場」「第三者の視点」といった具合に、ひとつの出来事を多角的に記述するだけで、頭の中にある思考が立体的になっていきます。この習慣は慣れるまで少し手間に感じるかもしれませんが、確実に思考の幅と深さを高めてくれる方法です。
計画力がある人に共通する思考習慣
計画力が高い人と一緒に仕事をしていると、その進行のスムーズさや予測の的確さに感心することがあります。彼らは限られた時間や情報の中でも、自信を持って優先順位を判断し、関係者との連携もうまく取りながら仕事を前に進めていきます。その裏には、特別な才能や知識だけでなく、日頃から無意識のうちに行っている「思考の習慣」があるのです。
この章では、計画力が高い人たちに共通して見られる、日常の中での思考のクセや行動パターンを3つの視点から紹介します。これらは決して難しいものではなく、誰でも意識すれば身につけられるものです。少しずつでも取り入れることで、自分自身の仕事の進め方が着実に変わっていくのを実感できるはずです。
「なぜ今これをやるのか」を考えるクセ
計画力のある人が持っている最も特徴的な思考習慣のひとつが、「目的意識を持って動くこと」です。彼らは、ただ指示されたから動くのではなく、「この仕事は全体の中でどんな意味を持っているのか」「今このタイミングでやるべき理由は何か」といった問いを常に自分に投げかけています。
たとえば、資料作成を頼まれたときでも、「誰がどんな目的でこの資料を使うのか」「どこに重点を置くべきか」を考えることで、内容の精度が大きく変わってきます。これにより、無駄な作業を減らし、本当に必要なことに時間とエネルギーを集中できるようになります。
この「なぜ今やるのか」を考えるクセは、仕事全体の流れを俯瞰する力につながり、段取りや優先順位を決めるうえでも大きな助けとなります。計画の立て方に迷ったときには、一度立ち止まって「これは何のためにやるのか?」と自問してみることで、方向性が明確になりやすくなります。
長期と短期の視点を持つ癖づけ
もうひとつの特徴は、短期的な行動だけでなく、長期的な視点を同時に持っていることです。たとえば、今日やるべきことを考えるときにも、「この先の予定にどう影響するか」「この業務は今後のどんな成果につながるか」といった見通しを持って動いています。
これは、「今さえよければいい」という場当たり的な判断を避け、将来的なコストやリスクを考慮に入れながら行動することを意味します。たとえば、早く終わらせることだけを重視してミスを増やすよりも、少し時間がかかっても丁寧に進める方が、結果的にやり直しが減って効率がよくなる場合もあります。
このように、目先の効率と将来の結果をバランスよく考える習慣が、計画の柔軟性と持続性を支えています。スケジュールを立てるときには、短期のスパンと中長期のスパンを並行して意識し、「いま何を積み上げるか」という視点を持つことで、より計画的に行動できるようになります。
常に改善を意識する振り返りの力
計画力のある人は、仕事が終わったあとも「それで終わり」にせず、必ずと言っていいほど振り返りを行っています。そして、その振り返りを次の計画に生かすことに非常に長けています。これは、成功したときも失敗したときも、自分の行動や判断を一度立ち止まって見直すことで、次回の精度を高めていこうとする姿勢です。
たとえば、会議の準備が時間通りに終わらなかった場合、「原因は作業の見積もりが甘かった」「依頼内容を正確に理解できていなかった」といった点を自分で洗い出し、それを次のスケジューリングに反映させる。このような小さな改善の積み重ねが、計画力を実践の中で育てていくのです。
また、振り返りはネガティブな意味だけではなく、「うまくいった点」を意識して確認することも大切です。「どの判断が正しかったのか」「どんな工夫が効いたのか」といったポジティブな振り返りは、自信とモチベーションにもつながります。これにより、計画を立てること自体が「反省のための作業」ではなく、「前進するための思考」へと変わっていくのです。
リーダーシップと多面的思考の関係

リーダーシップという言葉を聞くと、多くの人が「決断力」や「指示を出す力」といった一面的な能力を思い浮かべるかもしれません。しかし、現代の職場環境では、チームの多様性が進む中で、リーダーに求められる力も大きく変化しています。今、求められているのは「一つの正解を押しつける力」ではなく、「複数の意見や立場を理解し、最善の方向へと導く力」です。ここで大きな役割を果たすのが、多面的な思考です。
この章では、リーダーシップを発揮する場面でなぜ多面的な思考が必要とされるのか、そしてその視点がチーム全体にどのような影響をもたらすのかを、3つの切り口から丁寧に掘り下げていきます。
視野の広さがチームの方向性を決める
リーダーは、チームの方針や優先事項を決めるうえで、さまざまな判断を求められます。そこで大切になるのが「視野の広さ」です。目の前の数字や進捗だけを見るのではなく、メンバーの状態、クライアントの反応、業界の動向など、複数の視点を同時に捉える力が必要とされます。
たとえば、納期に遅れそうなプロジェクトがある場合、「急いで仕上げるべきだ」と一方的に考えるだけではなく、「メンバーの負担はどうか」「品質は維持できるか」「この対応が今後の信頼にどう影響するか」といったさまざまな観点から冷静に判断する必要があります。
視野が広いリーダーは、常に全体のバランスを見ながら判断を下すため、チームメンバーも安心してついていくことができます。また、周囲の環境に合わせて柔軟に対応する力も育まれるため、組織としての持続力や信頼感にもつながっていきます。
複数の意見をまとめるファシリテート力
リーダーの役割には「決めること」だけでなく、「意見を引き出し、まとめていくこと」も含まれます。多面的な思考を持っているリーダーは、異なる意見や価値観を排除せず、それぞれの立場に耳を傾ける姿勢を持っています。この姿勢は、メンバーの意見を引き出しやすくし、チームの対話を活性化させる効果があります。
たとえば会議の場面で、意見が割れているときにも、「どちらが正しいか」ではなく、「なぜそのように考えるのか」「共通する部分はあるか」を探る視点を持つことで、対立ではなく融合に導くことができます。こうした関わり方ができると、メンバーは「自分の考えが尊重されている」と感じるようになり、主体性をもって行動するようになります。
リーダーが持つべきファシリテート力とは、まとめる力というよりも、違いを活かすための土台づくりです。その土台には、多様な視点を尊重し、調和を生む姿勢が不可欠であり、まさに多面的思考が支えているのです。
一貫性と柔軟性のバランスを保つ
リーダーにとって難しいのは、「ブレない姿勢」と「変化に対応する柔軟性」を両立させることです。どちらかに偏りすぎると、強引な印象を与えたり、逆に優柔不断と見なされることもあります。そこで大切なのが、「多面的に状況を把握しつつ、自分の軸を見失わないこと」です。
たとえば、部下からの提案に対して、「それは以前にうまくいかなかった方法だから」と即座に否定するのではなく、「今回は何が違うのか」「改善点はどこか」を一度多角的に考えることで、可能性を見極める余地が生まれます。そこから自分の考えと照らし合わせ、納得感のある判断を示すことで、チーム全体にとっても安心感のある決断になります。
柔軟に対応する一方で、自分自身の信念やビジョンをしっかりと持ち続けること。このバランスを保つためには、目の前の出来事に振り回されず、多角的に状況を観察し、整理する力が欠かせません。つまり、一貫性と柔軟性の両方を支えているのが、多面的な思考にほかなりません。
仕事力を高めるための継続的な工夫
仕事を通して成果を出し続けるためには、単発のテクニックや一時的な努力だけでなく、日々の中に自然と組み込まれた「継続的な工夫」がとても大切です。特に、多面的な視点や計画力といった力は、いくら一時的に意識しても、長く使わなければ定着しません。だからこそ、小さな習慣や工夫を積み重ねて、無理なく長く続けるための仕組みづくりが求められます。
この章では、日常業務の中で無理なく続けられる3つの取り組みを紹介します。どれも、忙しい中でも「やれること」にフォーカスした工夫ですので、自分のスタイルに合わせてぜひ取り入れてみてください。
学びを習慣化する仕組みづくり
まずは、日々の学びを「一時的な知識」で終わらせず、「習慣」として取り入れていく仕組みを作ることが重要です。たとえば、業務に関連するニュースを毎朝10分だけチェックする、気になった言葉や事例をノートに書き留めておく、といったシンプルな習慣でも、積み重ねることで視点が広がっていきます。
また、読書や動画視聴といったインプットに加え、自分の言葉でまとめるアウトプットも非常に有効です。社内SNSや日報、または個人のメモでもよいので、学んだことを自分の視点で言語化しておくと、記憶にも残りやすくなります。
このように、「学ぶ→整理する→活かす」という流れを日常の中に取り入れることで、知識が蓄積されるだけでなく、考え方そのものが広がっていきます。新しい視点や考え方を柔軟に受け入れる準備ができている人ほど、計画力や多面的な判断力も育ちやすくなっていきます。
定期的なアウトプットの場を持つ
学んだことや考えたことを「形にする」ことで、気づきを深めたり、他者の視点を得る機会が生まれます。たとえば、社内で行われるミーティングで月に一度、自分の業務を振り返って簡単なプレゼンをする、または、業務改善提案を定期的に発信するなど、アウトプットの場を意識的に設けることが効果的です。
アウトプットをすると、自分の中で整理できていなかった考えが明確になったり、他人からのフィードバックで新たな視点に気づけたりすることもあります。これが、次の行動のヒントとなり、思考の幅を広げる結果につながります。
また、アウトプットを習慣化することで、「自分の考えを外に出すこと」に対する抵抗も減り、意見を伝える力や説得力も自然と養われていきます。日々の中で、アウトプットのタイミングを少しでも作るようにすると、仕事そのものが自分の成長につながっていく感覚を持ちやすくなります。
フィードバックを取り入れる意識
最後に、継続的な成長を支えるうえで非常に大切なのが「他人からのフィードバックを受け取る姿勢」です。自分の考えや行動にはどうしても主観が入るため、他者の視点を取り入れることによって、思いもよらない改善点に気づくことがあります。
たとえば、定期的に上司や同僚から「最近の業務で気になる点があったら教えてください」と問いかけるだけでも、受け取る情報の質は格段に変わります。もちろん、すべての意見をそのまま受け入れる必要はありませんが、自分の中に「耳を傾ける余白」を持っておくことが、多面的な視点を育てる上でも大きな意味を持ちます。
また、フィードバックを通じて信頼関係が築かれるという側面もあります。相手の意見に耳を傾け、真摯に応じる姿勢を見せることで、「この人には率直に伝えても大丈夫」と思ってもらえるようになります。結果として、組織の中での立ち位置や協力関係にもプラスの影響が出てきます。
まとめ
仕事において成果を上げるためには、単なる作業の効率化や知識の蓄積だけでは十分とは言えません。大切なのは、物事を多角的に捉える「多面的な視点」と、目的に向かって段階的に行動していく「計画力」の両方を、自分の中に自然な形で組み込んでいくことです。
多面的な思考は、自分とは異なる意見を尊重し、視野を広げる力を育みます。状況や立場によって見え方が変わることを理解しながら判断することは、職場での信頼関係や問題解決にも大きな影響を与えます。一方、計画力は、目的に向かって道筋を立てる力であり、効率的かつ安定した成果を生み出すための軸となります。この二つが合わさることで、状況の変化にしなやかに対応しながらも、確実に前進する力が養われていきます。
また、これらの力は決して特別な能力ではなく、日常業務の中で少しずつ鍛えていけるものです。視点を意識して話を聞く、計画を立てて行動する、振り返りを習慣化するといった小さな工夫の積み重ねが、自信と実力を確実に育てていきます。さらに、他者との対話やフィードバックを取り入れることで、自分の視野や判断の幅がより豊かに広がっていくことでしょう。
変化の早い現代の職場では、ひとつの正解にこだわるよりも、複数の見方を持ちつつ、自分なりの方針でしなやかに進んでいく姿勢が求められています。その土台となるのが、多面的な視点と計画力です。今日から、ひとつの会話やひとつのタスクの中に、少しだけ別の見方を取り入れてみる。それだけでも、あなたの仕事は確実に変わり始めるはずです。
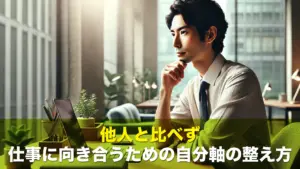
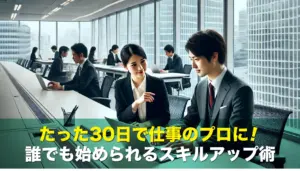

![助産師のお仕事とは?仕事内容・やりがい・スキル・資格、どんな経験がいかせるの?[職種図鑑]](https://hatachie.com/wp-content/uploads/2024/11/job-category-table0003-150x150.webp)